�X�V���F�@�@
���Ȃ���

�Ԗڂ̖K��҂ł�
�iogino�쐬���ʃJ�E���g�j
��
���Ɨ��jΰ��߰��
OGI�����HP
�M�B��cΰ��߰��
�M�B����ΰ��߰��
�^�c�ꑰ��ΰ��߰��
Mr.ogino��ΰ��߰��
��c�̗��Ɨ��jHP
�M�B�̗�HP
���{�̗�
���E�̗�HP
��
|
���{�̗�
���{�̗��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���l�E���E�O�k��
|
����t�@���Ԏ�
���킳���������@�ւ�����
�_�ސ쌧���s�����t�S�|�S�W
Tel 044-266-3420

 |
�@����t�͐����ɂ͋����R����@���Ԏ� (�������傤����ւ�����) �ƍ����܂��B�����R�@�E���c�R�V�����ƂƂ��ɁA�^���@�q�R�h�̊֓��O�R�Ƃ����܂��B |
| �@�]�˂̐̂���A���܂��܂Ȗ����t�Ƃ��ėL���ŁA���w�ɂ͑S������R�O�O���l���̎Q�q�҂��K��܂��B�_�ސ쌧�ł͂P�ԁA�S���ł��R�Ԗڂ̐l��ɂȂ�܂��B |
 |
 |
�@�厡�Q�N�i1127�j�A���Ԍ���i�Ђ�܂��˂̂�j�Ƃ������m���A�����̍߂Ő����̔�������ǂ��A�������Q�̂��������ɒH�蒅���ċ��t�Ƃ��ĕ�炵�Ă��܂����B������A���m�̖��̂������ŏM�������A�C������O�@��t�̑����������グ�܂����B |
| �@�S�Q�̖�N����������́A���̑������J��A���������Ăċ��{��ӂ�܂���ł����B�̂��ɍ���R�̑�����l�������s�r�̓r�����̒n�ɖK��A���̘b�����ɂ��܂����B�厡�R�N�i1128�j����J�R���A����Ɨ͂����킹�Đ����ɕ��Ԏ������������Ƃ������Ƃł��B |
 |
 |
�@�����P�O�N�i1813�j�ɓ��얋�{��P�P�㏫�R�A�ƐĂ���ɖK��A�����t�Ƃ��čL�܂�܂����B�ƌc�A�ƒ�A�Ɩ�����ɖK��L�����Ԃɒm��n��܂����B |
| �@��R��O�̎Q���̒������ʂ��O���ɂ͖����̋v���݂�_���}�A���Ȃǂ̂��X��������ׂĂ��܂��B�v���݂͍]�˓V�۔N�Ԃɑ�t�͌����̐E�l�E�v���q�����A�Â��������t�̖����ɂȂ�܂����B |
 |
��R��
 |
�@��R��͏��a�T�Q�N�i1977�j�J�n�W�T�O�N�̋L�O���ƂƂ��ė��c���܂����B���s�̓����̍���E�l�V������^���āA��̎l���ɂ͎l�V�����i�����V�A�����V�A�L�ړV�A�����V�j�̑������u����Ă��܂��B |
| ��R�� |
| �@��w�����ɂ͖�t�@���������u����ق��A�o�ɂɂȂ��Ă���A�����ōs����u�ʌo��v�Ŏʌo���ꂽ�o����A��[���ꂽ�ʌo�����߂��Ă��܂��B |
 |
| ��R�� |
��{��
 |
�@�O�@��t�P�O�O�O�N�䉓���œV�ۂT�N�i1834�j�������ꂽ�{���͏��a�Q�O�N�i1945�j�̋�P�ŏĎ����Ă��܂��܂����B�{����O�@��t���͑�S�R������������m��̌��f�ɂ��A��P�̂Q���O�ɉ��l�̊ω����ɑa�J���Ă����̂Ŗ����ł����B |
| ��{�� |
| �@���̖{���͑厡�Q�N�i1127�j�ɁA���Ԍ��悪���̂������ɂ���ĊC������E���グ���O�@��t�ؑ��ł��B����ƐāA�ƌc�A�ƒ�A�ƖȂǂ���w�肵�����ƂŖ��t�Ƃ��ĐM���L�����Ă������̂ł��B |
 |
| ��{�� |
 |
�@�{���͏��a�R�X�N�i1964�j�T���ɑ�{���Ƃ��čČ�����܂����B�{����O�@��t�𒆐S�ɕs�������A���������A�t����t�A�~���ω��A�����E��䶗��A�ّ��E��䶗����������Ă��܂��B�����ϔY���Ă��s�����얀�i���܁j��������Ă��܂��B |
| ��{�� |
�s����
| �@���݂̕s�����͏��a�R�X�N�i1964�j�ɍČ����ꂽ���̂ł��B�{���̕s�������͐��c�R�V�����̕s�������̖{�������������䕪�[�̕s�����������ł��B |
 |
| �s���� |
 |
�@���̕s�����͕����s��������P�ԎD���A�֓��R�U�s������V�ԎD���ƂȂ��Ă��܂��B |
| �s���� |
���p�d��
| �@���p�d���͏��a�T�W�N�i1983�j�ɑ���ꂽ�������̌��z�ŁA�ؑ��{�����̖{�i�I�ȕ����ł��B�O�@��t�v��P�P�T�O�N���L�O���Č�������Ă��܂��B���̔��p�͐^���̗l���ɂ��Ȃ��悤�A�ؗ�ɂ��Ċi������`�ł���A�ł��~�ɋ߂��������ł���Ƃ����u��e�́v�A�u���S���v���ے�����Ă��邻���ł��B |
 |
| ���p�d�� |
 |
�@�����ɂ͍O�@��t���Ȃǂ����u����Ă��܂��B������P���j���ƂQ�P���̉����Ɍ���������q�ςł��邻���ł��B |
| ���p�d�� |
| �@���p�d���̂Q�w�Ɍb�ʘa�㑜�A�O�@��t���A������t���A���E��䶗������u�B���w�ɐ^�����c�̐}���A�����E�ܒq�@�����A�n���̑�t�n��ԗ쓰�ɂ͎߉ޔ@�����������Ă��邻���ł��B |
 |
| ���p�d�� |
�o��
 |
�@�o���Ƃ͕����̌o�T��[�߂�ɂ̂��Ƃł��B�����ɂ͐��@�߉ޔ@�����������Ă��āA�u�����ő呠�o�i�����イ���������傤�j�v�Ƃ��������Ō�̖ؔő呠�o����������Ă��邻���ł��B�����P�U�N�i2004�j��J����C���L�O���Č������ꎵ�������������������ł��B |
| �o�� |
�����@
| �@�Â��Ȃ������܂��̒����@�͏��a�S�P�N�i1966�j�ɗ��c���Ă��܂��B�B�O�}�{�ܕS���q�ܓa�����������ꂽ�쑤�u���ڈ��v�ƒ�������Ɖƌ���@���E�������@�������������k���u�S�����v�A�u�ÉÌ��v�i����ȁj����Ȃ蒃�����y���ސl�̌e���̏�ƂȂ��Ă��܂��B |
 |
| �����@ |
�Z��������
 |
�@�肢���������Ƃ��ɐ_�Ђɕ�[����u�얳����ɕ��v�ƍ��ΕW��Z���������Ƃ����܂��B���������g���� �E���ʁA����ɂ��܂����A���g���̔N�����i�T�N�i1628�j�Ƒ���̊��x���߂���v���Ă��Ȃ������ł��B��ɊϐS�Ɣ͂Ȃ�m�ɂ���đ�����Y����ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B |
| �Z�������� |
���O��
| �@�������N�i1789)�Ɍ�������܂������A�吳�Q�N�i1913�j�̐k�Ђ̂��߂ɓ|��A�ڒz��A���a�Q�O�N�i1945�j�̐�Ђɂ��Ď����܂����B���a�Q�R�N�i1948�j�ɍČ����ꂽ���̂ł��B�����͊����V�N�i1795�j�ɍĒ����ꂽ���̂ő�A���̏���̏��Ƃ��ċ������Ă��܂��B |
 |
| ���O�� |
�H��t��
 |
�@���a�S�W�N�i1973�j�O�@��t���a�P�Q�O�O�N�L�O���ƂƂ��đ����A�T���ɊJ��@�v������s�Ȃ�ꂽ�����ł��B���̎��͂ɐV�l�����\�������D���̐Β��������A�юl���H�������ۂ̍������݂���Ă��邻���ł��B���N�A���r���F�肵�Ă��܂��B |
| �H��t�� |
�@���{���̑b�ł��B
�@�V�ۂT�N�i1834�j�Ɍ������ꂽ�{���̑b�ł��B���ɋK�͂̑傫�����F�ł������A���a�Q�O�N�i1945�j�̋�P�ɂ���ďĎ����Ă��܂��܂����B |
 |
| ���{���̑b�� |
 |
�@�܂�˔�ł��B
�@���a�Q�U�N�i1951�j�P���Ɍ��Ă��܂����B
�@���N�T���Q�P���ɂ܂�ˍՂ肪�Â���|�\�l��艉�|����[����邻���ł��B |
| �܂�˔� |
�@��⤁i���Ⴙ��j�˂ł��B
�@�V�ۂU�N�i1835�j���{���̔�Ȃǂ��c����Ă��܂��B�m���̓njo�֏��̂Ȃ��A��t���얀���A���𔒂����Ŋ����ꂽ��⤂����܂��B���̌�A��\�̕��X���ЂƂ�����ĕ����܂��B |
 |
| ��⤒� |
 |
�@�͐ł��B
�́A�͔�ׂɎg���Ă��������ł��B |
| �͐� |

| �@�~�������i�����܂��傤�ǂ��j�߉ޔ@�����ł��B�u�~�������v�Ƃ́A�ߑ����u���Ƃ�v���J�����Ƃ��̎p�ł��B�߂̒r�ɗאڂ���`�ł܂��A���䓰����Q�q���܂��B���a�T�Q�N�i1977�j�J�n�W�T�O�N�L�O���ƂƂ��đ����܂����B |
 |
| �~�������߉ޔ@���� |
 |
�@�ߑ����u���Ƃ�v���������悤�Ƃ��ĕ����̉��ɍ����Ă������A��X�̈���������ėU�f�����邢�͋������ĖW�Q���悤�Ƃ��܂������A�ߑ��͂�������Ƃ��Ƃ��ނ��āu���Ƃ�v���Ђ炢�������ł��B���̎��A�����G�̏�ɂ����A�E���L���đ�n���w���������ł��B |
| �~�������߉ޔ@���� |

�����Ԍ�ʈ��S�F���a
| �@���a�R�W�N�i1963�j�n�����ꂽ�����ł��B���a�S�T�N�i1970�j�P�P���A���݂̃C���h���̓��F�ɂȂ�܂����B�q���h�D�[���@���J���{�W�A�̕������@�̂悤�ł��B |
 |
| �����Ԍ�ʈ��S�F���a |
 |
�@�F���a�̒����哃�ɂ͢��@�֣���f�����Ă��܂��B�����̂��̑含�E�O�@��t������̏����~�ς̈��M�O���\������Ă��܂��B�O�@��t�A�s�������A�ʎ���\�Z�P�_���������Ă��܂��B |
| �����Ԍ�ʈ��S�F���a |
��t����
��������������
�_�ސ쌧���s�����t�����P
Tel 044-276-0050

 |
�@�@����t���Ԏ��ɗאڂ�������ŁA�싅��A�e�j�X�R�[�g�A�v�[���A�Ő��L��Ȃǂ�����܂��B�����̎���������Ȑl�H�̏��삪����Ă��āA������ ���܂������Ԃɏo��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�c�z�s���瑡��ꂽ�����뉀�u�c�G���v���l�C������܂��B |
�c�G��
���イ����
�_�ސ쌧���s�����t�����P�Ԓn ��t������
Tel 044-276-0050
| �@���a�U�Q�N�i1987�j�ɐ��s�E�c�z�s�F�D�s�s��g�T���N���L�O�����c�z�s���瑡��ꂽ�뉀�ł��B�u�c�v���c�z�s���c�A�u�G�v�͂��ꂢ�Ƃ����Ӗ��ŁA�c�z�s�̑f���炵���Ă��ꂢ�Ȍi�F���W�߂��뉀�Ƃ����Ӗ��ɂȂ邻���ł��B |
 |

 |
�@�ŏ��̖�̗����ɂ͗Y�X�������q�̑��������Ă��܂��B�ڗ����̉������[���Ŕ��������`��`���Ă��܂��B�Ԃ����Ƃ̃R���g���X�g���������ł��B |
| �@�S�R�O�O�������̓��{�ōő�̍L�����ւ钆���뉀�ɂ́A����̎���̓`���I�Ȍ������Č��B�����͐Ώ���L�Ō���A�������ƈ���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B |
 |
������
��������
�_�ސ쌧���l�s�ߌ���ߌ��Q�|�P�|�P
Tel 045-581-6358 �O���a
 |
�@�������̐������́A�u���ԎR�i���남����܁j�`�����v�Ƃ����܂��B�����͂P�R�O�O�O�]��A�h�k�͐��疜�l�Ƃ����鑂���@�̑�{�R�ł��B�ΐ쌧�\�o�ɂ��������Ԏ����������N�i1321�j���c���R�T�t�����ԎR�`�����Ɖ��߂�ꂽ�̂��n�܂�ł��B |
| �@�����Q�N�i1322�j�Ɍ���V�c�̒��ɂ�芯���ƂȂ�A�m�����̎����o���̓���ƂȂ�܂����B�����X�N�i1354�j�̌㑺��V�c�A�V���X�N�i1540�j�̌�ޗǓV�c�A���P�X�N�̌�z���V�c�A���ۂQ�N�i1645�j�̌�����V�c�ƂT����d�|�������Ƃ���u�ܒ��V�c�d�|�v�Ƃ����Ă��܂��B |
 |
 |
�@��������ɂ͑����`���A�`����������̊�i����A����ƍN�����a���N�i1615�j�痼����i���Ė��{�̋F�菊�Ƃ��Ă��܂��B���N�A���얋�{���R�\���ɑ��@�x���o�����Ƃ��ɁA�i�����ƂȂ��ő���������{�R�ƂȂ����̂ł����B |
| �O���� |
| �@�����͂P�U�O�O�O�]�̖������]���A�V�O�]�ɋy�ԓ��F���\���Ă��������ł��B�����R�P�N�i1898�j�{���̈ꕔ���o���Ď��������͂قƂ�ǂ��Ď����܂����B�����̏Z�E�����l�ߌ��Ɉړ]�����߂܂����B |
 |
| ���a |
 |
�@�Ȃ��\�o�̖P���S����̏��i�ӂ��������т̂��傤�j�ɂ������������͊����𑱂��A���݂͑������c�@�ƌĂꑑ���ȉ��������������܂����B���{�R�̈Е��Ɩʖڂ����ɕۂ��Ă��܂��B |
| ��c�� |
| �@�����S�S�N�i1911�j�Ɍ��݂̒n�A���l�̒ߌ��Ɉړ]�����������͖�T�O�����Ă̍L��ȕ~�n��L���A��ʂ̕ւ��悭�A�J���ꂽ�T���Ƃ��č��ۓI�ȑT�̍��{����Ƃ��Ĉ̗e���ւ��Ă��܂��B |
 |
| ���_�� |
 |
�@�����ɂ͒ߌ����̈ԗ�肪����܂��B���a�R�W�N�i1963�j�ߌ��ŋN�����d�Ԏ��̂łP�U�P���̑��������]���ɂȂ�܂����B�����ɂ͑��Ɂu���ؒ����̈ԗ��v�o�D�E�Ό��T���Y�̕�Ȃǂ�����܂��B�����ɂ́A�ߌ���w�A�ߌ����q��������A�w���L�����p�X�̖������S���Ă��܂��B |
| �ҖP�� |
�O����
 |
�@�������ɓ���ŏ��̖傪�O���ցi���傤����j�ł��B�吳�X�N�i1920�j�ɗ�������Ă��܂��B |
�O���t
| �@�O���t�i���傤�����j�͕����Q�N�Ɋ��������h�M�k���C����ł��B�e��Z�����j�[�̉��Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B�\�o�̑c�@�ɂ������R�{�̗��̌`���������ɂ��Ȃ�ŎO���t�Ɩ��t����ꂽ�����ł��B�n���ł͐��i������H���邱�Ƃ��ł��邻���ł��B |
 |
�O��
 |
�@�����R�V���̓S�R���N���[�g����̑������̐���ł���O��ł��B���@�̎R��Ƃ��Ă͑S���ő勉�ł��B���a�S�Q�N�i1967�j�Ɍ��Ă�ꂽ�����ł��B�Ƃɂ������h�ł��B���E�̐m���������͂���܂��B |
| �@���ʂ͎R��ƌĂ����̂ł����A��i�����j�E���z�i�ނ����j�E����i�ނ��j�̎O��E�i�����j�ɓ���Ƃ����Ӗ�����u�O��v�Ƃ����Ă��܂��B |
 |
���g��
 |
�@���g��͌�����l���ɂ��C�i��������ł��B���O���j������œ��R���̌����`���ł��B�c���̕����K�ꂽ���ɂ͊J�����邻���ł��B�P�N�̂����A�������A�ߕ��A���̑��d�v�Ȃ܂育�Ƃ̎����J�����邻���ł��B |
���{��
| �@���{��̋��{�Ƃ́A���̒��ɏZ�ޑz���̒��ł��B�����̒��Ƃ����Ē���\���Ă���Ƃ̂��Ƃł��B�������璆����A�ʓe��ւƒ����S�ԘL���������Ă��܂��B |
 |
���a
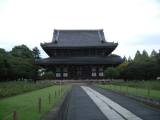 |
�@���������̒��S�����ő吳�S�N�i1915�j�ɍ��ꂽ���ꉮ�E��d�����̑��O�i���₫�j����̓a���ł��B���ʂ̊z�ɂ́u��Y��a�i�����䂤�ق��ł�j�v�Ə�����Ă��܂��B |
| �@�����ɂ͖{���̎߉ޖ���@���i�����A�ؒ��j���J���Ă���܂��B���̍��E�ɂ́A���߉ޗl�̏\���q�̈���ҁA�ޗt���҂��e���Ƃ����J���Ă��܂��B |
 |
��c��
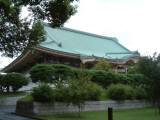 |
�@��c���i�����a�j�͓��{��̑傫�����ւ�{���ő������ő�̌����ł��B�����R�U���A�Ԍ��R�O�ԁi�T�S�D�T���j�A���s���Q�U�ԁi�S�V���j�̓S���S�؍��ł��B |
| �@��c���͊J�R���Ɩ@�������˂��{���q�a�Œ����Ƃ������ׂ����F�ł��B������~���̍L���̂Ȃ��ŁA��Q�O�O���̑m�����C�Ƃ�����A��̖@�v���s�Ȃ��邻���ł��B |
 |
���_��
 |
�@���_��͑��w����̑发�@�ł��B�T�t���S���̎��@�܂��͒h�M�k�Ɛ����ɑ��������Ƃ���ł��B�u���_�i�v�̊��|�i�������j�͓��������Y�匳���̂��̂ł��B |
�ҖP��
| �@�ҖP�ق͓���Ə��@���ڒz�������̂ŎQ�q�҂̋q�ԂƂ��Ďg���Ă���Ƃ���ł��B�������̌}�o�قɂ�����܂��B |
 |
������
 |
�@�����R�P�N(1898)�Q�ǂ̑傫�ȑD�ɂ���ĎR�`���߉��s�������̖{�������[����^��Ă��܂����B�������͑��������\�o����ړ]���čŏ��Ɍ���(�ڒz�j���ꂽ�L�O���ׂ������ł��B |
| �@�������͒����{���Ƃ��Ďg�p���Ă��܂������A���݂́u�ʔv���v�ɂȂ��Ă��܂��B�h�M�k�̂��ʔv�����u�������{�̓���ŁA���̉��ɔ[�����̏�Ɠa������܂��B |
 |
���ۘO
 |
�@���ۘO�ɂ͏��⑾�ۂ�����C�s�̍��}������Ƃ���ł��B |
�@�_���Q���ł��B
�@�_���i�����j�Ƃ͑T�@�̏C�s�m�̂��Ƃ��w���܂��B�_�̍s���܂ܐ��̗����܂܂̑�H�����Đ��i����p�ł��B |
 |
| �_���Q�� |
���������̔�
�Ȃ܂ނ�������̂�
�_�ސ쌧���l�s�ߌ��搶���P�[�P�U
Tel 045-503-3710
 |
�@���v�Q�N�i1862�j�W���Q�P���A�F���ˎ哇�Ò��`�i�����v�j�̕��ł��铇�Ëv���̍s�����C���̐�����ʉߒ��A�C�M���X�l�S�l���n�ōs��ɕ��ꍞ���ߎE�������ɂȂ�܂����B���ꂪ���������ł��B |
| �@�a��ꂽ�C�M���X�l���`���[�h�\���͏d�����Ȃ����ɂV�O�O���̂����܂Ŕn�œ����Ă��������ł��B�ǂ��Ă����F���ˎm�ɂ��Ƃǂ߂��h����S���Ȃ��Ȃ�܂����B���̔�͖����P�U�N(1883)�ߌ��̍��쑑�O�������Ă������ł��B |
 |
����������������
�Ȃ܂ނ�������͂����������
�_�ސ쌧���l�s�ߌ��搶��
 |
�@�����̂��������C���͏Z��n�ɂȂ��Ă��܂��B��p�ɁA������������̔肪����܂����B�C�M���X�͎Ӎ߂Ɖ���l�̈����n����v�����R�͂��������p�ɔh�����F�p�푈�ƂȂ�܂����B |
���l
�悱�͂�
 |
�@���l�͊��q����ɂȂ�ƊJ�����i�݁A����ł́A�k�����ɂ��A�̖�������ɂ����Ă��A�܂������ł́A���X�ؑj�ɂ�萅�c���J����܂����B |
| �@�]�˖��{�̂��Ƌ���̘Z�Y�˂̑喼�̂������āA�啔���͊��{�́A���{�����̓V�̂ɂȂ��Ă��������ł��B19���I�ɂȂ�Əh�꒬�_�ސ�Ȃǂ͐l���������A�鉺�����c���ƌ�����ׂ�قǂɂȂ��Ă��������ł��B |
 |
 |
�@�������N�i1854�j���Ęa�e�����A�����T�N�i1858�j���ďC�D�ʏ������܂����B�I�����_�A���V�A�A�p���A�����Ƃ��ʏ����������A���l�͈����U�N�i1859�j�J�`���܂����B |
| �@���{�͂����ɉ^�㏊��u���A��������E�Ƃ��Ĉȓ���O���l�����n�ɂ��܂����B�Ȗk�����{�l���Z�n�Ƃ���X�ɂ������T���ɕ������āA���l���Ɩ��t���A�e���ɖ����u�����N���S�̂����������ł��B |
 |
 |
�@�����Q�Q�N�i1889�j�S���P���Ɏs�������s����܂����B�J�`�����A���l����͐����E���E�C�Y�����A�o����A���D���E�ѐD�����A������܂����B�f�Ղ͊O�����ق̎�Ɉ����Ă��܂������A����ɉ��l���l�͐�������Ђ�ݗ������萶���חa�������肵�Ėf�Ղ̎哱�����m�����Ă����܂����B |
| �@�吳�P�Q�N�i1923�j�X���P���A�֓���k�Ђ��P���܂����B���l�s�̉Ɖ����z���͂��Ƃ��Ƃ��|�āA�̊C�Ɖ����܂����B���҂Q���]�l�A�S��Ɖ��U���˂��o���܂������A�s���̌����̓w�͂ŏ��a�S�N�i1929�j�ɂ́A�قڋ���ɕ����������ł��B |
 |
 |
�@���a�Q�O�N�i1945�j�����m�푈�ŕČR�̋�P�������A�s�X�n�͏œy�Ɖ����܂����B���ɁA�T���Q�X���̋�P�ł́A�����ҁE�s���s���҂��킹��14,157���A��ЉƉ�79,017�˂��o���A�s�X�n�̖�������ꂽ�̂ł��B |
| �@���N�W���P�T���s�킵�A���l�͘A���R�ɂ��`�p�{�݂̂X�O�p�[�Z���g�A�s�X�n�̂Q�V�p�[�Z���g���ڎ����ꕜ�����x��܂����B���N�푈�̓����ɂ�芈�������߂��A�l���͂R�T�O���l�ɂȂ蓌���Ɏ�����s�s�Ƃ��Ĕ��W�������Ă��܂��B |
 |
���l�w
�悱�͂܂���
�_�ސ쌧���l�s���捂����
 |
�@�����T�N�i1872�j�T���V���A�i��Ɖ��l�Ԃ����J�Ƃ��܂����B���̎��̉��l�w�͌��݂̍��ݐ����ؒ��w�t�߂����������ł��B���N�X���P�Q���V���Ɖ��l�Ԃ������J�Ƃ����̂ł����B���̌�A���C���{�����S���J�ʂ��܂����B |
| �@�吳�S�N�i1915�j�������t�߂ɐԃ����K�̓��ډ��l�w���a�����܂����B���̐ԃ����K�̉w�͊֓���k�Ђŕ��A���a�R�N�i1928�j���݂̒n�ɐV���l�w�w�ɂ��������܂����B |
 |
 |
�@���a�T�T�N�i1980�j���݂̉w�ɂɉ��z����A���݂̉w�ɂ͂S��ڂƂȂ��Ă��܂��B�����P�U�N�i2004�j�Q���P�����l�����S���݂ȂƂ݂炢�����ڑ�����܂����B���}�������Ƃ݂ȂƂ݂炢���̑��ݒ��ʉ^�]�J�n����֗��ɂȂ�܂����B |
���l���[����������
�悱�͂܂�[�߂�͂��Ԃ���
�_�ސ쌧���l�s�`�k��V���l�Q�|�P�S�[�Q�P
Tel 045-471-0503
| �@�����U�N�i1994�jJR�V���l�w�߂��ɉ��l���[���������ق��I�[�v�����܂����B300�~�̓��ꗿ���x�����Ċٓ��ɂ͂���Ɨ[�Ă��̂Ȃ��ɐ̂̓��{������܂��B |
 |

 |
�@���a�R�R�N�̉������C���[�W�����X���݂̒��Ɉ��삩��F�{�܂ŗL���Ȗ������[��������z�u���Ă��܂��B |

| �@���ŋ��₶���I�����s�b�N�Ȃǂ������s�Ȃ��Ă��܂��B�̂̂����肳��̊i�D�������]�ƈ����������ŔM�����Ă��܂����B |
 |
���l���؊X
�悱�͂܂��イ������
�_�ސ쌧���l�s����R�����P�P�W�[�Q
Tel 045-662-1252
 |
�@���l���؊X�͐_�˓싞���Ⓑ��V�n���؊X�ƂƂ��ɎO�咆�؊X�Ƃ����Ă��܂��B���{�ő�̒��؊X�Œ��ؗ����X�����ł��Q�O�O���ȏ゠�邻���ł��B�d���܂ł��Ԃ����߂��A�����͈ߐH�Z�̂��݂��݂܂ł������ł��B |
| �@���l�J�`��A���N�ŗ����������l�Ȃǂ̑����ŊO�l�����n���s�����Ă��������ł��B���v���N�i1861�j�ɂ͋����n�̊g���H�����s���A���l�V�c�Ƃ��̕��߂̏��n����������A���ꂪ���݂̒��؊X�ɂȂ��������ł��B |
 |
 |
�@���؊X�����{�l�X�̗l�ɐ��R�Ƌ敪�����ꂸ�{���ʃ��ɑ��߂ɋ敪������Ă���͉̂��l�V�c�̌l���̖��c�肾�����ł��B |
| �@�����̍L���E��C�Ȃǂ���吨�̐l������Ă��܂����B�L���͉؋��̌̋��Ƃ����A�Â�����C�O�ɐl�X�𑗂�o���Ă������Ȃ̂ł��B���l�؋��̑����͍L���̏o�g�ŁA�������؊X�ɍL�������������̂͂��̂��߂ł��B |
 |

 |
�@���l�ɂ͐��E�e�n����吨�̐l���K�ꂽ�����ł��B�J�`�������m�l�͓��{�ꂪ�킩�炸�A���{�l�͐��m�̌��t�⏤���ɂ��ĂقƂ�ǒm��������܂���ł����B |
| �@���`�E�L���E��C�̐��m���قœ����Ă��������l�͐��m�̌��t���b���A�܂����{�Ƃ͊����ŕM�k���ł��܂����B���̂��ߒ����l�����m�l�Ɠ��{�l�̂������ɗ����A�����⒃�̖f�ՂŒ���҂̖������ʂ������̂ł����B |
 |
�֒�_
����Ă��т傤
�_�ސ쌧���l�s����R�����P�S�O
Tel 045-226-2636
 |
�@���؊X��ʂ肩��1�{�͂���āA���l���؊w�@�̉��ɂ���̂��֒�_�ł��B���؊X�̒���Ƃ��āA�O������̉p���E�։H���J���Ă��܂��B�����U�N�i1873�j�������ɂ���āA�R�����t�߂ɓ��{�ōŏ��̏����ȕ_���n�����ꂽ�̂��n�܂肾�����ł��B�@ |
| �@����̊֒�_�͊֓���k�ЂőS�A����̊֒�_�����a�����ɑ�Q�����E���̐�Ђɂ��������܂����B���a�U�P�N�i1986�j�̌��U�ɂ������s���̏o�ɂ��Ď����Č��݂͑�S��ł��B�Č�����A���̎p�͒����̕��������h���Ƃ����Ă��邻���ł��B |
 |
 |
�@�u�֒�M�v�Ƃ́A�O���u�Ŋ��������u�։H�v���_�i�����ꐒ�q����Ă�����̂ł��B�։H�̖v��A�d���Ă��������ꑰ�ɂ��A���̌��т����������_�������������Ƃ��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B |
| �@�u�`�v�Ɍ����ア�҂̖����ł���Â����։H���A���̌�́u�W�E���E�v�E���E���E���v�̊e������A���̐����E��`�Ɋ�������� �����������Ƃ���A�썑�̐_���Ƃ��Ē����S�y�Ɋ֒�_�����������悤�ɂȂ��������ł��B |
 |
 |
�@�����ł������։H�́u���_�v�Ƃ��Ă̐��q�̑��ɁA���U��� ���Č��i�Ɂu���`�v���т������Ƃ���u�����v���Ƃ̃V���{���ƂȂ�A�M�p���d�鏤�l�̊ԂŁu���Ɛ_�v�Ƃ��Đ��q�����悤�ɂȂ����̂ł��B |
���l�X�^�W�A��
�悱�͂܂���������
�_�ސ쌧���l�s���扡�l������
Tel 045-661-1251
| �@�u�n�}�X�^�v�̈��̂Œm���鉡�l�x�C�X�^�[�Y�̃z�[���O���E���h�ł��B�����X�N�i1876�j�J���������j�̂�������u���l�����v�ɂ���܂��B |
 |
 |
�@�ǂ�Ԃ���X�����悤�ȊO�ςłU��̋t�O�p�`�̏Ɩ����́u���l�v�̃C�j�V�����́uY�v�������ǂ��Ă��܂��B�u�t�B�[���h�E�^�[�t�v�Ƃ����V�^�l�H�ł������Ă��܂��B |
�݂ȂƂ݂炢�Q�P
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢
 |
�@�݂ȂƂ݂炢�Q�P�n��ɂ͍��w�r���A���ۉ�c��A�W����Ȃǂ���������ł��܂��B���Ă͑��D����S���p�n�Ő�߂��֓��Ɖ��l�w���ӂ̎s�X�n�f���Ă��������ł��B |
| �@���l�����h�}�[�N�^���[�A�N�C�[���Y�X�N�G�A���l�A�p�V�t�B�R���l�A�Ս`�p�[�N�A�݂ȂƂ݂炢�R�Q�ԊفA�O�H�݂ȂƂ݂炢�Z�p�فA�m�s�s���l�V�d�r�A�W���b�N���[���A�悱�͂܃R�X�����[���h�Ȃǖ����łł����V�[�T�C�h�^�E���ł��B�݂ȂƂ݂炢�Q�P�n��͉��l�s����ƒ���ɂ܂�����C�ɐڂ��Ă���n��œs�s�i�ςP�O�O�I����܂��Ă��܂��B |
 |
���{�ۃ������A���p�[�N
�ɂق�܂�߂��肠��ρ[��
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�Q�|�P�|�P
Tel 045-221-0280
| �@�D�ԓ������̍���������{�ۃ������A���p�[�N�ł��B�W�O�N�ȏ�ɂ킽�萔��ǂ̑D�̏C���ɂ�����������Α���̃h�b�N�ɔ��D���{�ۂ�ۑ����J���Ă��܂��B�n���ɂ͉��l�}���^�C���~���[�W�A������������ł��B |
 |
 |
�@���D���{�ۂ͓��{�ۃ������A���p�[�N���ɂ���A��̓��C�g�A�b�v����Ė{���ɂ��ꂢ�ł��B���̔���������u�����m�̔����v�Ƃ���ꂽ�����ł��B |
| �@���{�ۂ͏��a�T�N(1930)�ɕ����Ȃ̍q�C�P�����̗��K���D�Ƃ��Đ_�˂̐�葢�D���Ői�����������ł��B�q�C���������͂P�W�R���L���A�n���S�T�����������ł��B�܂���Ă��������K���͂P�P�T�O�O���ɒB���邻���ł�� |
 |
 |
�@���g�����Q�Q�V�W�g���A�S���X�V���A�������Q�X���̂��̔��D�͌��݂͉��l�s���D��ƂȂ�A�D�Ђ����l�`�ɒu���A�݂ȂƂ݂炢�n��Ɏc���ꂽ���O�H�d�H�ƂP���h�b�N�ɕ����ׂ��Ă���̂ł��B |
| �@ �펞���͔��D����@�D�ɉ�������ċً}�����A���Ɏg��ꂽ�����ł��B���Ԃ��Ȃ��͈����g���A���ɏ]�����Ă��������ł��B���a�Q�V�N�i1952�j�ɔ��D�Ƃ��ĕ�������Ăї��K�D�Ƃ��Ċ��܂����B���a�T�X�N�i1984�j���{�ۇU�����A���オ�������߈��ނ��������ł��B |
 |
���l�}���^�C���~���[�W�A��
�悱�͂܂܂肽���ނ݂�[������
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�Q���ڂP�[�P
Tel 045-221-0280
 |
�@���{�ۃ������A���p�[�N�̒n���ɂ��锎���قł��B���l�`�𒆐S�Ƃ��āA�`�ƑD���e�[�}�ɂ��Ă��܂��B���l�s���P�O�O���N�A���l�`�J�`�P�R�O���N�ɂ����镽�����N�i1989�j�R���Q�T���ɊJ�ق��܂����B |
| �@���l�`�₢�낢��ȑD�Ɋւ����W�����Ă��܂��B�}���^�C���~���[�W�A���͈�ʓI�ɊC�������قƖ�Ă���悤�ł��B�D�𑀂�V�~�����[�V�����Q�[���Ȃǐl�C������悤�ł��B |
 |
�N�C�[���Y�X�N�G�A���l
�N�C�[���Y�X�N�G�A�悱�͂�
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�Q�|�R
Tel 045-682-0109
| �@�N�C�[���Y�^���[�͔g�����`�[�t�Ƃ����R�̃V���{���^���[���A�Ȃ��Ă��܂��B�I�t�B�X���͂��ߖ�U�O���̃V���b�v��X�g�����������X�X�A���l�`�̒��]���y���߂�u�p���p�V�t�B�b�N�z�e�����l�v�A�{�i�I�R���T�[�g�z�[���u���l�݂ȂƂ݂炢�z�[���v�Ȃǂ�����܂��B�N�C�[���Y�X�N�G�A���l�݂͂ȂƂ݂炢21�̒��S�I���݂ɂȂ������{�ő勉�̕����s�s�Ȃ̂ł��B |
 |

 |
�@�p���p�V�t�B�b�N�z�e�����l�͂R�̃^���[�̉��Ɍ����w�z�e���ł��B�����m���͂ޔ������s�s�Ⓡ�X���ЂƂ̊Ɍ���ł����A�p���E�p�V�b�t�B�N�z�e���Y�E�A���h�E���]�[�c�����{�ɏ��߂Č��Ă��O���[�v�z�e���Ȃ̂ł��B���ӂ������ƊC�������낷��D�̃��P�[�V�����ł��B |
�O�H�d�H���l�r��
�݂т����イ�������傤�悱�͂܂т�
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�R�|�R�|�P
Tel 045-200-7351
| �@�����h�}�[�N�^���[�̂����k���ɂ���n��R�R�K���āA�n���Q�K�̍��w�r���ł��B�݂ȂƂ݂炢�Q�P�n��͉��l�h�b�N�̖��Őe���܂�Ă����O�H�d�H�Ɖ��l���D����H��ƍ��S�̉ݕ����̐Ւn���������ɖ��ߗ��Ă��Ƃ���ɂł����̂ł��B���a�T�W�N�i1983�j�ɂ����𗣂ꉡ�l�s���̖{�q�y�ы���֍H����ړ]�����Ă��܂��B |
 |
 |
�@�O�H�d�H���l�r���ɂ͎O�H�݂ȂƂ݂炢�Z�p�ق�����܂��B���A�F���A�C�m�ȂǂU�̃e�[�}�ɉ������Ȋw�Z�p�Ɋւ���W���������܂��B�F���]�[���ł͍ŐV�s�̃��P�b�g�G���W���̎����������܂��B�w���R�v�^�[�̃t���C�g�V�~�����[�V�����u�X�J�C�E�H�[�N�A�h�x���`���[�v�ł͑��c�̌������킦�܂��B |
���l�����h�}�[�N�^���[
�悱�͂܂��ǂ܁[������[
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�Q�|�Q�|�P
Tel 045-222-5015
| �@���l�����h�}�[�N�^���[�͍����Q�X�U���̓��{��̒����w�r���ł��B�P�K����S�W�K�܂ł��I�t�B�X�ɂȂ��Ă��āA�S�X�K����V�O�K�܂ł����l���C�����p�[�N�z�e���j�b�R�[�ɂȂ��Ă��܂��B�U�X�K�͓W�]�t���A�̃X�J�C�K�[�f���ɂȂ��Ă��ĂR�U�O�x�ɂ킽���ĉ��l�s����֓��n���̊e�������n���܂��B |
 |
 |
�@���l�����h�}�[�N�^���[�̖k���ɂ͂T�K���ẴV���b�s���O���[���u�����h�}�[�N�v���U�v������A�����ɂ͕����X�N�i1997�j�ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�u�h�b�O���[�h�K�[�f���v������܂��B |
| �@�u���l���C�����p�[�N�z�e���v�͎O�H�n���̊֘A�z�e���ł��B�����U�N�i1994�j�ɎO�H�n���z�e���O���[�v���烍�C�����p�[�N�z�e���Y�֖��̂�ύX���Ă��܂��B�ŏ�K�V�O�K�ɂ���X�J�C���E���W�u�V���E�X�v�ł�����肷��ق����X�J�C�K�[�f�����p��������������܂���B |
 |
���l�����h�}�[�N�^���[�W�]�t���A
�X�J�C�K�[�f��
���������[�ł�
 |
�@�U�X�K�̓W�]�t���A�u�X�J�C�K�[�f���v�ւ́A�����V�T�O���Ƃ������E�ő��̃G���x�[�^�[�Ŗ�S�O�b�ł����Ƃ����Ԃɓ������܂��B�M�l�X�u�b�N�ɂ��o�^����Ă��邻���ł��B |
| �@���a�T�W�N�i1983�j�R���O�H�n���́A�O�H�d�H��(��)��葢�D���Ւn�R�P�����̓��A�Q�O�����A���ԍő�̒n���҂Ƃ��āu�݂ȂƂ݂炢21�v�ɎQ�悵�A�����h�}�[�N�^���[�J�����v�悵���̂ł����B |
 |
 |
�@�����T�N�i1993�j�V���P�U���ɉ��l�����h�}�[�N�^���[�͊J�Ƃ��������ł��B �f�U�C���̓A�����J�̃R���T���^���g�̃q���[�E�X�^�r���X���̉�Ђ������������ł��B |
�����h�}�[�N�v���U
| �@�u�����h�}�[�N�v���U�v�͉��l�����h�}�[�N�^���[�̖k���ɂ���n���Q�K����n��T�K�̃V���b�s���O���[���ł��B�@ |
 |

 |
�@����Ȑ���������Ԃ��͂�Ŗ�P�V�O���̓X�܂�X�g�������W�܂��Ă��܂��B�P�K�ɂ͂Q�J���̃C�x���g�X�y�[�X������s�A�m�̉��t������Ă����肵�܂��B |

�h�b�O���[�h�K�[�f��
�ǂ�����[�ǂ��[�ł�
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�Q�|�Q�|�P
Tel 045-222-5015�i�����h�}�[�N�v���U�j
| �@�h�b�O���[�h�K�[�f���͖����Q�X�N�i1896�j�Ɋ������������l���D���Q���h�b�N����̂��ĕ����������̂ł��B�p���l�Z�t�p�[�}�[�̒Ɋ�Â��A�����Q�Q�N�i1889�j�ݗ��́u���l�D����Ёv�����݂��A�����ŌÂ̖��c�Α����D���ł��B |
 |
 |
�@������P�O�O���A�[����P�O������A���{�ŌÂ̐Α���h�b�N�ł��B�������i1989�j�N�S���s�w����j�I�������ɂȂ�A�����X�i1997�j�N�P�Q���ɂ͍��̏d�v�������Ɏw�肳��܂����B |
�ՊC�p�[�N
����ρ[��
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�P�|�P
Tel 045-221-2155
| �@�݂ȂƂ݂炢�Q�P�̖k���[�ɂ���A�Ő��L��𒆐S�Ƃ����ՊC�����ł��B���l�`��x�C�u���b�W�A�ߌ���������]�ł���Ƃ���ł��B |
 |
 |
�@��X���R�畽�����ƍL��ȗΒn����������Œ��̖��������Ő��ʂ��ς�钪���̒r�Ȃǂ�����܂��B�����ɂ̓X�e�[�W���݂����Ă��āA���y���t�Ȃǂ̃C�x���g���J����Ă��܂��B |
���l���p��
�悱�͂܂т������
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�R�|�S�|�P
Tel 045-221-0300

 |
�@�������N�i1989�j�R���ɉ��l������̃p�r���I���Ƃ��ĊJ�ق��܂����B������I������P�P���ɐ����ɊJ�ق��܂����B�O�����O�����v���܂����B |

| �@�����ώR�A�s�J�\�A�Z�U���k�≡�l�䂩��̍�Ƃ̍�i�ȂǁA19���I���猻��Ɏ���߁E������p��W�����Ă��܂��B������p�A�ʐ^�𒆐S�ɖ�7800�_�����������W���J�Â��Ă��܂��B |
 |

 |
�@�{�݂͒n��3�K�Ŕ��p���M�������[����p�}�����ȂǁA�W�����ȊO�̃X�y�[�X���[�����Ă��܂��B |
| �@�~���[�W�A���E�V���b�v�A���X�g�����Ȃǂ̎{�݂�������p�قł��B�s���̃A�g���G�A�q���̃A�g���G�ł́A�f�b�T���u���Ȃǂ��J�Â��Ă��܂��B |
 |
�悱�͂܃R�X�����[���h
�悱�͂܂�������[���
�_�ސ쌧���l�s����V�`�Q�|�W�|�P
Tel 045-641-6591
 |
�@�悱�͂܃R�X�����[���h�݂͂ȂƂ݂炢�Q�P�n��ɂ���V���n�Ő��H������łR�̃]�[���ɕ�����Ă��܂��B���E�ŏ��߂Ẳ���I�ȓs�s�v�悩�琶�܂ꂽ�����u���̓s�s�^���̗V���n�Ȃ̂������ł��B |
| �@���E�ő�̎��v�^��ϗ��ԁu�R�X���N���b�N�Q�P�v�␢�E���̐����˓��^�W�F�b�g�R�[�X�^�[�u�o�j�b�V���v�A�}�C�i�X�R�O�x�̋Ɋ����̊��ł���u�A�C�X���[���h�v�Ȃǂ̊y�����A�g���N�V�����������ς��ł��B |
 |
 |
�@�����P�P�N�i1999�j�Ƀ��j���[�A������A��i�̒��߂��f���炵����ϗ��ԁu�R�X���N���b�N�Q�P�v����̃X�|�b�g�̒��S�ɂȂ�܂����B |

�p�V�t�B�R���l
�ς��ӂ����悱�͂�
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢�P���ڂP�[�P
Tel 045-221-2155
| �@�p�V�t�B�R���l�́u�g�ƕ��ƌ��v���e�[�}�ɁA���b�g�̔���L�̌`���ۂ������E�ő勉�̕����R���x���V�����Z���^�[�ł��B��T��Ȃ̐��E�ő勉�̍�����z�[���A��c�Z���^�[�A�W���z�[���A�z�e�����W�����Ă��܂��B |
 |
 |
�@�P�O�O�O���K�͂̉�c���R���s���ĊJ�Âł���[�������ݔ��ƃX�P�[���ł��B���ۉ�c�͂������A�w�p��c�A�V���|�W�E���A�Z�~�i�[�Ȃǂɂ��g���܂��B |
���R�n�}�O�����h�C���^�[�R���`�l���^�c�z�e��
�悱�͂܂����ǂ��[���˂�قĂ�
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢1-1-1
Tel 045-223-2222
| �@���R�n�}�O�����h�C���^�[�R���`�l���^���z�e���ł��B���b�g�̔����C���[�W�����O�ςł��B�E�H�[�^�[�t�����g�Ȃ�ł͂̊J�������ӂ��C���^�[�i�V���i���z�e���ł��B |
 |
 |
�@�ٕ������������鍑�ۓs�s�E���l�̐V�s�S�݂ȂƂ݂炢�w���k����Q���̗��n�ł��B�����R�N�i1991�j�ɃI�[�v�����Ă��܂��B���l�`�A�x�C�u���b�W�A�R�������ȂǃG�L�]�`�b�N�ȊX���݂�]�ޑ�^�V�e�B�z�e���ŕ����R���x���V�����Z���^�[�u�p�V�t�B�R���l�v�Ɉʒu���A�r�W�l�X�̋��_�Ƃ��Ă��œK�ł��B |
�Ղ��肳��
�Ղ��肳���
�_�ސ쌧���l�s����݂ȂƂ݂炢1���ڒn��
Tel 045-223-2121 ���l�`�U������
| �@�p�V�t�B�R���l��ʂ蔲������A�C���^�[�R���`�l���^���z�e���̊C�݂Ɂu�Ղ��肳�v������܂��B���l�w�����A�ԃ����K�q�ɁA�R�������ւ̃V�[�o�X��C��ό��D�̃^�[�~�i����ҍ����ɂȂ��Ă��܂��B |
 |
 |
�@�����R�N�i1991�j�����Ɣg�ɗh��锒���m�ٕ��̌����͊������܂����B�̉����Ɏ��v����̂����n���ȗm�ٕ��̊O�ς͉��炵�����͋C�ł��B |
���l���[���h�|�[�^�[�Y
�悱�͂܂�[��ǂہ[���[��
�_�ސ쌧���l�s����V�`�Q�|�Q�|�P
Tel 045-222-2000
| �@���l���[���h�|�[�^�[�Y�͖�P�R�O�̓X�܂Ɩ�S�O���̃��X�g���������鍑�۔h�������Ǝ{�݂ł��B���l�s���e�`�y�i�A�����i�n��j�Ɏw�肳�ꂽ���Ƃ��畽���P�P�N�i1999�j�ɗA�����i�̂��߂̎{�݂Ƃ��ăI�[�v�����������ł��B |
 |
 |
�@���E�e���̗A���i�������V���b�v�𒆐S�Ƀ��X�g������ԃ����K��͂����f��كt���A�A�u�����h�������t�@�b�V�������[���h�A���E�̐H�ގs��u�t�[�h���[���h�v�u���[���h�t�[�h�R�[�g�v�u����s��v�u�����s�ꉡ�l�v�ȂǑ��ʂł��B |
���l�ԃ����K�q��
�悱�͂܂����������
�_�ސ쌧���l�s����V�`�P�|�P�|�P
Tel 045-227-2002
| �@���l�ԃ����K�q�ɂ͐V�`�u�������l�`�ŏ��̖{�i�I�ȋߑ�`�p�Ƃ��Ė����R�Q�N�i1899�j���H���ꂽ�̂ɔ����A���̕t���{�݂Ƃ��Č��݂���܂����B���{�ő勉�̐ԃ����K�������ł��B |
 |

 |
�@���l�ԃ����K�q�ɂ͖����S�O�N�i1907�j�ɒ��H����吳�Q�N�i1913�j���H����܂������A�֓���k�ЂłR���̂P���Ď������݂͓����̔����̑傫���������ł��B |

| �@�u���ԂȂ��Y���v�̎B�e����Ƃ��Ă��g���Ă��܂����B���l�s��������擾���A���H��͂P���فA�Q���ق��킹�ĂU�Q���~���̑���������������ł��B |
 |

 |
�@�����P�S�N�i2002�j�t�ɉ��l�ԃ����K�q�ɂP���فE�Q���ق������A���Ǝ{�݂Ƃ��ăI�[�v�������̂ł��B�P���ق̓M�������[�A�z�[����W�������u���ꕶ���{�݂Ƃ��Ă̖������ʂ����Ă��܂��B |
| �@�Q���ق͂������Ȑ����G�݂�Ƌ�Ȃǂ��[���������h�V���b�v��A�ꗬ�̉��y���̊��ł��郉�C�u���X�g�����Ȃǂ��W�����Ă��܂��B |
 |
���l�Ŋ֖{�ْ���
�悱�͂܂�������ق傤����
�_�ސ쌧���l�s����C�ݒʂP�|�P
Tel 045-212-6053�@�Ŋ֍L��L����
 |
�@���l�Ŋ֖{�ْ��ɂ݂͂ȂƑ�ʂ�ƊC�ݒʂ肪��������p�Ɍ����Ă��܂��B���a�X�N�i1934�j�Ɍ��݂��ꂽ�S�T�K���Ẵr���ł��B�u�N�C�[���v�̈��̂ŌĂ�Ă��܂��B |
| �@�C�X�������@�̕����z�ŁA�㕔�̗ΐF�̃h�[���������I�ȋC�i���铃�ł��B�֓���k�Ќ�A���̑呠��b�����������u���Ǝҋ~�ς̂��ߓy�؎��Ƃ��N�����ׂ��v�Ƃ��Ď��Ǝҋ~�ς����˂����z���ƂƂ��Č��Ă�ꂽ�����ł��B |
 |
 |
�@�u�N�C�[���v�̍����͂T�P������܂��B�_�ސ쌧���{���ɂ́u�L���O�v�͂S�X���A���l�s�J�`�L�O��ق́u�W���b�N�v�͂R�U���ł��B���̌��������̂��̂ɕ������Ȃ��Ƃ��ĂS�V���̐v�}�����������A�T�P���ɂ����Ƃ����b���c���Ă��܂��B |
| �@�J�`����̉��l�`�̗��j��f�Ղ̕ϑJ�A�A�o���ʊւ̗���A�U�u�����h���i�A����E���e�Ȃǂ̖��A�̎���Ȃǂ������̓W����f���ŏЉ�Ă��܂��B |
 |
���{�X�D���j������
�ɂق�䂤����ꂫ���͂��Ԃ���
�_�ސ쌧���l�s����C�ݒʂR�|�X
Tel 045-211-1923
 |
�@�C�ݒʂ�ɖʂ��ĂP�U�{�̃R�����g���~����������Ă���r���͏��a�P�P�N�i1936�j�Ɍ��Ă�ꂽ���l�X�D�r���ł��B�����́A���{�X�D���j�����قƂȂ��Ă��܂��B |
| �@���{�X�D�͖����P�W�N�i1885�j�n���̗��j�̂�����{���\����C�^��Ђł��B���{�X�D���j�����قł͓��{�X�D�̗��j��ʂ��A���{�̋ߑ�C�^�j��C�ƑD�̗��j���w�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B |
 |
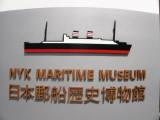 |
�@�D��ȋq�D����̃��f���V�b�v��f�B�i�[ ���Č����Ă��܂��B�܂������Ȃǂ��W������Ă��܂��B |
���l��s����
�悱�͂܂������傤����
�_�ސ쌧���l�s����{���R�[�Q�W
Tel 045-201-9853
| �@���a�P�P�N�i1936�j�V���Ɍ��Ă�ꂽ���l��s����̌����ł��B�c���̑�����ׂĂ��̊Ԃ�ˏo�����邱�ƂŁA���ʂɗ��̕\����������Ă��܂��B���ʎԊ��P�{���ł���̂������ł��B�͉̂��l��s�W������������ł��B |
 |
 |
�@�f�p�ȊO�ςɃA�N�Z���g������e�R���b�^�����Ă��܂��B����͑����͗l�̏Ă����^�C���ŃA�[���E�f�R�̓����ł��B��a��������S�K�����͏��a�S�O�N�i1965�j�ɑ��z���ꂽ�����ł��B |
���x�m��s���l�x�X
���イ�ӂ������悱�͂܂��Ă�
�_�ސ쌧���l�s����{���S-�S�S
Tel 045-671-2023 �s�s������
| �@���a�S�N�i1929�j�P�O���Ɍ��Ă�ꂽ���x�m��s���l�x�X�̌����ł��B���̑O�g�͋����c��s���l�x�X�����������ł��B���a�Q�R�N�Ɉ��c��s����x�m��s�ւƉ��̂���܂����B �O�ǂ̓��X�e�B�J�ς݂ŁA���ʃt�@�T�[�h�Ƀg�X�J�i����I�[�_�[�̉~���A���̊Ԃɂ͔��~�`�̑��������܂��B |
 |
 |
�@�S�R���N���[�g����̂Q�K���Ăł��B �v�͈��c��s�c�U�ہA�{�H�͑�q�y�A���� �听���݂��s�Ȃ��������ł��B��s�̈ړ]�ɂ��ꎞ���g�p����Ă��܂���ł������A�����P�S�N�i2002�j�R���ɉ��l�s���������擾���������ł��B |
�����l��s�{�X
���イ�悱�͂܂����ق�Ă�
�_�ސ쌧���l�s����{���T�[�S�V
Tel 045-221-0325�@���R�n�}�n���s�s�Z���^�[
| �@�����l��s�{�X�͕����Q�P�N�i2009�j�T����胈�R�n�}�E�N���G�C�e�B�u�V�e�B�[�E�Z���^�[�ƂȂ�܂����B���͂Ȃ��{�X�́A���a�S�N�i1929�j�ɑ���s���l�x�X�Ƃ��Č��z����܂����B���̌�A���{���M�p��s���o�ĉ��l��s�{�X�ƂȂ��������ł��B |
 |
 |
�@�����̑唼�͒n��ĊJ���̍ۂɎ���Ă��܂��������ł����A�o���R�j�[���������́A��s���z�̏ے��I�ȃf�U�C���Ƃ��Ẳ��l������Ƃ��Ďs�����S�ɂȂ�ۑ������܂��������ł��B |
�_�ސ쌧�����j������
���Ȃ��킯���ꂫ���͂��Ԃ���
�_�ސ쌧���l�s����쒇�ʂT�|�U�O
Tel 045-201-0926
| �@�_�ސ쌧�����j�����ق͖����R�V�N�i1904�j�����l������s�{�X�{�قƂ��Č��Ă�ꂽ�h�C�c�E���l�b�T���X�l���̌ÓT���z�ł��B���̃h�[���������ŁA���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
 |
�@�v�͖������z�E�̎O�����̂ЂƂ�ł���Ȗؗ����i�܂����Ȃ��j�ł��B���l�ŗB��̖{�i�I�ȐΑ���̃h�C�c�E���l�b�T���X�l���ł��B���ʂ���ї��������ɑ傫�ȃy�f�B�����g��݂��A�ǖʂ͑����Ƃɑ�I�[�_�[�̒��`���o���ăo���b�N�I���ʂ��������Ă��܂��B |
| �@�_�ސ쌧�����j�����قł͒������q�A�퍑��k���A�J���ƕ����J���ȂǁA���{�̗��j�̎�v����ƂȂ������l�̗��j���A�Ñォ�猻��܂łT�ɕ����Ă킩��₷���W�����Ă��܂��B�@ |
 |
�@�����@����
����������傤���傤��
 |
�@���j�����ق̌��������ɓ��{�ʐ^�̊J�c�Ƃ����鉺���@���肪����܂��B�����@��͒���̏��F�n�ƂƂ��ɓ��{�̏��Ǝʐ^�t�̑������Ƃ��Ēm���Ă���A���̔�͔ނ̎ʐ^�ق��ٓV���ɂ��������Ƃ���ނ̌��т��L�O���Ă����ɐݒu����Ă�����̂ł��B |
�O��Z�F��s���l�x�X
�݂����݂Ƃ������悱�͂܂��Ă�
�_�ސ쌧���l�s����{���Q�|�Q�O
Tel 045-211-0031
| �@ �@���a�U�N�i1931�j�Ɍ��Ă�ꂽ�O��Z�F��s���l�x�X�̃r���ł��B�Q�K���ĂŐv�͓����̃A�����J�̖��厖�����A�g���E�u���b�W�������B���O�X�g�����z�������ł��B |
 |
 |
�@���̌��z�������͎O��{�ق̐v���S�����������ł��B���̌����͂���ΎO��{�ق̏k���łƂ�������̂ł��B���ʂ�4�{�̃C�I�j�A���~�����ő�̓��������A�����ɂ��R�����g�����������������A�N���V�b�N�ȕ��͋C��Y�킹�Ă��܂��B |
���l�s�J�`�L�O���
�悱�͂܂������������˂�����
�_�ސ쌧���l�s����{���P�|�U
Tel 045-201-0708
| �@���l�s�J�`�L�O��ق͉��l�J�`50���N���L�O���đ吳�U�N�i1917�j�Ɍ��Ă�ꂽ�����ł��B�������N�i1989�j�ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
 |
�@�ԃ����K�Ɣ����ԛ���̏d���ȊO�ǂ̓l�I�E���l�T���X�l���ł��B������ɗ��R�U���̎��v���́u�W���b�N�v�ƌĂ�A���l�̃V���{���Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B�֓���k�Ђœ������Ď����܂������A�����H�����d�ˁA���݂̎p�ɂȂ��Ă��܂��B |
| �@������ɂ͔��p�h�[���A���k���ɂ͊p�h�[���������Ă��܂��B���z�����͋M�o����r�����[�h��������A�P�Ɍ���Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A ���l�����E�̃T�����Ƃ��Ă��p�����A
�܂����t��Â����ȂǕ����{�݂Ƃ��Ă̖������S���Ă��������ł��B |
 |
 |
�@�����U�N�i1859�j�̊J�`�����̗��j�I�Ȏ������͂��߁A���D��y���[�̉����L�ȂǁA�����J���̍��̉��l�Ɋւ���M�d�Ȏ����������W�����Ă��܂��B���ق̌����́A���a�U�N�i1931�j�Ɍ�������A�p�����̎��قƂ��ď��a�S�V�N�i1972�j�܂Ŏg���Ă��������ł��B |
| �@�ٓ��ɂ́A �F���C�Y���̐���ɂ��Ƃ�����J�`������`�����X�e���h�O���X��A �a�c�p��攌�̐F�ʒ��Ր}�Ȃǂ��ی�ۑ�����Ă��܂��B���v���u�W���b�N�v�́A
�_�ސ쌧���{����(�L���O)�A ���l�Ŋ֖{�֒���(�N�C�[��)�Ƌ��ɁA ���l�̂R���Ƃ��Ďs���ɐe���܂�Ă��܂��B |
 |
�_�ސ쌧���{����
���Ȃ��킯�傤�ق傤����
�_�ސ쌧���l�s������{��ʂP
Tel 045-210-1111
 |
�@�_�ސ쌧���̂R��ڂ̒��ɂ͐ԍ�}�o�ق̐v�҂̕ЎR���F�̎�ɂ����̂ł������֓���k�Ђɂ��Ђő傫�Ȕ�Q���A���Ē������邱�ƂɂȂ�܂����B���J�v���Z�̌��ʏ����ØY�̈Ă��̗p����܂����B |
| �@�O�ǂ̃X�N���b�`�^�C���\��ƍ����S�W�D�U���́u�L���O�v�̈��̂����钆���̍����������ł��B���l�Ŋ֖{�֒��Ɂu�N�C�[���v�A ���l�s�J�`�L�O��فu�W���b�N�v�Ƌ��ɁA
���l�̂R���Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B |
 |
 |
�@�S���S�R���N���[�g�� �n��T�K�E�n���P�K�̖{���ɂ͑�ёg���{�H���ď��a�R�N�i1928�j�P�O���Ɍ��Ă�ꂽ�����ł��B�銥�l���Ƃ�����V��t�̗l�ȓ����𒆉��ɍڂ��Ă��ď��a�����ɗ��s������삯�ɂȂ��������ł��B |
���l�s�s���W�L�O��
���l���[���V�A������
�_�ސ쌧���l�s������{��ʂP�Q
Tel 045-663-2424
 |
�@���a�S�N�i1929�j�Ɍ��݂��ꂽ�����l�s�O�d�b�ǂ����C���ĉ��l�s�s���W�L�O�قƉ��l���[���V�A�����ق������P�T�N�i2003�j�R���P�T���ɊJ�ق��܂����B |
| �@�������T���������ȃf�U�C���ł���Ȃ�����ו��ɂ͂���܂ł̌ÓT��`�l�����c���A�����̒��M�ȓƎ��̗l���������܂��B���l�Ƃ����s�s�̌`���E���W�̗��j�ɂ��āA���܂��܂Ȏ������Љ�Ă��܂��B��������̃����K���������}���z�[���̖͌^�Ƃ������������W����������܂��B |
 |
���l�C����
�悱�͂܂������傤����
�_�ސ쌧���l�s������{��ʂW
Tel 045-201-3740
 |
�@���a�W�N(1875)�ɍČ����ꂽ���l�C����ł��B�����T�N�i1872�j�ɃA�����J�̐鋳�t�T�~���G���ER�E�u���E���Ƃi�D�g�D�o���ɂ���Đݗ�����܂����B����̌����͊֓���k�Ђŕ��Ă��܂��B���{�ōŏ��̃v���e�X�^���g����ł��B�Ȃ���������ŌÂ̋���͌������N�i1864�j�����̒����Y�V�哰�ł��B |
| �@�����ǂŃG���K���g�Ȑ듃������A����炵���S�V�b�N���ł��B �����W�N�i1875�j�����̏��͍����J�`�L��ɖ苿���Ă��܂��B�����P�Q�N�i1879�j���{�l�ɂ�鏉�߂ẴN���X�}�X�~�T�����̔���������ōs�Ȃ�ꂽ�����ł��B |
 |
���l�J�`������
�悱�͂܂�����������傤����
�_�ސ쌧���l�s������{��ʂR
Tel 045-201-2100
 |
�@�J�`�L��Ɍ����l�J�`�����ق͏��a�T�U�N�i1981�j�U���Q���̊J�`�L�O���ɁA���Ęa�e����ꂽ�R�����邱�̒n�ɊJ�݂��ꂽ�����ł��B |
| �@�P�K�ɂ́A�u�J�`�ւ̓��v�Ƒ肵�āA�y���[���q�Ƃ��̑O��̏�≡�l�̗l�q�Ȃǂ��W������Ă��܂��B�����������Â������{�́A���D���Ђ�����y���[�̗��q�ɂ���āA
�傫���ϖe���܂����B���{�̊J���Ɖ��l�J�`�̈Ӗ��A���l�̖����Ȃǂ����炩�ɂ��Ă��܂��B |
 |
 |
�@�Q�K�ł͓��ʖ������疾���E�吳���܂ł̉��l�̗��j�Ɋւ��l���� �����Ȃǂɏœ_�����āA�N�S��̓��ʁE���W�����J�Â���Ă��܂��B |
���Ęa�e���̒n
�ɂ��ׂ��킵�傤�₭���傤����̂�
�J�`�L��
���������Ђ��
�_�ސ쌧���l�s������{��ʂR
| �@�������N�i1854�j���Ęa�e������Œ���܂����B���͊J�`�L��ɂȂ��Ă��܂��B�����ɕ�����~���[�̃I�u�W�F�̂ق��A���������ɐݒu���ꂽ�ߑ㉺�����̈�\���ۑ�����A�n���������ǂ������Ęa�e�������̒n�̐Δ肪�����Ă��܂��B |
 |
 |
�@�Éi�U�N�i1853�j�v���l�ŃA�����J�̃t�B�����A�哝�̂̐e����`�����y���[�͗��N�ė������A�����œ��Ęa�e����������܂����B |
| �@���͉��c�A���فi���فj�̊J�`�A�A�����J�D�ɐΒY�E�d���E���R�i���������邱�ƂȂǂP�Q������Ȃ��Ă��܂����B |
 |
 |
�@���̏������ɂ���ē��{�̍����̐��͕���A���ˑ̐��͗h�炢�ł������ƂɂȂ�܂��B���{��V�̈�ɑ|���璼�J�͏�Δh��e�����Ĉ����̑卖�����{���A���˘Q�m�ɂ���č��c��O�ŎE�Q����Ă��܂��܂����B |
��юR����
�̂���܂�������
�_�ސ쌧���l�s����V�����U�R�|�P�O
Tel 045-231-1307�@��юR������
 |
�@��юR������т͖����P�O�N��Ɍ��P�O�Y��Ζؑy���q�炪��@������܂��Ă��������ł��B�֓���k�Ђʼn�Ō�A���l�s�Ɋ���吳�P�S�N�i1925�j�a�E�m�E�ܒ��̂R�l��������юR�����Ƃ��ĊJ�����������ł��B |
| �@ �����m�푈���͗��R���g�p���A���͏��a�Q�Q�N�i1947�j�܂ŃA�����J�R�ɐڎ�����Ă��������ł��B |
 |
 |
�@�݂ȂƂ݂炢�Q�P�n��≡�l�`����]�ł���W�]���v�[���Ȃǂ̎{�݂��_�݂��Ă��܂��B�܂������͂��ߎl�G�܁X�̉Ԃ��炭�����Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B |
| �@��юR�������ɂ͍��v�ԏێR�肪����܂��B�J���P�O�O�N���L�O���āA���a�Q�X�N�i1954�j�Ɍ��Ă�ꂽ�����肾�����ł��B�ێR�͐M�B����˂ɐ��܂�V�ۂS�N�i1833�j�]�˂ɏo�č�����ւ̏m�ɓ���A��q�w�̍ċ����咣���ēV�ۂP�O�N�i1839�j�_�c�ɏm���J���܂����B���̘V���������O�Ɂu�}���\���v����\���ĉ��l�J�����咣���܂����B |
 |
��юR������
�̂���܂ǂ��Ԃ���
�_�ސ쌧���l�s����V�����U�R�|�P�O
Tel 045-231-1696
 |
�@��юR�������ɂ���A���a�Q�U�N�i1951�j�ɃI�[�v���������l�ŏ��̓������ł��B�R�D�R�w�N�^�[���̉����ɂ̓L������͒��ށA���b�T�[�p���_�Ȃǖ�110��̓��������炳��Ă��܂��B |
| �@���C�I����L�����Ȃǂ̑�^�������͂��߁A�t���{���g�y���M���Ȃǂ̂��킢�炵�����������܂��B�������������͖����ł��B�������l�s�c�̃Y�[���V�A���ł������߁A���܂荬��ł��Ȃ��݂����ł��B |
 |
���l�s�����}����
�悱�͂܂����イ�����Ƃ��傩��
�_�ސ쌧���l�s����V����1
 |
�@300�����ȏ゠�鑠���̒�����R���s���[�^�[�œǂ݂����{��T���Ď�邱�Ƃ��ł��鉡�l�s�����}���قł��B���C�U���V�X�e����p�̔����Ԉ֎q��p�ӂ��Ă���}���قł��B |
�ɐ��R�c��_�{
������܂�����������
�_�ސ쌧���l�s����{�蒬�U�S
Tel 045-241-1122
 |
�@�ɐ��R�c��_�{�͖��������A���l�����̖f�Ղ̗v�Ƃ��ĊJ�`�����ƁA���ƒ�����F�邽�߂ɊJ����܂����B |
| �@�����R�N�i1870�j�ɑn������܂����B�����͍]�ˎ���ɂ����ė��s�ɂȂ����u���ɐ��Q��v�̖��c�肩��A�y�q���̖ړI�ňɐ��_�{�̌�Ր_�ł���V�ƍc��_�̌䕪������������̂��n�܂�Ƃ���܂��B |
 |
 |
�@�Βi���オ���āA�咹����������ƁA���ʂɒ�������_���w����̖{�a������܂��B�{�a���ɂ͋n�z�{������ł��܂��B���݂͉��l�̑�����Ƃ��āA�܂��u�֓��̂��ɐ�����v�̖��̂Őe���܂�Ă��܂��B |
| �@���Ƃ��Ƃ͌˕����̊C�݈ɐ��̐X�Ə̂���R��ɒ������Ă��܂������A�����R�N�i1870�j��юR�̌��Вn�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ������Ƃł��B���݂ł͔N�ԂP�T�O���l���̐l�X���Q�q�ɖK��邻���ł��B |
 |
 |
�@�Гa�͉��x�����z����Ă��܂������A�֓���k�ЂŏĎ��A��P�Ő�ɂ����A���݂͂R��ڂ������ł��B���l�̑S�n������������������ȏ��ō��̖����Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B |
�_�ސ쌧���}���فE���y��
���Ȃ��킯���Ƃ��傩��E�����ǂ�
�_�ސ쌧���l�s����g�t���u�X�|�Q
| �@�_�ސ쌧�����y���͍g�t���o�����Ƃ���ɂ���܂��B���{�ł��L���̉��y�z�[���œ��{���̉��y��p�z�[���ł��B�����v�̓����h����Loyal�Festival�Hall���Q�l�ɂ��������ł��B |
 |
���l�\�y��
�悱�͂܂̂������ǂ�
�_�ސ쌧���l�s����g�t�P�u�Q�V�|�Q
Tel 045-263-3055
 |
�@���l�\�y���͑|���R�����ׂ̗ɂ���܂��B�����ɔ[�߂��Ă���\����͖����W�N�i1875�j�ɋ�����ˎ�@�Ɍ��Ă��A��ɋ������ˎ�@�Ɉڒz���ꂽ�u����\����v���������̂������ł��B�֓��Ɍ�������ŌÂ̔\����ł��B |

| �@�S�W�P�̊ϋq�Ȃ�����A�\�⋶���Ȃǂ̌������s�Ȃ��Ă��܂��B����(���傤����)�A�y��Ƃ������\�⋶���Ɋւ���i�X��W�����Ă��閳���X�y�[�X�Ȃǂ����݂���Ă��܂��B |
 |

�|���R����
�������܂�������
�_�ސ쌧���l�s����g�t�P�u�T�V
 |
�@�|���R�����͐_�ސ��s���̐Ւn���������������ł��B���ďC�D�ʏ����̒����������V�A��ɑ|�������J�i����������̂��݂Ȃ������j�䂩��̌����ł��B |
| �@�F���ˎm�L�u�����̒n�����L�O������Ă��̂������P�S�N�i1881�j�ŁA�����S�Q�N�i1909�j�Ɉ�ɑ�V�̓������������ꂽ�����ł��B |
 |
 |
�@��ɒ��J�͕F����Ő��܂�܂��������q�ł���A�{�q�̌��������P�V����R�Q�܂ł̂P�T�N�Ԃ��R�O�O�U�̎̕}���̕����Z�݂Ƃ�����炵�����������ł��B�O���R�N�i1846�j�Z�̈�ɒ����̗{�q�Ƃ����`�ŕF���˂̌�p�҂Ɍ��肵�A�Éi�R�N�i1850�j�ɌZ�̈�ɒ����̌���p���ŕF���ˎ�ƂȂ����l�ł��B |
| �@�F���ˎ���͔ː����v���s�����N�ƌĂ�A�A�����J���O���̃y���[�͑����q�ɔ����]�˘p�h���Ɋ��܂����B�F���V�c�̒��������ŃA�����J�Ɠ��ďC�D�ʏ�����ƒf�Œ���A���Δh�������̑卖�ɂ�葽���l���������߁A�����V�N�i1860�j�R���R�����˔˘Q�m�ɂ����c��t�߂ňÎE����Ă��܂��܂����B |
 |
���l
 |
�@���؋q�D���┑���Ă���傳�A�C�ɗאڂ���R�������A���l�`����]����}�����^���[�A�V�܃z�e����m�����z�̓@��E�E�E |
| �@��i�̖����̉��l�x�C�u���b�W�A�X��ۂ̗E�p�A�����ɂ̓��E���h�^���[��R�n�}�E�O�����h�E�C���^�[�R���e�B�l���^���ɑ�\�����MM�Q�P�̍��w�r���Q�E�E�E�@�V�Ƌ������a���Ă��钬�u���l�v�ł��B |
 |
�V���N������
���邭�͂��Ԃ���
�_�ސ쌧���l�s����R����1
Tel
045-641-0841
| �@���a�R�S�N�i1959�j�A�J�`�����p�����ЃW���[�f�B���E�}�Z�\������i�p��Ԋفj�̂������Ƃ���ɃV���N�Z���^�[�r�����ł��A���̊K��ɂ���܂��B |
 |
 |
�@�u���̂���݁v�]�[���ł́A�Ñォ�猻��܂ł̓��{�̂��ꂼ��̎���̓�������ߑ������W������A���E�̖����ߑ��̑����������g���č���Ă��邱�Ƃ������Ă���܂��B |
���l�}�����^���[
�悱�͂܂܂��[
�_�ސ쌧���l�s����R�����P�T
Tel 045-664-1100
 |
�@�R�������̌������ɗ������P�O�U���̃^���[�ł��B���E�ꍂ������Ƃ��ăM�l�X�u�b�N�ɂ��F�肳��܂����B���݁A����̋@�\�͕����Q�O�N�i2008�j�X���P���ɔp�~����Ă��܂��B |
| �@�}�����^���[�͏��a�R�U�N(1961)�P���P�T���A�J�`�P�O�O���N���L�O���č��ꂽ�P�O�p�`�̓���ł��B�S�K�Ƀo�[�h�s�A�A�R�K�ɋ@�B�d�|���̂�������قȂǂ�����܂��B |
 |
 |
�@�s�[�N���ɂ͂P�O�O���l������������҂ł������A�����P�V�N�i2005�j�ɂ͔N�ԂQ�V���l�ɂ܂Ō������A�^�c��Ђ́u�X��ۃ}�����^���[������Ёv���l�s�ɏ��n���܂����B�@ |
| �@�@���l�s�͊J�`�P�T�O���N�ɂ����镽���Q�P�N�i2009�j�A�O�ς̃��j���[�A���≮���̉������s���A�T���Q�R���Ƀ��j���[�A���I�[�v�����܂����B |
 |
�R������
��܂�����������
�_�ސ쌧���l�s����R�����Q�V�X
Tel 045-681-1860
 |
�@���a�T�N(1930)�R���ɊJ�������R�������́A���l�̌����̒��ň�Ԓm���Ă�������ł��B�C�w���s����J�b�v���A�Ƒ��A���O���[�v�A�x���͂�������ł����Ă������̐l�o�œ�����Ă��܂��B |
| �@�X��ۂ̑O�̂�����ƁA�u���E�̍L��v�̓���������ɂ͉Ԓd�������āA�G�ߖ��̉ԁX���������炢�Ă��܂��B |
 |
 |
�@�R�������͊֓���k�Ђ̕������Ƃ̂ЂƂƂ��Ċ��I�ߗ��Ăđ������ꂽ�����Ȃ̂ł��B |
| �@��Q�����E����̓A�����J�R�ɂ���Đڎ�����܂������A���a�Q�X�N�i1954�j���班�����Ԋ҂���A�����A���ǂ��o�āA���a�R�U�N(1961�j�ɂ͍Đ������������Ăقڌ��݂̎p�ƂȂ�܂����B |
 |
 |
�@���a�U�R�N�i1988�j�ɍs��ꂽ���l������̍ۂɓ����̒n�����ԏ�Ƃ��̏㕔�́u���E�̍L��v�Ȃǂ���������܂����B |
| �@�R�����������Ɏc���Ă������Ս`�S�����ːՂ𗘗p���āA�����P�S�N�i2002�j�t�Ɂu�R���Ս`���v�����i�[�h�v����������܂����B����ɂ���ĎR�������ƐV�`�n��Ƃ��V�����Ō���U���₷���Ȃ�܂����B |
 |
�X���
�Ђ���܂�
���l�s����R�����R�������n��
 |
�@�X��ۂ͏��a�T�N�i1930�j�O�H���l���D���ő����܂����B���g�����P���Q��g���A�S���P�U�R�D�R���̍��؋q�D�ł��B�A�[���E�f�R�l���̃C���e���A���������ꂽ���̑D�́u�k�����m�̏����v�ƌĂꂽ�����ł��B�D���́A�X��_�Ђ���Ƃ��������ł��B |
| �@��O�A����ʂ��k�����m���Q�R�W�f���A���ׂQ���T��l�]�̏�q���^�X��ۂ́A���a�R�T�N�i1960�j�P�O���A���������ނ��܂����B�^�q�I����͉��l�s�R�������O�̉��l�`�ɌW������Ă��܂��B |
 |
 |
�@�X��ۂ��^�c���Ă����X��ۃ}�����^���[�͕����P�W�N�i2006�j�^�c���I�����A�D�̂���{�X�D�ɏ��n���܂����B���{�X�D�͑D�̂̏C�U�E�����̏C�����s�������Q�O�N�i2008�j���甎���ّD�Ƃ��Č��J���ĊJ���܂����B |
�K�[���X�J�E�g�̑�
| �@�R�������ɂ́A�A�����J�̃K�[���X�J�E�g�T�O���N�ƁA���{�̐��E�A�������������L�O���Č��Ă�ꂽ�u�K�[���X�J�E�g�̑��v������܂��B |
 |
�����߂̐�������
 |
�@�����߂̐�������@�Ȃ��������
�@�����X�q�@�����V���c�@������
�@�g�Ƀ`���b�v�@�`���b�v�@������ł�
�@���b��Ƃ̕����r�q�����������A�͑����z������ɋȂ�t���܂����B���a�P�Q�N�i1937�j���z�̖��œ��w�̎�̉͑����q���̂��܂����B |
���̎��_
| �@���a�R�T�N�i1960�j�o���s�s�ł���A�����J�̃T���f�B�G�S���瑡��ꂽ���j�������g�u���̎��_�̑��v�ł��B |
 |
�Ԃ��C�̏��̎q�̑�
 |
�@����J��̎��ɂȂ银�w"�Ԃ��C"���͂��Ă������̎q�̑��ł��B
�@�Ԃ��C �͂��Ă��@���̎q
�@�ِl����� ����ā@�����������
�@���l�� �u������@�D�ɏ����
�@�ِl����� ����ā@����������� |
�_�ސ쌧�������z�[��
���Ȃ��킯������݂�ف[��
���l�s����R����3-1
| �@�_�ސ쌧�������z�[���͍`���R�n�}�̒��S�Ɉʒu���R�������E���؊X�E�����ȂǂɈ͂܂ꂽ�D���n�ɂ���܂��B |
 |
 |
�@��Q�T�O�O�����e�̑�z�[�����͂��߁A���z�[���E�召��c��������S���K�͂̊w�p��c��e����ɕ��L�����p����Ă��܂��B |
�w�{�����m�@��
�ւڂ�͂����Ă�����
�_�ސ쌧���l�s����R�����Q�S�T
 |
�@�w�{�����m�@�Ղ̋L�O��́A���l�l�`�̉Ƃ̂����ׁA�n���������ɂ̑O�ɂ���܂��B�w�{�����m�����{���������Ȃ��������̂��A���{�ōŏ��̘a�p�����A�����ĒԂ邽�߂ɍ��ꂽ�̂��w�{�������[�}���������ł��B |
| �@�w�{�����m�͊J�`�ƂƂ��ɗ��������鋳�t�̂P�l�ł��B�_�ސ쐬�����ɂR�N�Z��A���v�Q�N�i1862�j�~�A���l�����n�R�X�ԂɈړ]���A�����̖|��A�a�p���T�̕Ҏ[�A��p�̕��y�Ȃǂɗ͂�s�����܂����B���a�Q�S�N�i1949�j�P�O���ɋL�O�肪�@�ՂɌ��Ă��܂����B |
 |
���l�l�`�̉�
�悱�͂܂ɂ傤�̂���
���l�s����R�����P�W
 |
�@���l�l�`�̉Ƃ́u���l���E���E�̐l�`�ӂꂠ���N���[�Y�v���R���Z�v�g�B�ْ��ɐ�_�A�v���f���[�T�[�ɖk���Ƌv�����}���A���E�P�S�P������R�T�O�O�_�ȏ�̐l�`��W�����Ă��܂��B |
�`�̌�����u����
�݂ȂƂ݂̂��邨����������
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�P�P�S
Tel 045-711-7802
 |
�@�`�̌�����u�����͉��l���\��������̈�ł��B���l�`�Ɖ��l�x�C�E�u���b�W����]�ł��A��i�X�|�b�g�Ƃ��Ă��l�C������܂��B�����ɂ͑�Ŏ��Y�L�O�فA�_�ސ�ߑ㕶�w�فA�R��P�P�P�Ԋق⌳�p�����̎������@�������C�M���X�قȂǂ�����܂��B |
| �@�t�����X�R��[�Y�K�[�f���̎U����ł��܂��B���̌����͏I�풼��̏��a�Q�R�N�i1948�j�Ƀq�b�g�������s�́u�`��������u�v�ɂ��Ȃ�Ŗ�������A���a�R�V�N�i1962�j�ɃI�[�v�����܂����B |
 |
 |
�@�`�̌�����u�����͂��ĉ��l�J�`���ɃC�M���X�ƃt�����X�̌R�������Ԃ����ꏊ�Ƃ��Ă悭�m���Ă��܂��B�t�����X�̎��ق��u����Ă����Ւn���u�t�����X�R�v���Ƃ��Č����ɉ����������ł��B |
| �@�����Q�X�N�i1896�j�t�����X�̎��قƂ��̊��@�����݂��ꂽ���A���̃t�����X�R�ɂ͈�ː������ݏグ�邽�߂̕��Ԃ��ݒu���ꂽ�����ł��B |
 |
 |
�@�����K����̈�˂̓t�����X�̎��ُv�H���ɏ㐅�����Ȃ��������ߕ~�݂��ꂽ���̂ł��B�[���͂R�O�����邻���ł��B |
| �@�������u�̏�͓W�]�䂪����L��ɂȂ��Ă��܂��B�����P�S�N�i2002�j���畽���P�U�N�i2004�j�ɂ����Ēi�K�I�ɐ������s���吨�̐l���K��Ă��܂��B |
 |
| �W�]�L�� |
 |
�@�W�]��Ƃ��̓쑤�̈�p�͂��̌����̒��S�ƂȂ镔���ł��B�Ԓd�Ȃǂ���������Ă��Ē[���Ȕ������������Ă��܂��B |
| �W�]�� |
| �@��]�̂��Ƃɉ��l�x�C�u���b�W�≡�l�`�������낷���Ƃ��ł��܂��B�}�����^���[��݂ȂƂ݂炢�Q�P�n��̃^���[���悭�����܂��B |
 |
| �W�]�� |
��Ŏ��Y�L�O��
�����炬���낤���˂�
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�P�P�R�@�`�̌�����u������
Tel 045-622-5002
 |
�@���l�o�g�ʼn��l������Ȃ������������ƁA��Ŏ��Y���L�O���ď��a�T�R�N�i1978�j�Ɍ��Ă��܂����B |
| �@�����̓t�����X�̖��ƕ��̐ԃ����K������n���ȂQ�K���Ăł��B�ނ̔ӔN�̏��ւ��ٓ��ɕ������Ă��܂��B |
 |
 |
�@�u�Ɣn�V��v�u����v�u�p���R��v�u�V�c�̐��I�v�Ȃǂ̎��M���e�∤�p�i�A�t�����X�j�����A�������h��Ȃǂ��W������Ă��܂��B |
| �@��Ŏ��Y�L�O�ق���_�ސ�ߑ㕶�w�قɂȂ��閶�J���ł��B���������̉��l��ɂ�����Ŏ��Y�̏����u���J�v�ɂ��₩���Ă��܂��B |
 |
| ���J�� |
�_�ސ�ߑ㕶�w��
���Ȃ��킫���Ԃ�����
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�P�P�O�@�`�̌�����u������
Tel 045-622-6666
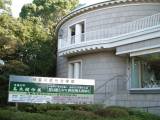 |
�@��Ŏ��Y�L�O�ق̗���ɂ���܂��B�����̒n���R�K�A�n��Q�K���Ă̌����ł��B�_�ސ쌧�ɂ䂩��̐[�������A��[�N����J�菁��Y��̈�i�����W�A�ۊǂ��Ă��܂��B |

| �@�u�꒼�Ƃ�k�����H�A�Ėڟ��A���ҏ��H���āA�O���R�I�v�̏��A�H�열�V��u�w偂̎��v�̌��e�A�����ւ̕`�����G��A���ؓc�ƕ��̗����Ȃǂ�����܂��B |
 |
�R��P�P�P�Ԋ�
��܂ĂP�P�P��
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�P�P�P�@�`�̌�����u������
Tel 045-623-2957
 |
�@�R��P�P�P�Ԋق͑吳�P�T�N�i1926�j�ɕč��l���t�B�����@�Ƃ��Č��Ă�ꂽ�X�y�C�����̗m�قł��B�v�҂͓����̊ۃr�����݂̂��߂ɑ吳�X�N�i1920�j�ɗ��������A�����J�l���z�Ƃ�J�EH�E���[�K���ł����B���l�R�萹�����x�[���b�N�z�[���A�����n��ϗ��ȂȂǂ��v���Ă��܂��B |
| �@�n�K�͓S�R���N���[�g�A�n��Q�K�͖ؑ��̊���ŁA�z�[���͊J���I�Ȑ��������ɂȂ��Ă��܂��B���{�����������[�K���͉��l�Ɉڂ�Z�݁A�������̌����̐v���肪���܂����B�R��P�P�P�Ԋق͉��l�s�̕������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
�����L��
 |
�@�C�M���X�قƎR��P�P�P�Ԋقɋ��܂ꂽ�����L��ɂ͉��l�n�ݐ����L�O�������̕������ݒu����Ă��܂��B |
| �@���g���ȃo�X���^�s���Ă��܂����B |
 |
�C�M���X��
�����肷����
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�P�P�T�|�R�@�`�̌�����u������
Tel 045-623-7812
 |
�@�C�M���X�ق͉��l�s�̕������Ɏw�肳��Ă��錳�p�����̎��ٓ@�ł��B���a�P�Q�N�i1937�j�ɉp���l�v�Ƃɂ���Č��Ă�ꂽ�R���j�A���X�^�C���̗m�قł��B |
| �@���a�S�T�N�i1970�j����͉��l�s�̌����{�݂ɂȂ�܂����B�C�M���X�ق̌��ꏊ���瓹�H������Ŋ�蔎���ق̌�������܂ŁA�������疾�������ɂ����ăC�M���X�R�����Ԃ����Ƃ��낾�����ł��B |
 |
 |
�@�����P�S�N�i2002�j����͈�ʌ��J���s����悤�ɂȂ�܂����B�Q�K�ɂ͉p���̗��j�ȂǂɊւ���e�펑�����W������Ă��܂��B�������ꂽ�Q����e�펑���̓W���Ȃǂŏ��a�����̉p�����̎��̐������킩��܂��B |
���[�Y�K�[�f��
| �@�C�M���X�ق̑O�̖�W�畽�����̓y�n�ɂ͖�W�O��P�W�O�O���̃o�����A�����Ă��܂��B���[�Y�K�[�f�����K�N���炭�T���ƂP�P���A�K�N�ɕ�܂��悤�ɂ��Č��C�M���X�ق̎p����Ԕ������悤�ł��B |
 |
�Q�[�e����
 |
�@�Q�[�e���Ղł��B�{���ʂ�Q�[�e���ɑւ��A�����P�W�N�i1885�j�t�����X�l���z�ƃT���_�ɂ���Č��Ă�ꂽ�R��Q�[�e���̐Ւn�ł��B���{�ŏ��߂ăV�F�C�N�X�s�A�����㉉�����Ƃ���ł�����܂��B |
���~���[�W�A��
���킳���݂�[������
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�Q�T�S
Tel 045-623-2111
| �@���a�T�T�N�i1980�j���w�����Q�[�e���Ւn�Ɍ��������ĕ����̔����قɂ��������ł��B |
 |
 |
�@�Ñ�G�W�v�g���猻��܂ł̕����̕ϑJ���Q���̂P�̏k�ڂōČ�����Ă�����A�K���X�H�|�i�Ȃǂ���Ă���悤�ł��B |
�O�l��n
��������ڂ�
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�X�U
Tel 045-622-1311
| �@�`�̌�����u�����̐��ʂɂ���O���l��p�̕�n�ł��B�����S�N�i1854�j�A�����J�̃y���[��̓~�V�V�b�s����Ŏ��̎������������o�[�g�E�E�B���A���X�������ɑ���ꂽ�̂��n�܂肾�����ł��B |
 |
 |
�@�n�߂͓��Ęa�e���ɂ���āA�ɓ����c�̋ʐɕč��l�p��n���݂����܂������A�x�X�ς����āA�c���Q�N�i1866�j���݂̏ꏊ�ɂقڌ��݂̕��܂Ŋg�����ꂽ�����ł��B |
| �@���v�Q�N�i1862�j�X���̐��������̋]���҉p�����l�`���[���Y����`���[�h�\���A�����S�̏���Z�t���������A�d�b�Z�t���[�\���A�t�F���X���w�@�n���҃L�_�[�當���J�Ԃ̌��J�҂Ȃǂ������ɖ�������Ă��܂��B |
 |
 |
�@�ً��̒n�E���l�Ŗv�����O���l�A�S�O�J���]���S�U�O�O�l���P���W�畽�����̕~�n�ɖ����Ă��܂��B |
�R��\�Ԋ�
��܂Ă��イ��
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�Q�S�V
Tel 045-621-4466
 |
�@�R��\�Ԋق͎R��̍���Ɍ����n���ȗm�قł��B���a�S�Q�N�i1967�j�����P�O�O�N���L�O���Č��Ă��܂����B�V���{���ł���Ƃ艮���̎��v�䂩��͐Ԃ��C�̃����f�B���苿���A�R��̏ے��ɂ��Ȃ��Ă��܂��B |
| �@�P�K�̓e�B�[���[���A�Q�K�̓��X�g�����ɂȂ��Ă��܂��B�O���l��n���ӂ̌i�ς��ЂƂ���G�L�]�`�b�N�ɂ��Ă��܂��B���̎��ӂ͐_�ސ�̌i���T�O�I�ɑI��Ă��܂��B |
 |
�R�莑����
��܂Ă���傤����
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�Q�S�V
Tel 045-621-4466
 |
�@�R�莑���ق͖����S�Q�N�i1909�j�Ɍ��z���ꂽ�����̂܂ܕۑ�����Ă���M�d�Ȗؑ��m�قł��B���l�̖ؑ��m�ق̒��ł����������A�֓���k�Ђł̓|��A�Ď���Ƃꂽ�M�d�Ȍ����ł��B |
| �@���̌����́A���l�E�˕��̑�H�ɂ���Ē��V�@�Ƃ��Ė{�q�Ɍ��Ă��A���a�S�N�i1929�j�ɉ��l�E�z�K���̉��c�@�Ɉڂ��ꂽ��A ���a�T�Q�N�i1977�j�Ɍ��ݒn�Ɉڒz���ꖾ������吳����̉��l�����ɓ`���鎑���قƂȂ�܂����B |
 |
 |
�@�J�`�����̐�����`����Ƌ��H��Ȃǂ̃R���N�V�������L�x�ɂ���܂��B�G�������h�O���[���̕ǁA�����o���̃o�����X�������������ł��B |
�u���L�̂������ᔎ����
�Ԃ肫�̂�������͂��Ԃ���
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�Q�R�X
Tel 045-621- 8710
| �@����T��c�ɏo�����Ă�����W�ƁE�Ӓ�m�ł���k���Ƌv���̂������ᔎ���قł��B���W�����u���L�̂��������W�����锎���ق���낤�ƁA�Â��m�ق��������ď��a�U�P�N�i1986�j�ɃI�[�v�����܂����B |
 |
 |
�ٓ��͓������~���[�W�A���V���b�v�A���������قƂȂ��Ă��܂��B�R���N�V�����́A1890�N�ォ��1960�N��ɓ��{�ō��ꂽ���̂𒆐S�ɁA�u���L���̐l�`�A�ԁA��s�@�Ȃǂ�������W������Ă��܂��B |
�R�萹����
��܂Ă�����������
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�Q�R�S
Tel 045-622-0228
 |
�@���������̌������Ɍ������̏�̂悤�ȑ�J�Α���̋���ł��B���v�Q�N�i1862�j�ɉ��l�ݏZ�̉p���l���R�����ɐݗ������N���C�X�g����O�g�ŁA���̌�R��Ɉڂ��������ł��B���݂̌����͏��a�U�N�i1931�j�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł��B���F�������ł����B |
�R��Q�R�S�Ԋ�
��܂ĂQ�R�S��
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�Q�R�S�|�P
Tel 045-625-9393
 |
�@���a�Q�N�i1927�j���댚�݂��ꂽ�O���l�����A�p�[�g�����g�n�E�X�ł��B�T�^�I�ȗm���Z��̑���ŁA�k�Ќ�ɋ��Z�����O���l�̐�����`����M�d�Ȍ����ł��B |
| �@�S�̓���`���̏Z�˂��������̌��փ|�[�`���͂���őΏ̓I�Ɍ����������A�㉺�ɏd�Ȃ��Ă��܂��B�܂��Z�˂͗m���Z��̕W���I�ȗv�f�ł���グ���������낢�˂Ȃǂ͊ȑf�Ȏd�l�ɂȂ��Ă���̂������ł��B |
 |

�G���X�}���@
���肷�܂�Ă�
�_�ސ쌧���l�s���挳��1���ڂV�V�|�S
Tel 045-211-1101
 |
�@�����������̎R��{�ʂ�ɖʂ��������m�قł��B�X�C�X�l�f�Տ��G���X�}���̓@��ł��B�吳�P�T�N�i1926�j���㌚�z�̕��ƌ����郌�[�����h�̐v�Ō��Ă�ꂽ�����ł��B |
| �@�������N�i1989�j�Ɍ��������̕~�n���Ɉڒz��������A�u�G���X�}���@�v�Ƃ��Č��J����܂����B�R��{�ʂ�ɕ��ԗm�ق̂ЂƂƂ��Ċό��q���W�߂Ă��܂��B
|
 |
 |
�@�@���ɂ͎����W�����̂ق��A�g�F�̂��鉞�ڎ���T�����[���Ȃǂ������܂��B�G���X�}���@�̐����ɂ͘H�n������Ńx�[���b�N�z�[���������Ă��܂��B |
��������
���Ƃ܂���������
�_�ސ쌧���l�s���挳��1-77-4
| �@�O���l��n�̐��ɗאڂ��A�R��{�ʂ艈���̎ΖʂɍL��������ł��B���������ɂ́A���̈�т���N���o��V�R�����O���D�̈������Ƃ��Ĕ���ꂽ���߁A�u�����~�v�ƌĂ�Ă��������ł��B |
 |
�R��J�g���b�N����
��܂Ă��Ƃ�������傤����
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�S�S
Tel 045-641-0735
 |
�@�w�Z�Q�Ɉ͂܂��R��̊X�ŁA�t�F���X���w�@�̌������ɔ��ΐF�̐듃�����S�V�b�N���z�̃J�g���b�N�R�苳�����܂��B |
| �@���v�Q�N�i1862�j�t�����X�l�_���W�F���[���������n�W�W�Ԓn�Ɍ��Ă��J�`��̓��{�ŏ��߂ẴL���X�g����ł��鉡�l�V�哰���O�g�ł��B |
 |
 |
�@�����R�X�N�i1906�j�ɂ����R��S�S�ԊقɈڂ��������ł��B�o��������������̃S�V�b�N���̋���ͤ�u�Ƃ�₻�v�Ɠ��{�l�̊ԂŌĂꤐe���܂�Ă��������ł��B�֓���k�Ђŕ��܂������A���a�W�N�i1932�j�ɍČ����ꂽ�����ł��B |
| �@���ƃ}���A���̓t�����X���瑡��ꂽ���̂������ł��B���l�s�F����j�I�������Ɏw�肳��Ă��邻���ł��B |
 |
�R�����
��܂Ă�������
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�Q�R�O
Tel 045-671-3648
 |
�@�t�F���X���w�@��w�̐�ɂ�������ł��B���w���̉̂��^���̂̒���ʂ�߂���ƃe�j�X�̋���ł����������Ă��܂��B |
| �@�����R�N�i1870�j�O���l��p�V�y��Ƃ��đ���ꂽ���{���̒뉀�������ł��B |
 |
 |
�@�����X�N�i1876�j�ɓ��{�ŏ��߂ă��[���e�j�X���s�Ȃ��u���{�닅���˔V�n�v�ƍ��܂ꂽ�L�O�肪�����Ă��܂��B |
| �@�����P�P�N�i1878�j�����l�������������������R�n�}�E�C���^�[�i�V���i���E�e�j�X�N���u������܂��B |
 |
���l�R��e�j�X���ˋL�O��
�悱�͂܂�܂ĂĂɂ��͂����傤���˂�
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�Q�R�O
Tel 045-671-3648
 |
�@���l�R��e�j�X���ˋL�O�ق͎R��������ɂ���A���{�ɂ�����e�j�X�̗��j��W�����Ă��܂��B�ؑ��Q�K���ĂłP�K���W�����A�Q�K��������Ǝ��ɂȂ��Ă��܂��B1870�N��̃e�j�X�p�i�A�e�j�X�E�G�A�Ȃǂ�����ł��܂��B |
| �R��e�j�X���ˋL�O�� |
�O�����̉�
������������̂���
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�P�U
Tel 045-662-8819
| �@�R��C�^���A�R�뉀�ɂ���A�����J���E���B�N�g���A�����̗m�قł��B�����̒뉀�͕����Q�N�i1990�j�ꕔ���J�����뉀�ŕ~�n�ʐϖ�P���R�畽��������܂��B�C�^���A�ő���������뉀�l����͂������Ԓd���w�I�Ƀf�U�C�����������ł��B |
 |
 |
�@�����P�R�N�i1880�j���疾���P�X�N�i1886�j�܂ŃC�^���A�̎��ق��u����Ă������Ƃ���A�u�C�^���A�R�v�ƌĂ�Ă��邱�̏ꏊ�ͤ�݂ȂƂ݂炢�Q�P�n���֓����ӂ̎s�X�n����]���邱�Ƃ��ł��܂��B |
| �@��O�����̉ƣ�́A�j���[���[�N���̎��߂��������{�̊O�����E���c��Ƃ̎��@�����������ł��B�����S�R�N�i1910�j�����a�J�̓약��Ɍ��Ă�ꂢ�����̂ł��B�@ |
 |
 |
�@�����X�N�i1997�j�����R��C�^���A�R�뉀�Ɉڒz��������܂����B�v�͂i�D�l�D�K�[�f�B�i�[�ł��B�A�����J���r�N�g���A�l���̌����͏d���ŁA�����̃X�e���h�O���X�͓����̗l�����f���Ă��܂��B |
| �@�H���A�q�ԁA���ցA�Q���ȂǁA�����̗l�q�𒉎��ɍČ����Ă����܂��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
�u���t�P�W�Ԋ�
�Ԃ�ӂP�W��
�_�ސ쌧���l�s����R�蒬�P�U
Tel 045-662-6318
 |
�@�R��C�^���A�R�뉀�����̉E���Ɍ������̓u���t18�ԊقƂ��Ă��܂��B�吳�����Ɍ��Ă�ꂽ�O���l�Z��ŁA���͎R��J�g���b�N����i�ՊقƂ��ĕ����R�N�i1991�j�܂Ŏg���Ă��������ł��B |
| �@�����T�N�i1993�j�����Ɉڒz��������܂����B�ؑ�2�K���ĂɃt�����X���A��낢�˂����T�^�I�ȊO���l�Z��ł��B�����g�p����Ă������l�Ƌ�̕����W��������ȂǁA���ۂɓ����̕�炵��̌����邱�Ƃ��ł��܂��B |
 |
�O�k��
��������
�_�ސ쌧���l�s����{�q�O�V�J58-1
| �@�O�k���́A���l�s�̓쓌����{�q�C�݂ɉ������R��J�Ȃǂ̔��������R�̋N�������̂܂ܐ���������L��ȏ����{���뉀�ł��B |
 |
 |
�@�ʐς͂P�V���T�畽�����i��T�R�C�O�O�O�j�ɂ��y�Ԃ��̒뉀�ͤ�����f�Ղō����Ȃ������l�̎��ƉƁE���x���Y�̎�ɂ���Đ������߂đ����܂����B |
| �@�x���Y�̍����O�k���������ߎO�k���Ƃ������O�ɂȂ�܂����B���p���D�ƂƂ��Ēm���A�˔\���鑽���̌|�p�Ƃ̉����A�琬�ɗ͂𒍂����{��d�ɑ���ȉe����^���܂����B |
 |
| ��r�ƎO�d�� |
 |
�@����A�E���������i�����Ⴍ�݂傤�����j�̕�����͂��߂Ƃ���ނ̌Ô��p�̃R���N�V�����͍����L�����ւ�܂����B���̏�A�Ì��z�̈�i��뉀�ɔz�����]�������������̂ł��B |
| �@�r |
| �@�����ɂ͂P�O���̏d�v���������܂ނP�V���̗��j�I���z�����A�l�G�܁X�̎��R�̌i�ς̒��ɍI�ɔz�u����Ă��܂������������s�⊙�q�Ȃǂ���W�߂������A�a�ɁA�O�t�A�����Ȃǂ̖��̂���Ì��z�̈�i����ł��B |
 |
| �Ί� |
 |
�@���O�k�͌��P�O�Y�ɖ��ɓ������l���Ŋ����Ò����g�̍��_�؉Ƃ̒��j�ł����B����c�̑O�g�̓������w�Z�̊w������������A�Ռ��������Ɍ����܂�A�Ռ����w�Z�̐搶�ɂȂ�Ƃ����āA�K���Ɨ��j�A�����������Ă��������ł��B |
| �@�����Ō��P�O�Y�̂ЂƂ薺�E�����q����ƒm�荇��������̖��A�{�q�ɓ����������ł��B���P�O�Y�͉��l�J�`��R������A�R�ѓ����蕥����ʂ�艡�l�̒n�ɏo�Đ����ɖڂ�t����������Y�n���삯���萶�����W�߁A���@���Ƃ��ē��p�����������̊�Ղ��m�������l�ł����B�����Č��O�k�͂����傫�������l���ł����B |
 |
| �務�n�� |
���Ċt
�������傤����
 |
�@���@�r�̎R��ɂ͒��Ċt�i�����ƏZ��j������܂��B���O�k�������R�O�N��Ɏ��@�Ƃ��Č��Ă��Z��ł��B�ߔN�̕����������Ƃɂ��n�������̎p�ɖ߂���܂����B |
| ���Ċt |
| �@���Ċt�͊y�����E���̊ԓ��E���֓��E�q�ԓ��E���ԓ��E�q�Ȃǂ̌����Q�ō\������Ă��܂��B�����ʐςX�T�O�������[�g���ɂ��y�ԍL��ȋK�͂̌����ł��B���l�s�̗L�`�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ���Ċt |
 |
�@���̌����͋��Z�p�Ɨ��q�p�̋@�\�����킹�����A���l�s��̋ߑ�a�����z���\���Ă��܂��B�O�k�ƌ𗬂̂��������R��ςȂǑ����̕����l���x�X�o���肵���ꏊ�Ƃ��Ēm���Ă��܂�� |
| ���Ċt |
���
������
| �@�����������Ώ�̓���i��ł����ƌ��ƌĂ����傪����܂��B���̖�͋��s�̐������ɕ�i�T�N�i1708�j�����c���ꂽ���̂ł��B�吳�����ɎO�k���Ɉڒz����܂����B���l�s�̗L�`�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ��� |
���_�@
�͂�����Ă�
 |
�@��������Ă����ƕ��̌����ɔ��_�@������܂��B���̌����́A���O�k���吳�X�N�i1920�j�A�B�����Ƃ��Č��Ă���������z�ł��B�����ȍ~�ɂ�����ߑ�a�����z���\������̂Ƃ����Ă��܂��B |
| ���_�@ |
| �@�����̍\���͒P�ɋ���Ƃ��Ă����łȂ��A���p�i�̊ӏ܂�ڋq�Ȃǂ̖ړI�����˔������z�u��Ԏ��ɂȂ��Ă��邻���ł��B���O�k�͖S���Ȃ�܂ł̖��\�N�Ԃ����ɏZ��ł��������ł��B���l�s�̗L�`�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ���_�@ |
�O�k�L�O��
�������˂�
 |
�@�O�k�L�O�قł́A�O�k���̑n�ݎ҂ł��錴�O�k�̋Ɛт�䂩��̔��p�i�Ȃǂ��Љ�Ă��܂��B�܂��O�k���Ɋւ��鎑������p�H�|�i�����W�����Ă��܂��B |
| �O�k�L�O�� |
| �@�u���̖��Z�Ȏ��R�̕��i�͑n����̂��̂ł����Ď��L���ł͂Ȃ��v�Ƃ��āA�����R�X�N�i1906�j����L����ʂɌ��J�����悤�ɂȂ��������ł��B |
 |
| �O�k�L�O�� |
 |
�@���r�[�ł́u�O�k���̎l�G�v���̃r�f�I����f���Ă��܂��B�O�k���͌��݂ł͍��c�@�l�O�k���ۏ���̎�Ɉڂ���ĕ����H����ۑ�����Ă��邻���ł��B |
| �O�k�L�O�� |
�Տt�t
����
| �@�Տt�t�́A�I�B����Ə���̗��邪�A�c���Q�N(1649)�ɘa�̎R�̋I�m�쉈���Ɍ��Ă��Ă̕ʑ��̈�̌��o��a�Ƃ����Ă��܂��B |
 |
| �Տt�t |
 |
�@�ʏ̓��R��a�Ƃ������L�b�G�g���z�����ڊy��̕ʓa�Ő痘�x��������������Ƃ����Ă��܂������ŋ߂̒����ł͌��o��a�����L�͂Ȃ悤�ł��B |
| �Տt�t |
| �@����W�㏫�R�g�@�͗c�����A���̊ޏo��a�Ɉ炿�A���ی��N�i1716�j�ɏ��R�ɂȂ�܂����B��������@����̕ʑ����z�Ƃ��āA�{�ƕʑ��E�j���{�Ƌ��ɕʑ����z�̑o���Ƃ����Ă��邻���ł��B |
 |
| �Տt�t |
 |
�@�吳�U�N(1917)�ɁA�O�≀�Ɉڒz����܂����B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�L�����{�뉀�̒��Ɍ�����3�A�Ȃ����悤�Ȑ��������@���\���Ă��܂��B |
| �Տt�t |
| �@�O���͉Ԃ��y���ލ\���ɂȂ��Ă��܂����A���������ɂ���Տt�t�ł͌Ì��z���n���Ȓ낪���͓I�ł��B���s��j���{�Ƃ悭�Δ䂳��邻���ł��B���a�R�R�N(1958�N)�̌��J�܂Ť���Ƃ̎��낾�����Ƃ���ł��B |
 |
| �Տt�t |
 |
�@�R���̌����̂�����ꉮ�͌��ւɂ�����܂��B�߂̊ԁA���傤���̊ԁA�Ԓ��̊ԁA��q�̊Ԃ̂S��������܂��B |
| �@��͉y���̊Ԃł��B�y���̍T���̊ԁi�Պ�����̊ԁj�A�y�������i�Q�̊ԁj�A�y������i�Z�V�]�̊ԁj�̎O����������܂��B�E�͘Q�i�Ȃɂ�j�̊Ԃł��B���i�����`���Ă��܂��B |
 |
| �Տt�t |
 |
�@��O���͉Ƒ��̕����ɂȂ�܂��B�Q�w�ŏ�w�͋�܊���A�w�畘���A���w�͂����畘���ł��B�V�y�̊ԁA���̊ԁA�O�̊ԁA��K�̊Ԃ�����܂��B |
| �Տt�t |
| �@�V�y�̊Ԃł��B���Ԃɂ͖{���̉�y��́A♁C�Ђ��肫�A���J�@�叭��{�������Ă��܂��B���̂��Ƃ���V�y�̊ԂƌĂ�Ă���̂ł��B�y��𗓊Ԃɏ���Ƃ͋����ł��B |
 |
| �Տt�t |
 |
�@���̊Ԃł��B���q����A��������`����ꂽ�T�@���z�ɂ͉��̌`�������Γ������g���܂����B�����̕Ǔ��ɂ��̌`�̏o����������Γ����ƌĂ��l�ɂȂ�܂����B��K�ɏオ��K�i���ɂȂ�܂��B |
| �Տt�t |
����
�@�Տt�t�Ƌ��V�������������̊Ԃɉ˂��鋴�̒����Ɂu�����v������܂��B�w�畘���̓��j���̉������������D��ȋ��ł��B�p���t���b�g�ɂ͒����ƂȂ��Ă��܂������X�́u������v�Ƃ����Ă����悤�ł��B�u����v�Ƃ������͖w���Ɂu�ˁv�Ƃ��������ł��B
|
 |
| ���� |
���V������������
���イ�Ă�������Ƃ��������ǂ�
 |
�@�V���Q�O�N�i1592�j�L�b�G�g����̑吭���̕a�C�������F�肵�ċ��s�哿�����ɓV���������Ă܂����B���������ĕ��������̂���Ѥ�V�����ɐΑ��̎��������Ă܂����B�����Ƃ͒������j���Đ������Ɍ��Ă��̂��Ƃł�����̌����͂��̎����̕����ł��B�ߔN�̏C���œV���P�X�N�̖n��������������A�����n���̔N��ƈ�v���ďG�g�̌����������̂ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B |
| ���V������������ |
| �@�����ېV�̍ہA�V�����͔p���ɂȂ蕢���͗��k�̐����@�A�哿�����~�@���o�āA�����R�T�N(1902)�O�k���Ɉڒz����܂�����Ȃ������͑����X�D�U�T�ڂ̐Α��ō����哿�����A���Ď��i���V�����j�ɂ���܂��B
���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ���V������������ |
���ؓa
�������ł�
 |
�@�Տt�t�̐����Ɍ��ؓa������܂��B���̌����́A����ƍN���c���W�N(1603)���s��������Ɍ��Ĥ���喼�f��̍ۂ̍T���ɂ��Ă����̂Ɠ`�����Ă��܂�����̌��������̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| ���ؓa |
| �@���a�U�N�i1620�j��������̎��A�F���̒����㑺�O���ɗ^������ɏ㑺�Ƃ����s���@�@�̎O���ˎ������@�Ɋ��q�a�Ƃ��Ďg���Ă������̂ł��B�吳�V�N(1918)�ɎO�k���Ɉڒz����܂���� |
 |
| ���ؓa |
���ьA
�����������
 |
�@���ؓa�̉��ɑ����悤�ɂ��ċ��ьA������܂��B�吳�V�N�i1918�j���O�k���ɂ���đ���ꂽ���������̒����ł��B�G�z�͖����̐���ҁA�O��̉v�c�݉��̏��ł��B |
| ���ьA |
| �@�����ɋ��s���厛�̎O��ł�����ъt�̍����̎肷������̒����̏����Ɏg���Ă��邱�Ƃ��炱�̖����t���������ł��B |
 |
| ���ьA |
�V���@
�Ăア��
 |
�@���ؓa�̉��A�쐼�ɓV���@������܂��B���̌����ͤ���q�̌������̓����ł���S�����i��������j�Ƃ����p���Ղɂ������n�����Ƃ����Ă��܂��B |
| �V���@ |
| �@���a�R�X�N�i1964�j�ɉ�̏C�����s���A���̍یc���S�N�i1651�j�̖n��������������A�����̔N�����炩�ƂȂ�܂����B |
 |
| �V���@ |
 |
�@�吳�T�N�i1916�j�ɎO�k���Ɉڒz����A���Ƃł͂�����������Ƃ��Ďg���Ă��������ł��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �V���@ |
���H�t
���傤���イ����
| �@�����Ȑ���n���Ă����ƒ��H�t������܂��B�Տt�t�̐��A���ؓa�̓�ɂ�����܂��B��w�̘O�t���z�ŏ�w�͊���A���w�͓��ꉮ����ł��B�������畘���ł��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ���H�t |
 |
�@���̌����͂��ƎO�}�t�ƌĂ�A���a�X�N�i1623�j�O�㏫�R����ƌ����㗌�ɍۂ��A���v�ԏ��Ăɖ����āA���s�������ɂ��点�����̂Ƃ����Ă��܂��B |
| ���H�t |
| �@���̌ケ�̌����͓���ł���t���ǁi�������̂ڂˁj�Ɏ���A�ǂ͂����v�̈�t��̍]�˓@���Ɉڂ��������ł��B�����P�S�N�i1881�j�����ᏼ���̓�����@�Ɉڒz����A�吳�P�P�N�i1922�j�O�≀�Ɉڒz����܂����B |
 |
| ���H�t |
 |
�@�Z�\���萅��(�Ђ傤������傤����)�ł��B�L�b�G�g�����p���Ă����Ɠ`������萅���ł��B |
| �Z�\���萅�� |
�t���h
�������
| �@���H�t�̓�ɂ͏t��ḂƂ�������������܂��B���̌����́A���Ƌ��s���@�@�̎O���ˎ������@�ɂ��������ؓa�ɕt�����ė��Ă��Ă��������ł�����O�k���r�p���Ă������ؓa�Ƌ��ɓޗǂ̍�������ʂ��Ĕ�����������̂ł��B |
 |
| �t���I |
 |
�@�D�c�M���̒�E�D�c�L�y�Ă����Ă����̂Ɠ`�����O��̒����ł�������X���邽�ߋ㑋���ƌĂ�Ă��������ł��B���~���肩�璃������ֈڂ�ߓn���̂��̂Ƃ��Ē��ڂ���܂��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �t���I |
�@�؉@
�����
| �@�|�̒��̏��a�ɘ@�؉@������܂��B���V�������������̓쓌�ɂȂ�܂��B�吳�U�N�i1917�j�Ɍ��O�k�����Ă��c�ɕ������ł��B���]�⏬�ьÌa���K�˂������ł��B |
 |
| �@�؉@ |
 |
�@�Z��Ɠ�����̒���������܂��B�y�Ԃƕǂɂ͉F�������@�P�����Ɏg���Ă��������~���Ɗi�q������܂��B���͍]�ˌ���̖��m�A�����M�̎ʂ��Łu�����ӂĒ��ɂ܂��v�Ə�����Ă��܂��B�哿�����ˉ@�̍��R�a���̕M�ɂ����̂������ł��B |
| �@�؉@ |
���
| �@�C�ݖ�Ƃ��Ă����ł��B����������Ă��܂����������P�P�N�i1999�j�P�P���ɏo����ł���悤�ɂȂ�܂����B |
 |
| ��� |
�����t
 |
�@���\�}�ȍ⓹��o���āA�T���Ƃ������M�������蔲����ƁA��K��������ɂȂ��Ă��鏼���t������܂��B����قnji�F�͗ǂ��Ȃ��Ζ��R���r�i�[�g�̉��˂Ƒ召�^���N�̗ї��ł����B |
| �@�����t���狌�������̎O�d���ւ����R���̓r���ɏo���ω��̐Ε����������Ă��܂����B |
 |
���������O�d��
���イ�Ƃ��݂傤�����イ�̂Ƃ�
 |
�@�O�≀�̃V���{���̂悤�ɒ����̎R��Ɍ��O�d���́A�������ɂ��������̂��A�吳�R�N�i1914�j�R���Ɉڒz�������̂ł��B�������͐����V�c�̒���ɂ��m�s��ɂ���ēV���V�N(735)�ɊJ�n���ꂽ�Ƃ����Ă��܂������݂͔p���ƂȂ��Ă��܂��B�ߔN�܂ŋ��s�{���y�S�i�����炭�j���Β��ɏ��݂������@�@�̎��@�����������ł��B |
| ���������O�d�� |
| �@�������͒�ςT�N�i863�j�ɐ��a�V�c�̒��莛�ƂȂ�A��k���̓����ōr�p��A�N���R�N�i1457�j�ɓV��@�̎��@�Ƃ��čċ������悤�ł��B�O�d�������̎��ɍČ����ꂽ�悤�ł��B�����̎O�d���ŁA�����Șa�m����Ȃ��Ă��āA�T�@�l�̉e���͑S���Ă��܂���B�֓��n���ł͍ŌÂ̓��ł��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ���������O�d�� |
 |
�@�����͓����������R�ω��������������ł��B�������Ɖ��߂܂������A�������N�i1661�j�ɓ��@�@�։��@�����ہA���������瓕�����ɉ��߂������ł��B�S���͊e�d�A�e���ňقȂ�܂����A���̐�[�̖�l�͓������ɂȂ��Ă��܂��B |
| ���������O�d�� |
| �@�����A�ʕI�A�g�ݕ����̕��ނ͑�����������Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B�I��ԋ߂����a�Q�O�N�i1945�j�U���̋ɂ�莊�ߒe��������e�Ђő��������a�Q�X�N�i1954�j�ɏC������Ă��܂��B |
 |
| ���������O�d�� |
 |
�@�����قڒ����̏������R�̒���ɐؐΐς̊�d��z������ɉ���݂����Ă��Ă��܂��B�����e�����猩���A�܂��ɎO�k���̃����h�}�[�N�ɂȂ��Ă��܂��B |
| ���������O�d�� |
��������
�͂˂����
| �@���������O�d�����牺���Ă���Ə�������������܂��B�����̐^�ɂ͈͘F�����L��A�̂͂����ō����┒����U�镑���Ă��������ł��B���݂ł͊ϔ~��̊��Ԓ��̂Ê��ŕ��������������o�����悤�ł��B |
 |
| �������� |
 |
�@�C���h�̃m�[�x���ܕ��w�҃^�S�[����H�열�V����������K��ď������邳��Ă��܂��B�H��́A�吳�S�N�i1915�j�����ł̈�ۂ�
�@ �u�ЂƂ͂���@����������@�����̏H�v
�@�Ɣo��Ɏc���Ă��܂��B |
| �������� |
�����c�����a
���イ�Ƃ��������Ԃł�
| �@���c���͍O���W�N�i1285�j�k�����@�̍Ȋo�R�n�����܂����B�썞�����邢�͉��؎��Ƃ��ėL�������������ł��B�����S�O�N(1907)�ɓ��c���̕��a�͎O�k���Ɉڒz����܂����B���̏d�v�������ł��B |
 |
| �����c�����a |
 |
�@���a�̌����N��͖��炩�ł͂���܂��A���͉i��6�N�i1509�j�ɉЂɂ�����Ď����܂����B���a�̌`����@�͎�������̂��̂Ȃ̂ł��̒���ɍČ����ꂽ���̂Ɛ��肳��Ă��܂��B |
| �����c�����a |
| ���a�̊�{�I�Ȍ`���́A�����̒��K�͑T�@�l���a�Ɠ����ł����A�g���͊ȗ�������A�܂��A�����͈�ʂɊi�V���ȂǁA�]�ˊ��̍D�݂������Ɍ����܂��B�������A�S�̓I�Ɏ������̗l����F�Z���c���Ă��܂��B |
 |
| �����c�����a |
����͌��ƏZ��
���イ��̂͂炯���イ����
 |
�@�����S���쑺�␣�i���싽�j�ɂ������������̉Ƃł��B�]�ˎ���̕��N�ԁi1751�`1764�j��˂R���҂̈�l�Ƃ���ꂽ�����̖��������̉ƂƂ��Ďg���Ă������̂������ł��B |
| ����͌��ƏZ�� |
| �@���߃_���̌��݂ɂ���ČΒ�ɒ��މ^���ɂȂ�܂����̂ŁA���L�Җ�͌��Ƃ���O�k���Ɋ���A���a�R�T�N�i1960�j�Ɉڒz����܂����B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ����͌��ƏZ�� |
 |
�@�����̖ؑg��"����"�ƌĂԊۑ����������킹���悤�ɍ��E����g��ł���̂ŁA��������Ƃ����Ă��܂��B�����͍����������䌺�ւ������@����A�E��������ʔ_�Ƃ̑���ł��B�㊯�Ȃǂ̕o�q���}����q���~������܂��B�����Ƃ̋��ɂ͟D�ɕd�A��ʎU�炵�ȂǁA�������������̗��Ԓ������͂߂��Ă��܂��B |
| ����͌��ƏZ�� |
���J��
�悱�Ԃ�����
| �@��������n�������ɉ��J��������܂��B�Íނ��Ă���ꂽ�c�ɕ��̒����ł��B���J�͍��q�V�c���{�A�����@�Ɏd���܂����B���d���̉Ɛb�A��������i�֓������j�Ƃ̔ߗ��͗L���ł��B |
 |
| ���J�� |
 |
�@���J�͎��ɂ������ē������瑗��ꂽ�瑩�̗����������ČȂ̑�������܂����B���̑������̈��Ɉ��u����Ă����̂ł��B��Q����풆�ɔ�Q�������Ă��܂��������ł��B���R�����̖��������ɂ�����Q����`���w���\���鏬���u��������v���L���ł��B |
| ���J�� |
| �@���J�̕����������Ƃ����������ŗ��ɗ������֓������͐e�ɂ�������o�Ƃ��āu��������v�ɂȂ�A���s�̑�����ŏC�Ƃ��܂��B�݂菈�������J���K�˂Ă��܂��B |
 |
 |
�@�����͋�������g���ǂ��Ԃ��܂��B���J���������낤�Ƃ��鎞�A���ʼn̂��������u�̐v�Ɂu�R�[�ݎv������ʂ�ł̌˂̂܂��Ƃ̓��ɉ����v�ƌ����c���܂��B���J���o�Ƃ��A�@�؎��̓�ɂȂ����Ƃ��A�剁��ɐg�𓊂����Ƃ������Ă��܂��B |
| ������ |
���������{��
���イ�Ƃ��݂傤���ق�ǂ�
| �@�������͐����V�c�̒���ɂ���ēV���V�N(735)�ɊJ�n���ꂽ�Ƃ����Ă��܂���������͌��ݔp���ƂȂ��Ă��܂����ߔN�܂ŋ��s�{���y�S���Β��ɏ��݂������@�@�̎��@�����������ł��B |
 |
| ���������{�� |
 |
�@�����̕����Ŕp�₵�܂������A�N���N�ԁi1455-1456�j�A�V��m�E�T���������A�{���ƎO�d�������������悤�ł��B���̖{���ͤ�l���㤎������㏉���Ɍ��Ă�ꂽ���̂Ɛ��肳��Ă��܂�� |
| ���������{�� |
| �@ �����R�S�N�i1901�j�썇�F���Y�������������܂����B�����đ吳�R�N�i1914�j�O�k���Ɉړ]�����̂ł��B�����̏t���~�q�͍����ő�̂��̂������ł��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ���������{�� |
�O�k���V���{
��������Ă�܂�
 |
�@�O�k���V���{�͂��Ƃ͊Ԗ�V�_�Ƃ����Ă��܂����B�O�k���ɂقNj߂��Ԗ�̋��ƍ����Ƃ̐�c���{�q�̋u�̒����Ɍ��Ă����̂������ł��B���a�T�Q�N�i1977�j�O�k���Ɉڂ��ꂽ�����ł��B |
| �O�k���V���{ |
| �@��r�ɉ˂���ϐS������͟��Ԓ����݂��܂��B�������牺�����Ă݂�Ƃ�������̋T���̂�т�j���ł��܂����B |
 |
| �ϐS�� |
 |
�@�O�d�����������f�����r�ɂ͑D����ǂۂ�ƕ�����ł��܂����B�����������l�̑D�𑀂��Ă���悤�ł����B |
�O����
���݂傤��
�_�ސ쌧���l�s���O�������Q�U�V
Tel 045-711-1231
 |
�@�O�����i���݂傤���j�́A�����R�@�؉@�ƍ����A���l�s���ɂ���s���ŌÂƂ�����^���@�̎��ł��B |
| �@��������V���������@���ꂽ��A�������N�i1044�j�ɖ{�����Č����ꂽ�L�^���c���Ă��邱�Ƃ���A��������܂��͂���ȑO�̑n���Ɛ��肳��Ă��܂��B |
 |
 |
�@�{���ɂ͍��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���ؑ��\��ʑ������u����Ă��܂��B�s��̍�Ɠ`�����Ă��܂��B�n���̐l�����Ɂu�ω����܁v�ƌĂ�e���܂�Ă��܂��B |
| �@�����ɂ͐g��i�݂����j�n����F������܂��B�l�X�̐g�̂̎��a��S�̔Y�݂��~�ς��Ă���邻���ł��B |
 |
 |
�@���`�ɂ��P�Q�O�O�]�N�O�̗{�V�T�N�i721�j�ɃC���h�̑P���؎O���@�t�ɂ��J�݂��ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B���q����ɂ͌��Ɨݑ�̋F�菊�Ƃ��ꂽ�����ł��B |
| �@���i���j�ƌĂ�������܂��B�@�P���؎O���@�t�͍O�����ɗ��������Ď��̔Ր߂������ł��B���A���Ƃ����g���������Ă�����Ƃ��ĐM����Ă��邻���ł��B |
 |
 |
�@�]�ˎ���ɂ͔��ω��O�\�O�J���̂P�S�ԎD���Ƃ��ĐM���W�ߔN�Q��̎s�������A��ϓ�����������ł��B |
| �@�{���̖ؑ��\��ʊω������͊֓��Ɏc���뒤��i�Ȃ��ڂ�j�̓T�^�I�ȍ��Ƃ��ėL���Ȃ��̂ŁA��������i�P�P�`�P�Q���I�j�̍삾�Ɠ`�����Ă��܂��B���Ă͍����������ł��B |
 |
 |
�@�O�����͍L�����L�n�������Ă��܂������A�p���ʎ߂ɂ����L�n���ŁA�k�̎��L�n�̑唼�����l�s�ɏ��n���܂����B���݂́u�O���������v�Ƃ��Đ�������Ă��܂��B |
���i
���Ȃ���͂�����
�_�ސ쌧���l�s�����
| �@���q����̋���́A�C�ニ�[�g�Ŋ��q�Ɩ[�������ԗv�n�ł����B����̌i�ς͑f���炵���A��������̊G�t�������������܂�Ɍi�ς��ǂ��̂Ŋ������ĕM���̂Ă��Ɠ`�����Ă��܂��B |
 |
 |
�@���i�̖��O�̗R���͉���N�ԂɁi1673-1681�j�ɐ��˓���Ƃɏ�����Ă������̑m�S�z�T�t������ɗ������ɔ\�������猩��ቺ�̔������ɂ����ꕐ�B�\�������i�̎����r���Ƃɔ����܂��B |
| �@�u����̖�J�v�A�u����̕��v�A�u�̖��̔ӏ��v�A�u�쓇�̗[�Ɓv�A�u�F��̐����v�A�u�����̗���v�A�u���w�̋A���v�A�u���˂̏H���v�̂W�ӏ��ƂȂ��Ă��܂��B�����L�d���ъG��`�������Ƃŏ����ɂ��m����悤�ɂȂ����悤�ł��B |
 |
���i���_��
�т킶�܂���
���l�s����搣��
 |
�@�����p�ɓ˂��o���ċ���������܂��B���i�Ɏ��������ȓ���ɔ��i���_�Ђ̏����ȎЂ��J���Ă��܂��B |
| �@���̐_�Ђ́A�s�n���P���J����̂ŁA�����S�N�i1180�j�����������ː_�Ђ��J�����ۂɍȂ̐��q���ٍ��V���J�������̂Ƃ���Ă��܂��B�ٍ��V���͔��i�������Ȃ������ŁA�ʖ��Łu���g�ٍ��V�v�Ƃ��Ăꗧ�g�o���̐_�l�Ƃ��ĐM����Ă��邻���ł��B |
 |
�쓇����
�̂��܂�������
�_�ސ쌧���l�s�����쓇��
Tel 045-781-8146 �@�쓇���N���C�Z���^�[
 |
�@�쓇�͂��ēƗ������Ǔ��ł��������̂��A���w�i�����Ƃ��j�C�݂̍��B���L�т����āA�B�葺�Ɨ������ɂȂ������̂ł��B���̖��̖�P�W���������C�l�����������̂��쓇�����ł��B |
| �@�C��55���[�g���̎R���t�߂ɂ́A�ꕶ���㑁���̖쓇���y�킪�������ꂽ�쓇�L�˂�����܂��B�L�˂���͐Ί�⍜�p����o�y���Ă��܂�����A��W�O�O�O�N�ȏ���O���狙���̐��������������ƂɂȂ�܂��B |
 |
�ɓ������ʑ���
���Ƃ��Ђ�Ԃׂ݂���������
�_�ސ쌧���l�s�����쓇��
 |
�@�������ɂ͖����R�O�N�i1897�j�Ɍ��Ă�ꂽ�ɓ������̕ʑ��Ղ�����܂��B���J����Ă��܂����@�̍ŏI���Ă��쐬�������Ȃ̂ł��B |
| �@�����P�X�N�i1886�j�ɓ������A���q�����Y�A�ɓ������A���B�̂S�l�͍��̋����F��ɂ��������ٓ����Ō��@�R�c���n�߂܂����B���������N���Ă̓������g�����N�����܂�Ă��܂��܂����B |
 |
 |
�@���R�̖C��p�n�Ŗ��l���̉ē��ɕʑ������ĂĂ������ɓ������͗p�S�̂��߂����ɏꏊ���ڂ��ɔ闠�ɑ��Ă�������̂ł����B���Ă͂����Ŋ������Ė����Q�Q�N�i1889�j���z���ꂽ�̂ł����B |
�C�̌���
���݂̂�������
�_�ސ쌧���l�s�����C�̌���
Tel 045- 701-3450�@�C�̌����Ǘ��Z���^�[
| �@���a�T�S�N�i1979�j�X���Ɋ����������l�����ł��B���w�i���Ƃ��j�C�݂��Đ������Ċg�������C�l�����ŁA���l�s�ŗB��C�������y���߂�ꏊ�ł��B���i�́u���w�̋A���v�͂��̂�����ɂȂ�܂��B |
 |
 |
�@���l�̒����͖�炍�A���͂Q�O�O���Ŗ������ɂ͂U�O���ɂȂ邻���ł��B���l�̊g���ɂ������ẮA��t���̐�ԎR�̓y����p���A�̌@�����y�����C��ɂT�N�ԓ���܂��Ă��犈�p����Ƃ������C�̒�����Ƃ��s�Ȃ��������ł��B |
| �@�t���珉�Ăɂ����ăA�T����}�e�K�C�Ȃǂ̒������A�ď�͊C������E�C���h�T�[�t�B���Ȃǃ}�����X�|�[�c�A�o�[�x�L���[���y���߂܂��B���i���V�[�p���_�C�X���悭�����܂��B |
 |
���i���V�[�p���_�C�X
�͂��������܂��[�ς炾����
�_�ސ쌧���l�s����攪�i��
 |
�@���i���V�[�p���_�C�X�́u���R�ƊC�Ɛl�Ƃ̂������v���e�[�}�Ƃ����{�݊��p�^���N���G�[�V�����̋��_�Ƃ��ĕ����T�N�i1993�j�T���I�[�v�����܂����B |

| �@�V�[�p���_�C�X�̒��ŃA�N�A�~���[�W�A���ƕ���Ől�C������̂��C���e�[�}�ɂ����P�S��̃X���������h���y���߂�v���W���[�����h�ł��B�u���[�t�H�[���������܂��B |
 |
 |
�@�n��P�O�V���̍����܂Ń��������Ɠo��u�K�N���b�v�Ƃ����Ռ��Œ���ɓ����B�i�F������ǂ���łȂ��Ԃɐ����ɖ҃X�s�[�h�ŗ������܂��B |

| �@���{���̊C�㑖�s���[���[�R�[�X�^�[�u�T�[�t�R�[�X�^�[�v�̓v���W���[�����h�̖ڋʃA�g���N�V�����ł��B�C�ɓ˂��o�������[�v���삯�����A�C�փ_�C�r���O����悤�ȋC�������킦�܂��B |
 |

 |
�@�l�C�̍������{�ő勉�̐����ق́u�A�N�A�~���[�W�A���v�ł��B�I�[�v�������ẴC���J�̐����فu�h���t�B���t�@���^�W�[�v�ł͌����������邱�Ƃ��ł��邻���ł��B |
| �@�h�[�i�c��L���r���̒��ň֎q�ɍ������܂܂X�O���̍����܂ŏ㏸����u�V�[�p���_�C�X�^���[�v�Ȃǂ�����܂��B�V���������ĂR��]������Ȃ���㉺���A�R�U�O�x�̃p�m���}�����鎖���ł��܂��B |
 |

 |
�@�����h�[���̖�P�W�{�͂���Ƃ����铇�S�̂��A�����فA�V���n�A���X�g�����A�V���b�v�A�z�e���A�����Ȃǂ��W�܂����A��̑傫�ȃA�~���[�Y�����g�{�݂ɂȂ��Ă܂��B |
�̖����i���Ɂj
���傤�݂傤���i���Ȃ���Ԃj
�_�ސ쌧���l�s�������Q�P�Q�|�P
Tel 045-701-9573
| �@�̖����͖k�����̈ꑰ�ł������k�����̑c�A�k�������̑n���ł��B���S�悪���̎j�ՂɎw�肳��Ă��܂��B�̖����̐Ԗ�͏��a�V�N(1932)���ɉw�ւ̓��H�J�݂ɂƂ��Ȃ��V�`�W����ނ��Č��ʒu�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł��B |
 |
| �̖����Ԗ� |
 |
�@�Ԗ�͓��얋�{����������������Ƃ��Ė��Ԃ��h�������Ƃ���t����ꂽ�悤�ł��B���a�N�ԁi1764�`1772�j�ɍČ�����Ă��܂��B |
| �̖����Ԗ� |
| �@���������ɍ]�ˎ������ɏ̖����̌܂̓����̈�ʂ��߂Ă��������@�̕\�傪����܂��B���l�s�w��L�`�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| �����@�\�� |
 |
�@���̕\��́A���K�͂Ȏl�r��ł����A�a�l����ɑT�@�l�����������ӏ��ƂȂ��Ă��܂��B�����T�N�i1665�j�Ɍ��Ă��Ă��܂��B |
| �����@�\�� |
| �@�Q�����܂������ɍs���Ɛm���傪����܂��B�������N�i1818�j�ɍČ����ꂽ���̂ŁA�Ԍ��T�Ԕ��i10���j���s�R�Ԕ��i6.3���j�̘O��ł��B |
 |
| �̖����m���� |
 |
�@���E�Ɉ��u���ꂽ�����͎m���́A�����Q�N�i1322�j�̊��q����ɐ��삳�ꂽ�֓��ő�̐m�����ŁA���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�啧�t�A�@���̍�Ƃ����Ă��܂��B |
| �̖����m���� |
| �@�̖��������ɂ͈������r�𒆐S�Ɏ�F�̔������˂����y���뉀����������Ă��܂��B�z�u�͕������㒆���ȍ~����ɂȂ�����y��䶗��̍\�}�Ɋ�Â�����ꂽ�����A�������ǂ��Ă��܂��B |
 |
| �̖����뉀 |
 |
�@�뉀�͋���匰�̎���̕��ۂR�N�i1319�j����A���N�̌����Q�N�ɂ����đ���ꂽ�����ł��B����@�t����낵���悤�ł��B���a�U�Q�N�i1987�j��������܂����B |
| �̖����뉀 |
| �@�����R�N�i1323�j�ɕ`���ꂽ�d�v�������́u�̖����G�}�����E�L�v�ɂ���āA������뉀�̔z�u�Ȃǂ��`����Ă����̂��Č������̂ł��B |
 |
| �̖����뉀 |
 |
�@�̖����́A����R�̖����ƍ�����^�����@�̕ʊi�{�R�Ƃ��Đ��厛���̗��@�ŁA�{���ɂ͏d�v�������Ŋ��q����ɑ���ꂽ�ؑ����ӕ�F���������u����Ă��܂��B |
| �̖����뉀 |
| �@�m���l�ł������k�������͋��s�≓�����������R�̏��������Ċw��ɗ�悤�ł��B�����̑�ʂ̏������������Ă����̂��̖����ɂ����ꂽ���ɂ������̂ł��B���̎����͎������a�Ŗv���钼�O�̌������N�i1275�j���Ƃ����Ă��܂��B |
 |
| �k������ |
 |
�@���ɂɂ́A�����A���j�A���w�A�����ȂǑ���ɓn�鏑�Ђ����߂��Ă����悤�ł��B����k�����ŖS��́A��̖̏����ɕ��ɂ̊Ǘ����䂾�˂��܂������A���^�̐��ނƂƂ��ɑ���������ɎU�킵�������ł��B |
| �V�{�� |
| �@�퍑����͏㐙���M�R�̗��D�ɂ����܂����B�]�ˎ���ɂ͓���ƍN���]�ˏ���̍g�t�R���ɂ������ߑ����̑����������o����Ă��܂��r�p�����̂ł����B |
 |
| �V�{�� |
 |
�@�����ɂȂ��Ĉɓ������́A�����R�O�N�i1897�j�ɏ̖����̎Q�������ɋ��ɂ��ċ����܂������A�֓���k�ЂŔ�Ђ��Ă��܂��܂����B |
| �V�{�� |
| �@�����ɂ͒�����詓��i�����ǂ��j���c���Ă��܂��B�̖����Ƌ��ɂ̊Ԃɗ����ǂ����Ղ����蔲�����g���l���Ղł��B���q����ɕ`���ꂽ�u�̖����G�}�v�ɂ����̑��݂��L����Ă��邻���ł��B |
 |
| ����詓��� |
 |
�@�k�������ɂ���đn�����ꂽ���{�ŌÂ̕��ƕ��ɂ͏��Ђ̏N�W��ړI�Ƃ�����̂ŁA���̂悤�ȉ{����ړI�Ƃ���}���ق̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����������ł��B |
| �@�����F�̒��S�ɂ��錻�݂̋����͌��a���N�i1681�j�ɍČ����ꂽ���̂������ł��B���Ɉ��u����Ă���{���̖��ӕ�F�����́A�����Q�N�i1276�j�̖�������A���q����̂��̂ł��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| �̖������� |
 |
�@�̖����͖k���������A�Z�Y������̋��ٓ��ɉc���������甭�����Ƃ����Ă��܂��B���̌�A�������������ꤎ����̎q������̎��ɂͤ���ӓ��A�얀����O�d���Ȃǂ���������܂����B |
| �̖������� |
| �@�����̎q��匰�͉����̍đ��c���s��������O�N(1323)�ɂ́A���r�𒆐S�Ƃ��Ė��ӗ��}�G�i�d�v�������j�ɑ������ꂽ���������ߤ�u����m����ȂǁA����������������s��ȏ�y��䶗��ɂ��ƂÂ������������������̂ł��B |
 |
| �̖����߉ޓ� |
 |
�@�����ɗאڂ���߉ޓ��ɂ́A�����R�N�i�P�R�O�W�j���̎߉ޔ@�����������u����Ă��܂��B����͊��q����̂��̂ō��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �̖����߉ޓ� |
| �@�߉ޓ��̑O�ɂ�����O�ɂ́A���i�̈�u�̖��̔ӏ��v�Ƃ��Ēm��ꂽ�������݂���Ă��܂��B����������̒ǑP�̂��ߒ��������̂ł����������A�匰�����������ƈˌ��ɉ������������̂ō��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| �̖������O |
 |
�@�{���O�Ɂu�t���i�����Łj�v�ƌĂ�������܂��B��������̍�����̍�̗w�ȁu�Z�Y�i�ނ�j�v�͔~�A���A���Ȃǂ�l�i�����đ��̐��Ƃ��Ĉ������Ƃ��납��L���ɂȂ��Ă��܂��B�̖�����K�ꂽ���ב����S�R�̍g�t�ɐ�삯�A�{���O�̂��̕��������g�t���邱�ƂɊ������āu�����ɂ��Ă��̈�{�Ɏ��J����A�R�ɐ悾��̂��݂��t�v�Ɖr�����ł��B |
| �t�� |
| �@���͔��Ɍ��h�Ɏv���u���Ȃ薼�𐋂��Đg���肼���͂���V�̓��Ȃ�v�Ƃ̌Ë�ɂȂ炢�A���̌�͍g�t������Ύ��i�Ƃ��킬�j�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B |
 |
| �t�� |
 |
�@�g�t���邱�Ƃ���߂��ߕ��́u�t���v�ƌĂ��悤�ɂȂ��������ł��B���ɂ݂͂ȐS�����邱�Ƃ�����Ă��܂��B���̕��͋ߐ��̒n���ނɂ�����̖��Ƃ��Ă����Ύ��グ���܂������A���̌�A�͂�Ă��܂��܂����B���̖͐V�A���ꂽ���̂ł��B |
| �S�ω� |
| �@����R��o���Ă����ƕS�ω�������܂��B���ĎO�d���t�߂ɐ����P�Ԃ�u���A�����̕�O��ʂ�A����R�ɓo��A��R�A�����R���o�ċ������̂P�W���ɂ킽���Ēu���ꂽ���̂������ł��B |
 |
| �S�ω� |
 |
�@���p���͋���R�̎s���̐X�R���ɂ���܂��B�k���U�U�O�N�����L�O���āA�����َЎ�ł�����ɂ̍ċ��ɍv�������勴�V���Y�����S�ω��ƂƂ��Ɋ�i�������̂������ł��B |
| ���p�� |
| �@���p���ɂ͈ꎞ���A�C���o���ω����J���Ă����������ł��B���̌�S�Ȃ��҂ɉꌻ�݂Ɏ����Ă���Ƃ������Ƃł��B |
 |
 |
�@���p���t�߂̕���ȂƂ���͔��p���L��ƌĂ�Ă��܂��B��������̓W�]�͑f���炵���A���l���S�����Ղł��܂��B���͔��i���A�쓇���ʂ̒��]�@�ł��B |
| �@���p���͏����̒��ɂ������܂��B���c�N�v�́u���l�E�l�����v�ł��B�������Y�Ј������i�̈�A����R�R���̔��p���̒��Ŏ���ł���̂��������ꂽ�Ƃ����X�g�[���[�ł��B |
 |
 |
�@����͊��q�̊O�`�Ƃ��ĉh�����Z�Ö��i�ނ�݂ȂƁj���J����f�Ս`�Ƃ��ē���������ł��B�k����R�㎷���͏d�v�����āA��̖k�����ׂ�n���ɂ��Ē����n�Ƃ��܂����B���Ȍ�A�����A�����A�匰�A�叫�Ƒ����܂����B���ꂪ����k�����Ȃ̂ł��B |
| �@����R�̎s���̐X�R�����班�������Ĕ����`���Ɉ�R�ʂ���s���ƈ�R�x����������A���̐�ɐΒi������܂��B |
 |
 |
�@�������k�������_�ł��B���ʂɂ͋���k�����̕悪����܂��B��n�����̕�⸈��A�����̕�Ɠ`�����Ă��܂��B����ɂR��A�E��ɂQ��̈��̕悪����܂��B
|
| �k�������̕� |
| �@�����́A���q���{�̑��㎷���ł������`���̑��ň��t�O��]��O�Ȃǖ��{�̗v�E���C���A���i�R�N�i1275�j�ɂ͉z�i��s���Ƃ߂Ă��܂��B�߉������{�̗��L�n�̎��ł��{��ǂ�ł����Ƃ����Ǐ��Ƃ������悤�ł��B |
 |
 |
�@���a�P�S�N�ɐA����ꂽ�����i��������j�ł��B�u�g�l���o�n�[�m�L�E�����V���{�N�v��ʂɂ͞��̖Ƃ��Ă��܂��B�́A�����ōE�q�̕�̖T�ɐA�����Ă����̂ōE�q�ƌĂ�A���{�ł��ŏ��́A�w��ƊW�̂��鏊�����ɐA����ꂽ�����ł��B�E�q�M�ƊW�̂��铒�������A�����w�Z�ȂǂɐA�����ꂽ�����ł��B |
| ���� |
����
���Ȃ���Ԃ�
�_�ސ쌧���l�s�������P�S�Q
Tel 045-701-9069
| �@���ɂ́A�k���������ݗ��������Ƃ̕��ɂł��B���{���̎��ݐ}���قł��B�����R�O�N�i1897�j�Ɉɓ�������ɂ���čČ�����܂������֓���k�ЂŎ����A���a�T�N�i1930�j�ɐ_�ސ쌧�̉^�c���镶���{�݂Ƃ��ĕ��������̂ł����B |
 |
 |
�@�����Q�N�i1990�j�ɉ�������A���q����𒆐S�Ƃ������j�����قƁA�����d�v���������܂ދ��ɂ̑����́E��������{�݂����݂͐ݒu����Ă��܂��B����́u���I�W���v�A�k�������ȉ��S��̏ё���A�����̕悩�猩���������قȂǖ�Q���_�̎j�������W����Ă��āA�ꕔ���W������Ă��܂��B |
| ���� |
 ���Ɨ��j�̃z�[���y�[�W�����ǂ� ���Ɨ��j�̃z�[���y�[�W�����ǂ�  �@���{�̃y�[�W�ւ��ǂ�@�@�@�@ �@���{�̃y�[�W�ւ��ǂ�@�@�@�@
|
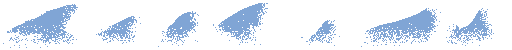


 ���Ɨ��j�̃z�[���y�[�W�����ǂ�
���Ɨ��j�̃z�[���y�[�W�����ǂ�  �@���{�̃y�[�W�ւ��ǂ�@�@�@�@
�@���{�̃y�[�W�ւ��ǂ�@�@�@�@




