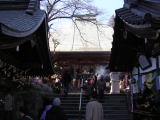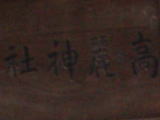更新日:
あなたは

番目の訪問者です
(ogino作成共通カウント)
★
旅と歴史ホームページ
OGIさんのHP
信州上田ホームページ
信州長野ホームページ
真田一族のホームページ
Mr.ogino旅ホームページ
上田の旅と歴史HP
信州の旅HP
日本の旅
世界の旅HP
★
|
渋沢栄一記念館
しぶさわえいいちきねんかん
埼玉県深谷市下手計1204
Tel 048-587-1100
 |
渋沢栄一記念館は近代日本を支えた明治時代の大実業家、日本資本主義の父・渋沢栄一の記念館です。渋沢栄一の肉声テープをはじめ、資料を展示しています。館内の渋沢栄一資料室には、栄一の遺墨や写真などたくさんの資料が展示されています。 |
| 天保11年(1840)、現在の深谷市血洗島の農家に生まれました。27歳の時、15代将軍・徳川慶喜の実弟・徳川昭武に随行しパリの万国博覧会を見学、欧州諸国の実情を見聞しました。渋沢栄一は「論語」の精神を重んじ「道徳経済合一説」を唱え、各種産業の育成と多くの近代企業の確立に努めました。 |
 |
 |
第一国立銀行を設立し、東京ガス、東京海上火災保険、王子製紙、秩父セメント(現太平洋セメント)、帝国ホテル、秩父鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、キリンビール、サッポロビール、東洋紡績など、多種多様の企業の設立に関わり、その数は500社以上もあったそうです。 |
尾高惇忠(藍香)生家
おだかあつただ(らんこう)せいか
埼玉県深谷市下手計
 |
尾高藍香は天保元年(1830)下手計村(現深谷市)に生まれました。渋沢栄一とは従兄弟にあたります。栄一は少年時代、尾高のもとに通い論語などを学んだそうです。 |
| 尾高や渋沢らの青年同志が時の尊皇攘夷論に共鳴し、高崎城の乗っ取り計画をこの2階で謀議したそうです。 尾高は後に官営富岡製糸工場長、第一国立銀行仙台支店長などを歴任しました。 |
 |
箭弓稲荷神社
やきゅういなりじんじゃ
埼玉県東松山市箭弓町2−5−14
Tel 0493-22-2104
 |
箭弓稲荷神社の創建は和銅5年と伝えられています。長元元年(1028)下総国の平忠常が安房・上総・下総の三カ国を制圧し、大軍をもって武蔵国に侵攻してきました。甲斐国守を勤める源頼信は、忠常追討の綸旨を賜り、鎮圧に向かいました。 |
| 源頼信が平忠常鎮圧を祈願し野久稲荷神社に夜を徹して戦勝祈願しました。すると白狐に乗って現れた神様から箭と弓とを賜る夢を見て、苦戦の末、みごと戦に勝利しました。 |
 |
 |
そして、この勝利はご神威、ご神徳によるものだとして、社殿を寄進するとともに、野久稲荷を箭弓稲荷と改めたのでした。以来、箭弓稲荷神社は松山城主、川越城主をはじめとして多くの人々の信仰を集めてきています。 |
| 7代目市川團十郎は特に厚く箭弓稲荷神社を崇敬し、社に籠り芸道精進、大願成就を祈願しました。江戸の柳盛座の新春歌舞伎興行において「狐忠信」「葛の葉」等の芸題を披露しましたところ毎日札止めの大盛況となりました。感謝の意をこめ、文政4年(1821)石造りの祠を建立しています。 |
 |
 |
箭弓稲荷神社には、ぼたんが有名な「箭弓ぼたん園」があります。1500株のぼたんが咲き揃います。つつじ、フジも見事です。社殿は埼玉県の有形文化財に指定され、商売繁盛、開運の神社として知られています。 |
吉見百穴
よしみひゃくあな
埼玉県比企郡(ひきぐん)吉見町北吉見327
Tel 0493-54-1511
 |
吉見百穴は、横穴墓群の遺跡で、大正12年(1923)、国の史跡に指定されています。丘陵斜面につくられた穴の数は219個といわれ、このような遺跡としては日本一の規模です。穴の入り口は直径1m程度です。 |
| 直径1.5m程の穴が、蜂の巣のように開けられたもので、古墳時代後期(6〜7世紀)の横穴墓と考えられています。多くの古墳は土を盛った小山の中に1つだけ玄室が存在しているのに対し、岩山の表面から数mの小穴(古墳の玄室に相当するもの)を多数掘って造られた集合墳墓である。 |
 |
 |
太平洋戦争末期の昭和20年(1945)初頭から8月までの間、この岩山の地下に軍需工場を建設するため、その出入口として岩山の最下部に大きなトンネルが3本掘られたそうです。この地下軍需工場跡も残されていて中を見学することが出来ます。 |
| 明治29年(1896)に坪井正五郎博士による「住居跡」説から、大正時代に、「墓穴」として作られたものであることが明らかになっています。まわりに住んでいた人々が家族が死ぬたびにくり返し埋葬した墓なのです。 |
 |
 |
横穴の中のいくつかには、太陽の光を反射して黄金色に輝く天然記念物の苔、「ヒカリコ゛ケ」が自生しています。尚、関東平野にこの苔があるのは、とても珍しいそうです。 |
蓮馨寺
れんけいじ
埼玉県川越市連雀町7−1
Tel 049-222-0043
 |
孤篷山(こほうざん)蓮馨寺(れんけいじ)は、大道寺駿河守政繁(まさしげ)の実母・蓮馨尼によって天文18年(1549)に開基、甥にあたる感誉上人(かんよしょうにん)を開山とし、創建された寺院です。大道寺政繁は、北条氏康の家老で川越を治めていました。 |
| 徳川時代には「関東十八檀林」の一つに数えられ葵の紋所が許されました。壇林として幕府の庇護の下、多くの学僧を育てました。檀林とは幕府公認の僧侶養成機関、僧侶大学でした。 |
 |
 |
正面の呑龍堂は大正初期の建築で、呑龍上人の像が安置されており、子育ての呑龍様として親しまれています 。呑竜上人は、感誉上人の孫弟子で、群馬県太田市の大光院を開いています。 |
| 境内には呑龍上人を祀った呑龍堂やその外陣に置かれた「おびんづる様」、墓域には蓮馨尼の供養碑、多門伝八郎重共(おかどでんぱちろう しげとも)の祖父・信清の宝箆印塔の墓碑などがあります。 |
 |
 |
蓮馨寺は明治26年(1893)の川越大火で、鐘楼と水舎を残し、山門及び諸堂すべて焼失してしまいました。この焼け残った鐘楼の梵鐘は元禄8年(1695)に造られたもので、その大きさは約1.5mあり市内では最大です。 |
法善寺
ほうぜんじ
埼玉県川越市幸町2ー14
Tel 049-222-2449
 |
自然山宝林院(じねんさんほうりんいん)法善寺(ほうぜんじ)は、一番街の通りから少し奥に入ったところにあります。天文18年(1549)の古刹で、浄土真宗大谷派、京都東本願寺に属しています。 |
| 境内に入ると、本堂に向かって右側に、柱に屋根をかけた霊屋、四斗樽に腰をかけた袴姿の侍像「虫食い奴(やっこ)の墓」があります。一日も欠かさず酒を飲んでいた大酒飲みのお墓です。その男は、瀬川嘉右衛門(かえもん)といい、松平信綱が川越城主の時代に槍持ちとして仕えていました。 |
 |
 |
嘉右衛門は生前から変わったことを求める者で、晩年にはみずから自分の姿を石に刻み墓を建立し、法善寺に納めました。現在、この墓は二代目になります。まれに見る悪食家で、酒の肴に虫などを食べたことから「虫食い奴」と呼ばれました。 |
成田山川越別院本行院
なりたさんかわごえべついんほんぎょういん
埼玉県川越市久保町9ー2
Tel 049-222-0173
 |
成田山川越別院本行院は成田山新勝寺の別院で真言密教の寺院です。創建は江戸時代末の嘉永6年(1853)です。眼病平癒を祈願し、その願いがかなった石川照温が、廃寺となっていた本行院を成田山新勝寺の別院として再興しました。喜多院の北側に位置し、地元では「お不動様」として親しまれています。 |
| 境内には成田山川越別院の開祖・石川照温の等身大座像が安置されている開山堂や、弘法大師の像が安置してある大師堂、福寿殿、鐘楼堂、出世稲荷などがあります。境内では、月に1度の骨董市やアンチックバザール「蚤の市」が開かれます。 |
 |
喜多院
きたいん
埼玉県川越市小仙波町1−20−1
Tel 049-222-0859
 |
星野山無量寿喜多院は徳川家とゆかりの深い名刹です。五百羅漢やダルマ市で有名で、川越大師とも呼ばれます。天長7年(830)、慈覚大師円仁が無量寿寺というお寺を開いたことからこのお寺は始まります。元久2年(1205)、無量寿寺は兵火に遭い荒廃しました。 |
| 永仁4年(1296)、尊海僧正が慈恵大師を勧請して無量寿寺を再興しました。伏見天皇は関東天台宗の本山としています。仏蔵院(北院)・仏地院(中院)・多聞院(南院)が建てられ、関東における天台宗の中心的存在になりました。 |
 |
 |
寛永10年(1633)中院のあった場所に仙波東照宮が建てられ、中院は200m南方に移動しました。天文6年(1537)には北条氏綱と上杉朝定(ともさだ)の戦火に巻き込まれ焼失してしまいました。 |
| 慶長4年(1599)、天海僧正が無量寿寺の北院の第27世を継承しました。慶長16年(1611)に徳川家康が川越を訪れ接見しています。その翌年、当時の名称であった仏蔵院北院を喜多院と改めました。天海僧正は家康の信任を得て寺勢をふるうようになりました。 |
 |
 |
慶長18年(1613)には2代将軍徳川秀忠の関東天台法度により関東天台総本山と位置づけられ500石の寺領を賜りました。寛永15年(1638)、大火により現存の山門を残し、すべての堂宇は焼失してしまいました。 |
| 3代将軍徳川家光の命により再建が行われました。その際に江戸城紅葉山の別殿を解体移築して、客殿、書院、庫裏に当てました。慈恵堂、多宝塔、慈眼堂、鐘楼門、東照宮、日枝神社なども数年の間に相次いで再建されました。 |
 |
 |
客殿、書院、庫裏は現存する江戸城唯一の遺構であり、国の重要文化財に指定されています。4代将軍徳川家綱は200石を加増しました。750石、寺域48000坪の大寺となり、徳川家に厚く保護され隆盛しました。 |
| 喜多院は川越大師としても知られ、初大師、節分会、桜まつりなどでにぎわいます。毎年1月3日には、恒例のだるま市が行われ、家内安全、商売繁盛、諸願成就を願う人々がだるまを買い求めに訪れます。 |
 |
 |
山門は天海僧正が寛永9年(1632)に建立したものです。寛永15年の川越大火での焼失を免れ、喜多院では最古の建造物です。切妻造り、本瓦葺きの四脚門で、国の重要文化財に指定されています。山門の右側には番所があります。江戸時代の建築で、同種の物としては埼玉県内に残る唯一の遺構です。 |
| 山門 |
| 客殿は、書院、庫裏とあわせ江戸城紅葉山(皇居)の別殿を移築したものです。寛永15年(1638)の大火で焼失した堂宇を再建するため家光が移築させました。上段の間は、3代将軍徳川家光がここで生まれたということから、「徳川家光誕生の間」と呼ばれています。 |
 |
| 客殿・書院 |
 |
客殿は裄行8間、梁間5間の入母屋作りでこけら葺きです。12畳半2室、17畳半2室、10畳2室があります。寛永16年(1639)に建てられた書院には「春日局化粧の間」があります。客殿、書院、庫裏は国の重要文化財に指定されています。 |
| 客殿・書院 |
| 慈恵堂(じえどう)は、前方3間を外陣、後方2間を内陣とする喜多院の本堂で、慈恵大師と慈眼大師が祀られています。建物は寛永16年(1639)に建立されました。桁行9間、梁間6間、入母屋造り、銅板葺き(もとは桟瓦葺き)、向拝付の大きな建物です。県の有形文化財に指定されています。 |
 |
| 慈恵堂 |
 |
慈恵堂に向かって右手に多宝塔があります。寛永16年(1639)に建立されています。もとは山門の北側、日枝神社と白山神社の間にありました。高さ13m、三間、重層の宝形造り、本瓦葺きの多宝塔です。塔の中間には漆喰塗りの円形部分「亀腹」があります。江戸時代初期の多宝塔の特徴をよく残している建造物で、県の有形文化財に指定されています。 |
| 多宝塔 |
| 前方後円墳の墳丘に慈眼堂(じげんどう)があります。慈眼堂は天海僧正を祀ったお堂で、正保2年(1645)、3代将軍家光の命により建立されたといわれています。禅宗様式に和様を折り込んだ造りで、方3間、宝形造り、本瓦葺きです。背面に1間の通り庇(ひさし)付いています。 |
 |
| 慈眼堂 |
 |
堂内中央の須弥(しゅみ)壇に厨子(ずし)があります。寛永20年(1643)に108歳で亡くなる2ヶ月前の姿を写した天海僧正の木像を安置しています。厨子は1間厨子、向唐破風造り、本瓦形板葺いです。慈眼堂は国の重要文化財に指定されています。 |
| 慈眼堂 |
| 慈眼堂の正面石段を下りて、まっすぐ行くと鐘楼門(しょうろうもん)があります。桁行3間、梁間2間、入母屋造り、本瓦葺きで袴腰が付けられています。元禄15年(1702)建立と伝えられています。壁面の東側には龍、西側には鷹の彫刻が、それぞれ二つずつはめ込まれています。国の重要文化財に指定されています。 |
 |
| 鐘楼門 |
五百羅漢
 |
喜多院境内に五百羅漢があります。「日本三大羅漢」の1つに数え上げられています。人間味あふれる様々な表情をした石像は、それぞれどこか身近にいそうな親しみを感じさせます。 |
| 五百羅漢は、川越北田島の志誠(しじょう)の発願により、天明2年(1782)から文政8年(1825)の約50年間にわたり建立されたもので、538体の石仏があります。 |
 |
 |
十大弟子、十六羅漢を含め、五百三十五尊者のほか、中央高座の大仏に釈迦如来、脇侍の文殊・普腎の両菩薩、左右高座の阿弥陀如来、地蔵菩薩などがあります。 |
| 五百羅漢は喜多院境内の一角のおみやげ物やさんから入りますが入場券は庫裏にありますので最初は邸内を見てから入るのが良いかもしれません。 |
 |
 |
今はできませんが深夜こっそりと羅漢さんの頭をなでると、一つだけ必ず温かいものがあり、それは亡くなった親の顔に似ているのだという言い伝えも残っているそうです。 |
仙波東照宮
せんばとうしょうぐう
埼玉県川越市小仙波町1丁目21
Tel 049-224-3431
 |
仙波東照宮は喜多院の南側にあります。元和2年(1616)駿府で徳川家康が没し、その遺骸を久能山から日光山へ移す途中、天海僧正によって喜多院で4日間の法要が営まれました。その後、日光山へと遺骸は運ばれ、東照宮に祭られました。 |
| 天海僧正は寛永10年(1633)年、喜多院の境内に東照宮(仙波東照宮)を建立しました。この場所は中院の仏地院が建てられていた場所でした。 |
 |
 |
寛永15年(1638)川越城下は寛永の大火に見舞われます。喜多院は山門を残し、ほぼ全焼。東照宮も焼け落ちました。3代将軍徳川家光によって川越藩主で老中の堀田正盛が造営奉行に命ぜられ、幕府によって、寛永17年(1640)に再建されました。 |
| この再建された社殿が、現在の仙波東照宮です。日光・久能山とともに三大東照宮の一つに数え上げられています。江戸時代を通じ社殿や神器など、すべて江戸幕府直営で行われたそうです。 |
 |
 |
本殿は三間社流造り、銅瓦葺、極彩色です。拝殿には、正面に後水尾天皇の筆となる東照大権現の勅額が懸けてあります。拝殿にある三十六歌仙絵額は岩佐又兵衛筆で知られ国宝です。本殿、唐門、拝殿及び幣殿、随身門、石鳥居、瑞垣が国の重要文化財に指定されています。 |
中院
なかいん
埼玉県川越市小仙波町5丁目15ー1
Tel 049-222-2170
 |
中院は天台宗別格本山で閑静な佇まいが特徴のお寺です。中院の境内の桜は有名で、本堂前しだれ桜は特に趣があるようです。かつて中院は星野山無量寿寺(せいやさんむりょうじゅじ)仏地院(ぶつちいん)と称し、天長7年(830)に慈覚大師によって創建されました。 |
| 元久2年(1205)、無量寿寺は兵火に遭い荒廃しました。 永仁4年(1296)、尊海僧正が慈恵大師を勧請して無量寿寺を再興しました。仏蔵院(北院)、仏地院、多聞院(南院)が建てられ、関東における天台宗の中心的存在になりました。 |
 |
 |
北院は天海僧正の時に喜多院となり、南院は廃寺になってしまいました。当初の中院は喜多院の隣にある仙波東照宮の場所にありましたが、寛永10年(1633)の東照宮建造の折、200m南方の現在の場所に移りました。 |
| 天海僧正が喜多院の住職に着く前までは、喜多院よりも中院の方が寺勢が強く関東天台宗の本山として栄えていたそうです。 |
 |
 |
静かなたたずまいをみせる境内には、川越城主秋元氏の家老であった太陽寺一族の墓、島崎藤村の義母・加藤みきの墓、成田山川越別院の開祖・石川照温上人の墓などがあります。 |
| 中院は島崎藤村ゆかりの寺院としても知られ、境内には藤村ゆかりの茶室「不染亭」が平成4年(1992)に移築されています。市指定文化財の「不染亭」の前には、藤村の書による「不染之碑」が建てられています。不染の名前の由来は、藤村の義母、加藤みきが茶道の師匠として「不染」と称したことから名付けられたそうです。 |
 |
| 不染之碑 |
 |
中院は狭山茶・河越茶の発祥の地としても知られ、慈覚大師円仁が無量寿寺建立の際、比叡山より茶の実を携え、境内に薬用として栽培したのが始まりとされています。 境内にはその旨を記した石碑が建てられています。
30年ほど前までは境内にも茶畑があり、茶摘みをしていたそうです。 |
| 狭山茶発祥の地 |
日枝神社
ひえじんじゃ
埼玉県川越市小仙波町1丁目4ー1
Tel 049-222-1396
 |
慈覚大師円仁が喜多院の前身である無量寿寺を天長7年(830)に創建しました。日枝神社はその鎮守として、貞観2年(860)に比叡山坂本の日枝山王社を勧請したといわれています。東京赤坂の日枝神社(旧官幣大社)は、文明10年(1478)、太田道灌が江戸城築城の際に、この川越日枝神社から分祀したものです。 |
| 小さく質素な本殿は朱塗りの三間社流造り、銅板葺きで国の重要文化財に指定されています。建築時期は寛永15年(1636)の火災後の再建か、それ以前の建築とみられます。建築の一部に古式造りが認められ室町時代末期頃とも考えられています。 |
 |
浮島稲荷神社
うきしまいなりじんじゃ
埼玉県川越市久保町17
 |
地元の人々から「うきしま様」と呼ばれ広く親しまれている神社です。以前は「七つ釜」と呼ばれ清水の湧き出る穴が七つもある葦(あし)の生い茂った沼地であったといわれています。遠くから神社を眺めると鳥のように浮かんで見えたことから浮島神社と呼ばれるようになったといいます。 |
| かつては末広稲荷とも呼ばれ、安産の神として麻を奉納する風習があったそうです。慈覚大師が喜多院の前身である無量寿寺を天長7年(830)に創建したときに、ここに移したとか、太田道灌の父大田道真が川越城を築城した際に城の守護神としてこの地に祀ったともいい伝えられています。 |
 |
三芳野神社
みよしのじんじゃ
埼玉県川越市郭町2ー25ー11
Tel 049-222-5556
 |
三芳野神社は、大同2年(807)に建立されたと伝わります。川越城の築城当初から城内鎮守の宮として歴代城主の崇敬をあつめてきました。三芳野とは川越の昔の呼び名で「神聖な美しい広い土地」という意味だそうです。 |
| 三芳野神社は、川越城の鎮守として寛永元年(1624)、時の城主酒井忠勝によって再建されたといわれています。 三芳野神社の優美な権現造りの社殿は、名前の由来となった「三芳野天神縁起絵巻」とともに市の指定文化財になっています。 |
 |
 |
この天神様は、童謡「とおりゃんせ」発祥の地といわれています。川越城内にあったため、一般の人の参詣はなかなか難しく、その様子が歌われていると伝えられています。 |
| 三芳野神社の社殿は三間社の本殿に幣殿及び拝殿を付した複合社殿、銅板葺です。現存する社殿は川越城主・酒井忠勝が寛永元年(1624)に再建したものです。その後、明暦2年(1656)松平信綱によって修復されました。また、平成元年(1989)から平成4年(1992)にかけて大修理が行われました。 |
 |
| 三芳野神社社殿 |
氷川神社
ひかわじんじゃ
埼玉県川越市宮下町2丁目11ー3
Tel 049-222-8417
 |
氷川神社は古墳文化が伝えられた6世紀の欽明天皇の時代に、武蔵の一宮である大宮氷川神社を分祠したことから始まったといわれています。関東三大まつりで国の重要無形民俗文化財である川越祭り(川越氷川祭)は氷川神社の例大祭でです。 |
| 川越城を築城したとされる太田道真・道灌父子は、築城以来氷川神社を篤く崇敬し、道真は「老いらくの身をつみてこそ武蔵野の草にいつまで残る白雪」と和歌を献納し、道灌は境内に矢竹を植樹しています。以来、川越の総鎮守とされ、「お氷川様」と呼ばれ崇敬され親しまれてきました。 |
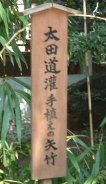 |
 |
江戸時代には、歴代川越城主の篤い崇敬を受けました。慶安元年(1648)には、城主松平伊豆守信綱が氷川神社に神輿・獅子頭等を寄進し、神幸祭が始まり、それが「川越まつり」に引き継がれました。 |
| 夫婦の神様を祀っていることから「縁結びの神」として信仰され、毎年多くのカップルが結婚式を挙げています。素盞鳴尊(すさのおのみこと)は伝家の宝刀を抜き、八岐大蛇の首をはねて、奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)を助け、結婚しました。この二人が祭神に入っているのです。 |
 |
 |
氷川神社では、昔より境内の小石を持ち帰り大切にすると、良縁に恵まれるという言い伝えがあります。 お祓いした縁結び玉は早朝に行かないとすぐに無くなってしまうそうです。 |
| 埼玉県指定有形文化財の本殿は入母屋造り、銅板葺きで向拝付です。寛永2年(1849)川越城主・松平斉典の寄進により建立されました。本殿の全面を覆う「江戸彫り」と呼ばれる精巧な彫刻は、江戸化政年間の名彫り師・嶋村源蔵の手によるものです。川越まつりの山車の人形を主題にした彫刻がほどこされています。 |
 |
| 氷川神社本殿 |
 |
境内の入り口に大きくそびえたつ大鳥居は、木製の鳥居としては日本一の大きさです。大鳥居の社号は勝海舟の筆によるもので、高さは約15メートルあります。平成の大典奉祝行事として建立されました。
|
| 氷川神社鳥居 |
| 柿本人麿神社は、戦国時代に丹波の綾部から近江を経て移住した綾部家が一族の祖・柿本人麿を奉斎したものです。毎年、柿本人麿祭が行われ、多くの人々が訪れます。 |
 |
| 末社・柿本人麿神社 |
川越城本丸御殿
かわごえじょうほんまるごてん
埼玉県川越市郭町2丁目13ー1
Tel 049-222-5399
 |
川越城は関東七名城の一つで、江戸時代には17万石川越藩の藩庁が置かれていました。川越城の築城は、室町時代上杉持朝の命により、太田道真・道潅父子によって行われました。当時建てられた城は、小さい砦のようなものだったと考えられています。 |
| 徳川家康が関東に入ると、初代川越藩主として三河以来の家臣だった酒井重忠が川越城主になり、徐々に近代城郭の形態を整えていきました。川越城には天守閣はなく、宇都宮城・清明台櫓と同様に城の中で一番高い所にあった富士見櫓が天守閣の代わりをしていたそうです。 |
 |
 |
家康は鷹狩りの際、天海僧正の住持する喜多院のある川越をたびたび訪れていたようです。藩政時代には、松平信綱や柳沢吉保など幕府の要職についた歴代藩主が多く、特に江戸時代中期までは「老中の居城」でした。 |
| また、川越城は、国立歴史民族博物館蔵の江戸図屏風にも描かれるなど、江戸に最も近い城であり、北の守りとして重要な役割を果たしていました。嘉永元年(1848)に、松平斉典によって建てられた本丸御殿の大広間と玄関が現存しています。 |
 |
 |
日本では川越城の他には高知城のみで、貴重な遺構です。入母屋造りで、豪壮な大唐破風と霧除けのついた間口19間・奥行5間の建物で大玄関と車寄せがあります。36畳の大広間は、板間で玄関と区切られ、さおべり天井で奥行3間の座敷には9尺の廊下が四方を囲っています。建坪は165坪もあります。 |
蔵造りの町並み
くらづくりのまちなみ
埼玉県川越市幸町・仲町・元町
Tel 049-224-5940
 |
大江戸(東京)に対し小江戸と呼ばれる川越、その市街地に蔵造りの建物が並ぶ一角があります。明治26年(1893)川越大火が起こりました。川越商人達は、焼け残ったいくつかの土蔵を目の当たりにして、当時の耐火建築のレンガ造りではなく、江戸の町屋形式の蔵造りで再建しました。 |
| 大火から3年あまりで復興を果たし、川越に蔵造りの街並みが出現しました。川越の蔵造りは、箱棟、大きな鬼瓦、重厚な観音扉が特徴で、塀や地下蔵にはレンガが用いられています。蔵造りは「倉」に用いるのが普通ですが、川越では一般の町家で家全体を土蔵造りにしています。 |
 |
 |
関東大震災により東京の蔵造りは姿を消しますが、江戸の景観を今に残す川越の街並みはとても貴重です。一番街の通りに面して建ち並ぶ蔵造りの町並みは商いと、生活が一緒になって江戸情緒を見せてくれます。 |
| 江戸の面影をとどめる蔵造りの町並みは、平成11年(1999)に文化庁の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定され、平成19年(2007)には「美しい日本の歴史的風土100選」に選定されました。 |
 |
 |
元町にある大沢家住宅(おおさわけじゅうたく)は、呉服太物を商っていた川越の豪商・西村半右衛門が寛政4年(1792)に建てた店舗蔵です。屋号は小松屋で、現在は川越の民芸品を販売しています。川越にある蔵造りの中では最も古く、国の重要文化財に指定されています。 |
| 大沢家住宅 |
| 享保5年(1720)に幕府の奨励で、江戸の町に耐火建築として蔵造り商家が立ち並びました。江戸との取り引きで活気のあった川越の商家もこれにならい、蔵造りが建つようになりました。明治26年(1893年)の川越大火のときにも、この蔵造りの家が焼け残ったことから、この辺り一帯が蔵造りの店になりました。 |
 |
| 大沢家住宅 |
 |
大沢家住宅は間口6間、奥行4.5間、桟瓦葺きの屋根を持つ切妻造り平入りです。壁の厚さは30cmもあります。中は縦と横に5cm丸竹を使い、あけびのつるで結束してあるそうです。江戸時代のシンプルな町屋形式の建築で、川越の町家では大きい部類に入ります。 |
| 大沢家住宅 |
| 埼玉りそな銀行川越支店(旧第八十五銀行)は青緑色のドームが目立つ様式建築です。大正7年(1918)に第八十五銀行の本店として建てられました。鉄骨鉄筋コンクリート造り、3階建て、搭屋・金庫室付き。高さ25m、面積291平方m。ネオ・ルネッサンス、サラセン風デザインで、平成8年(1996)国の登録有形文化財に指定されています。 |
 |
| 埼玉りそな銀行川越支店 |
時の鐘
ときのかね
埼玉県川越市幸町15−2
Tel 049-222-5556
 |
時の鐘は情緒あふれる蔵造りの町並みにひときわ高くそびえる時計台です。蔵造りの町並み「一番街」と同様に、城下の頃の面影を残す建造物で、江戸時代初頭から城下の町に時を告げ、庶民に親しまれてきた時計台です。 |
| 時の鐘は寛永年間(1624-44)、川越城主・酒井忠勝が城下に建てたのが最初です。以来、度重なる火災で鐘楼や銅鐘が焼失しましたが建て替えられてきました。現在の時の鐘は4代目に当たり、明治26年(1893)の川越大火の翌年に建てられたものです。町の3分の1が焼失し、まだ自分の店も再建していない川越の商人たちが時計台をいち早く建て直したのでした。 |
 |
 |
時の鐘は木造の3層のやぐらで高さは約16mあります。川越のシンボルとして川越を見守ってきた時の鐘は、今も1日4回、午前6時、正午、午後3時、午後6時に時を知らせています。近所の人は、時の鐘とは呼ばずに、鐘撞堂と呼んでいるそうです。 |
| 江戸幕府が江戸市中に鐘を鳴らして時を告げていたことにならい、当時の川越藩主・酒井忠勝が時の鐘を川越城下で鳴らし始めたのです。時の鐘は平成8年(1996)に「残したい日本の音風景百選」に選ばれています。 |
 |
川越市蔵造り資料館
かわごえしくらづくりしりょうかん
埼玉県川越市幸町7ー9
Tel 049-225-4287
 |
川越市蔵造り資料館は明治26年(1893)の川越大火直後に建てられた旧煙草卸商「万文」の店蔵をそのまま利用した資料館です。昭和47年(1972)、「万文」の建物が売却され取り壊しの動きが出たとき、保存を求める市民運動が起こりました。 |
| 川越市の開発公社が「万文」の土地・建物を取得して再生し、昭和52年(1977)「川越市蔵造り資料館」をオープンさせました。「店蔵」と「袖蔵」があり、資料館は「一番蔵」から「三番蔵」の3つから構成されています。実際に蔵造りの中に入って、内部の構造や敷地内の配置などを見ることができます。 |
 |
 |
奥の蔵には川越に蔵造り商家の町並みが生まれるきっかけになった川越大火関連の資料や、この蔵造りを所有していた煙草卸商に関する資料などが展示されています。また蔵造りの防火機能だけでなく川越商人がふんだんに金を次ぎ込んだ装飾も一見の価値があります。 |
| 厚い土壁と豪壮な屋根瓦や鬼瓦、重厚な観音扉などは迫力があり建築学上も貴重な遺構です。蔵の2階に上がると、格子窓越しに小江戸川越のシンボル「時の鐘」がすぐ目の前に見えます。 |
 |
山崎美術館
やまざきびじゅつかん
埼玉県川越市仲町4ー13
Tel 049-224-7114
 |
山崎美術館は、古い蔵造りの中にある美術館です。小江戸川越の風情にふさわしい芸術空間となっています。和菓子の老舗「亀屋」の一角に立つ蔵を利用し、代々山崎家に伝わる美術品・工芸品、古文書などのコレクションを展示しています。 |
| 山崎美術館は、亀屋中興の祖・4代目山崎嘉七(豊)の生誕150年を記念して、昭和57年(1982)の文化の日にオープンしました。美術品は日本画の革新者・橋本雅邦画伯の作品を中心に公開展示をしています。 |
 |
 |
橋本雅邦画伯は、川越藩松平周防守の抱え絵師、橋本晴園の子として生まれました。東京美術学校創立時に日本画の主任教授として迎えられ、横山大観、下村観山、菱田春草らを指導しました。日本美術院を興し、明治時代における日本画壇の最長老として美術界の革新に活躍しました。 |
| 第八十五銀行の頭取にもなった4代目山崎嘉七(豊)は橋本雅邦と交流があり、多くの作品を収集することになったようです。この美術館は茶菓のサービスがあります。作品の鑑賞が終わったら、「亀屋」のお菓子も味わえます。 |
 |
菓子屋横丁
かしやよこちょう
埼玉県川越市元町2ー7
Tel 049-222-5556
 |
菓子屋横丁では、明治の初めから菓子を製造していました。関東大震災で被害を受けた東京に代わって駄菓子を製造供給するようになり、昭和初期には70軒ほど軒を連ねていたようです。現在は10数軒の店舗が連なり、横丁気分が満喫できます。 |
| 色とりどりの手作りアメや素朴な生菓子、そして下町風の駄菓子はいつまでも愛され、菓子屋横丁は今日もにぎわいをみせています。平成13年(2001)度には、横丁が醸し出す雰囲気と下町風の菓子の懐かしいかおりが漂うということで、環境省の実施した「かおり風景100選」に選ばれています。 |
 |
川越市立博物館
かわごえしりつはくぶつかん
埼玉県川越市郭町2ー30ー1
Tel 049-222-5399
 |
川越市立博物館は、川越城二の丸跡に建設された川越市立の博物館です。蔵造りをイメージした切り妻の瓦屋根にしっくい風の白壁の建物です。博物館は平成2年(1990)3月1日にオープンしました。 |
| 開館以来、毎年およそ17万人が訪れています。川越藩の城下町として発展してきた川越に関する資料の収集・保存・調査研究・公開を目的として建設されました。 |
 |
 |
常設展示室では、最も川越の特徴がよく分かる近世に重点が置かれ、ビジュアル的要素を多く盛り込み、川越の歴史を楽しみながら理解できます。江戸を支えた城下町川越の特色が身近に感じられます。 |
| 川越の歴史や文化などの資料や復元模型が多数展示されており、昔の川越を色々な角度で知ることが出来ます。また蔵造りの町並みについてのビデオなども放映されています。 |
 |
 |
川越芋の歴史や芋せんべいの製作方法、道具などを紹介したコーナーや、蔵造り工程の模型、縄文人が使った舟などもあります。 |
西武園ゆうえんち
せいぶえんゆうえんち
埼玉県所沢市大字山口2964
Tel 04-2922-1371
 |
西武園ゆうえんちは、昭和25年(1950)にオープンした遊園地で、西武グループが運営しています。ゲート前は、埼玉県と東京都の境になっています。春は300本の桜、秋には園内や多摩湖の紅葉が楽しめます。 |
| 夏には波のプール、流れるプール、6コースのチューブ専用ウォータースライダー、冬はビッグなアイススケートリンクが楽しめ、ニジマス釣りなどもできます。 |
 |
 |
武蔵野の自然が満喫できるジャイロタワーや大観覧車などの眺望マシンに、ループ・スクリューコースターやルーピングスターシップといったスリルライドなど、アトラクションがたくさん揃っています。回転ボートやバイキング、空飛ぶじゅうたん、ウェーブスウィンガー、メリーゴーランド、オクトパス、ジェットファイター、回転馬車、、クラシックカー、ハングライダーなどなど一日ゆっくり遊べます。 |
狭山不動尊
さやまふどうそん
埼玉県所沢市上山口2214
Tel 042-928-0020
 |
狭山不動尊は、正式には狭山山不動寺といい、天台宗別格本山のお寺です。本尊は不動明王です。埼玉西武ライオンズが必勝祈願を行う寺です。開山は、昭和50年(1975)とまだ最近ですが境内には重要文化財などに指定されている古い建造物がたくさんあります。 |
| 山門は徳川2代将軍秀忠の台徳院霊廟の門だった勅額門です。御成門、丁子門も含め国の重要文化財です。本堂は京都東本願寺から移築した七間堂、長州藩主毛利家の江戸屋敷に建てられていた不動寺総門、大阪府高槻市の畑山神社から移築された多宝塔などがあります。 |
 |
 |
所沢には以前、世界の建物を集めたユネスコ村という施設がありました。この付近は、日本の重要文化財が集められていた場所でした。それらを守るため狭山不動尊が開山されたそうです。 |
| 西武グループ創業者、故堤康次郎は、空襲で焼けた増上寺の一部を買い取り、東京プリンスホテルを建てました。その際、増上寺にあった勅額門、御成門、丁子門をユネスコ村に移築したのです。 |
 |
 |
勅額門は 増上寺にあった徳川秀忠 (台徳院) の廟に建立されていたものです。寛永9年(1632)孝養報恩の志をのべたいと3代将軍徳川家光が建てたものです。 |
| 勅額門 |
| 江戸時代初期の四脚門で切妻造り、銅板葺きです。「台徳院」と書かれた額は、後水尾天皇の筆によるものです。そのため勅願門という名前になっています。旧台徳院霊廟勅額門として国の重要文化財に指定されています。 |
 |
| 勅額門 |
 |
御成門は勅額門を抜けて階段を上がった先にあります。勅額門と同様に増上寺にあった徳川秀忠 (台徳院) の廟に建立されていたものです。飛天の彫刻や絵画が多く描かれていて朝鮮渡来の天人門といわれています。 |
| 御成門 |
| 寛永9年(1632)3代将軍徳川家光が建てたものです。格天井の中央に丸い鏡天井が設けられています。非常にめずらしい特徴です。旧台徳院霊廟御成門として国の重要文化財に指定されています。 |
 |
| 御成門 |
 |
丁子門も国の重要文化財に指定されています。2代将軍秀忠の正室で、3代将軍家光の生母である達子(於江与の方・崇源院)の廟所である崇源院霊牌所の通用門です。増上寺にあったもので、寛永9年(1632)に家光が建立したものです。 |
| 丁子門 |
| 不動門総門は元長州藩主毛利家の江戸屋敷に建てられた門です。素材はすべて「けやき」で造られています。直線が巧みに組み合わされていて、武家屋敷の門にふさわしい威風堂々とした門です。 |
 |
| 不動門総門 |
 |
この第1多宝塔は弘治元年(1555)大阪府高槻市梶原にある畠山神社に建てられていたものです。美濃国の林丹波守が建立したと伝えられています。慶長2年(1607)の墨書があり桃山時代の建物です。埼玉県の有形文化財に指定されています。 |
| 第1多宝塔 |
| 弁天堂は滋賀県彦根市古沢町の清涼寺にあった経蔵でした。井伊直孝の息女が直孝の追善菩提のために建立したものです。万治2年(1659)から元禄6年(1693)の間に建てられてようです。一重、本瓦葺きの六角円堂で昭和23年(1948)に移築され、弁天堂になっています。 |
 |
| 弁天堂 |
 |
羅漢堂の周囲には、青銅製の灯籠が、びっしりと整列しています。増上寺の廟所に大名家が寄進したものです。羅漢堂は井上馨邸から移築したものです。奈良の二月堂の経堂を模倣して明治28年(1895)建てられたものです。 |
| 羅漢堂 |
| 桜井門は奈良県十津川の桜井寺の山門として建立されました。桜井寺は幕末天誅組の本陣として利用された歴史を持っています。千鳥破風の四脚門で入母屋造り、本瓦葺きです。 |
 |
| 桜井門 |
 |
第2多宝塔は兵庫県東條町天神にある椅鹿寺にあったものです。永享7年(1435)播磨国守護赤松満男教康が建立したそうです。3間の多宝塔で本瓦葺きです。細部にわたって室町時代中期の様式をよく伝えています。 |
| 第2多宝塔 |
| 大黒堂は柿本人麻呂ゆかりの地、奈良極楽寺境内に建立された人麻呂の歌塚堂だそうです。また大黒天は寛永寺山内の見明院に奉安されていた尊天だそうです。 |
 |
| 大黒堂 |
山口千手観音
やまぐちせんじゅかんのん
埼玉県所沢市大字上山口2203
Tel 04-2922-4258
 |
山口千手観音は吾庵山金乗院(こんじょういん)といい、寺号は放光寺で行基が開いた真言宗豊山派のお寺です。4体の千手観音像がありますが、本尊の千手観音は秘仏で公開されていません。 |
| 古くから観音信仰の霊場として知られ、弘仁年間(810-824)に奈良時代の僧行基によって観音像が彫られ観音堂が開かれたと伝えられています。この寺はその別当寺であったそうです。 |
 |
 |
元弘3年(1333)新田義貞が鎌倉攻めの際、ここに立ち寄り戦勝の祈願をしています。その時の祈願文が伝えられています。江戸時代には御朱印十石を寄進され、仁王門、本堂、鐘楼、開山堂など堂舎の整った名刹として隆盛をきわめました。 |
| 本堂には藤原様式を伝える市指定文化財の千手観音や他3体の千手観音像、絵馬たばこ屋の図、六歌仙図、銅鐘(市指定文化財)などがあります。 |
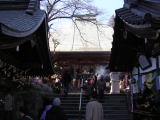 |
 |
境内には平成11年(1999)に建てられた目新しい八角五重塔があります。塔内には、千体の観音像と、太平洋戦争の折に供出された十八尺の唐金製聖観音像の頭部を奉安しています。地下に、元禄年間(1688-1704)の西国巡礼と、近年に作られた四国遍路の各本尊を祀っています。 |
小野家住宅
おのけじゅうたく
埼玉県所沢市林2丁目426−1
 |
小野家住宅は18世紀初頭に建造された入母屋造り、茅葺きの民家です。桁行14m、梁間6.5m、南北両面及び東面に日よけや雨よけ用のひさしが付いている直屋です。 |
| 柱や梁には、野生のクリやマツの木が使われています。かつてこの地は林村と呼ばれ、林木が多くあった場所だったようです。小野家住宅は武蔵野の開拓農家の面影を残す建物の代表例として、国の重要文化財に指定されています。 |
 |
高倉寺
こうそうじ
埼玉県入間市高倉3丁目3ー4
Tel 04-2962-2912
 |
高倉観音とも呼ばれる光昌山高倉寺は、入間川や飯能地方を見渡す高台にある曹洞宗のお寺です。鍵山(かぎやま)から高倉に向かう坂を登る途中に高倉寺があります。 |
| 境内には、室町時代初期に建立されたと推定される観音堂があります。方3間で、入母屋造りのこの観音堂は、根の先が優雅に跳ね上がる禅宗建築様式です。関東地方における、この様式の代表的な建造物です。 |
 |
 |
観音堂は、飯能市白子の長念寺の観音堂でしたが、延享元年(1744)高倉寺が譲り受けて移築したそうです。1重、桁行3間、梁間3間、入母屋造り、茅葺様銅板葺きの建物です。昭和24年(1949)高倉寺観音堂として国の重要文化財に指定されています。 |
| 観音堂の平面形態は方3間で、周囲に縁を持っています。正面の3間と側面の手前1間を桟唐戸として、内法貫上には弓形の欄間を設けて、側面の中央1間に花頭窓を配しています。 |
 |
出雲伊波比神社
いずもいわいじんじゃ
埼玉県入間郡毛呂山町(もろやままち)岩井西5丁目17ー1
Tel 049-294-5317
 |
出雲伊波比神社は古式ゆかしい「流鏑馬(やぶさめ)」で有名な神社です。毛呂山町のほぼ中央、小高い独立丘陵である臥龍山の上に位置しています。 |
| 出雲伊波比神社は景行天皇53年(123)に日本武尊(やまとたけるみこと)が、東国を平定した際に、家臣の武日命(たけひのみこと)に命じて社殿を造営させたのが始まりです。成務天皇の時代に、出雲の神・天穂日命を祀り、出雲伊波比神としたといわています。 |
 |
 |
平安時代の延喜式神明帳では武蔵国入間郡五座の筆頭神社にあげられています。源頼義、義家父子は奥州平定を祈願し、凱旋した康平6年(1063)に八幡社を建立しています。流鏑馬を奉納し、鎌倉時代以降、武士の信仰も集め源頼朝が畠山重忠に造営を命じています。 |
| 大永7年(1527)社殿が焼失し、翌年に当地を治めていた毛呂三河守藤原顕繁によって再建されています。江戸時代には「飛来大明神」あるいは「毛呂明神」などと呼ばれて地域の信仰を集めていました。 |
 |
 |
江戸時代、3代将軍徳川家光は社殿を修理させ、徳川幕府の庇護も厚かったそうです。中世から江戸期にかけて飛来明神(毛呂明神)と称していたのを明治維新に入ってから古来の出雲伊波比神社に戻しました。 |
| 11月3日の例祭には、町内の家の長男(小・中学生)が乗り子を務める流鏑馬(やぶさめ)神事があり、一の馬・二の馬・三の馬に別れ、白(源氏)・紫(藤原氏)・赤(平氏)に色分けして奉納されます。起源は康平6年(1063)に奥州平定をした源頼義、義家父子が凱旋の際に奉納した事によるといわれています。 |
 |
 |
現在の本殿は一間社流造り、桧皮葺きで、大永8年(1528)毛呂三河守藤原顕繁が再建したものです。埼玉県内では最古の神社建築として、棟札2面と併せて、国の重要文化財に指定されています。 |
| 出雲伊波比神社本殿 |
高麗神社
こまじんじゃ
埼玉県日高市大字新堀833
Tel 042-989-1403
 |
高麗神社は朝鮮半島で栄えた高句麗と縁が深く、高句麗の王で高麗郡の郡司であった高麗若光(じゃっこう)を祀っています。俳優ペ・ヨンジュンが高句麗の王を演じる韓国ドラマ「太王四神記(たいおうしじんき)」のヒットでお参りする人が増えたそうです。 |
| 飛鳥時代の668年、朝鮮半島北部から旧満州・中国東北部まで広く支配していた高句麗が唐と新羅の連合軍に破れ滅亡しました。日本に亡命した高麗人1799人は霊亀2年(716)武蔵国に新たにつくられたここ高麗郡に集められたことが続日本紀に記されているそうです。 |
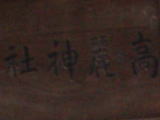 |
 |
祭神の高麗若光は666年に外交使節として来日していたそうです。高麗神社の神主は代々その子孫が務めています。神仏習合の時代、高麗家は修験者として別当を勤めていました。かつては高麗山の山頂に高麗権現社という上宮があり、右の峰に白山権現を、左の峰に毘沙門天を勧請して「高麗三社権現」と称したそうです。 |
| 古来より武門の信仰が篤く、鎌倉期には将軍源頼朝が正室北条政子の安産祈願をして、戦国時代には後北条氏がわずかな領地を寄進したという文献があるそうです。天正19年(1591)には徳川家康より朱印地100石を与えられています。 |
 |
 |
高麗大宮大明神、大宮大明神、白髭大明神と称されていた社号は、明治以降は高麗神社と称されるようになりました。
境内隣接地には江戸時代に建てられた国指定重要文化財の高麗家住宅があります。 |
| 高麗神社は、「出世明神」と呼ばれ政財界、各界著名人が大勢参拝しています。濱口雄幸、若槻禮次郎、斎藤実、小磯国昭、幣原喜重郎、鳩山一郎らが参拝後に総理大臣となったことから人気がてたそうです。 |
 |
高麗家住宅
こまけじゅうたく
埼玉県日高市大字新堀850
Tel 042-989-1403
 |
高麗家住宅は、代々高麗神社の神職を勤めてきた高麗家の住宅です。入母屋造り、茅葺き屋根で、山を背に、東を正面として建てられています。江戸時代初期の重要民家として昭和46年(1971)国の重要文化財に指定されました。 |
| 飛鳥時代の668年、朝鮮半島北部から旧満州・中国東北部まで広く支配していた高句麗が唐と新羅の連合軍に破れ滅亡しました。霊亀2年(716)亡命した高麗人は武蔵国に新たにつくられたここ高麗郡に集められ高麗神社が創建されました。 |
 |
 |
高麗神社には高句麗の王で高麗郡の郡司であった高麗若光(じゃっこう)が祀られ、その子孫が代々の神職を勤めてきました。高麗家住宅の建築年代は慶長年間(1596-1614)と伝えられていますが、明確な資料はありません。構造手法から17世紀中頃ではないかと考えられています。 |
| 間口14.292m(約7間半)、奥行き9.529m(約5間)、総面積136.188m(約37.5坪)で屋根は入母屋造り茅葺きです。間取りは5つの部屋と比較的狭い土間があります。広間には長押を打ち押板を構え前面5.717m(約3間)には格子窓が付けてあります。 |
 |
 |
大黒柱(棟持柱)がなく、細い柱で梁を支えているのが特徴で、桁と柱には杉、梁にはケヤキ・松が用いられています。手斧(ちょうな)や槍鉋(やりがんな)が使用され、全面的に丸みを帯びた仕上げになっています。
|
聖天院(勝楽寺)
しょうでんいん(しょうらくじ)
埼玉県日高市大字新堀990ー1
Tel 042-989-3425
 |
高麗山聖天院勝楽寺は真言宗智山派のお寺です。高麗王でありここ高麗郡の郡司であった若光(じゃっこう)の没後、侍念僧勝楽によって、天平勝宝3年(751)に創建されました。若光の三男聖雲と孫の弘仁が勝楽の遺志を継ぎ、若光の守護仏聖天像(歓喜天)を本尊としました。 |
| 朝鮮半島北部から旧満州・中国東北部まで広く支配していた高句麗が唐と新羅の連合軍に破れ滅亡しました。日本に亡命した高麗人1799人は霊亀2年(716)武蔵国に新たにつくられた高麗郡に集められました。
若光はここ高麗郡の長として、広野を開き産業を興し民生を安定させた人物でした。 |
 |
 |
その後、僧秀海が中興し、開山以来の法相宗を真言宗に改め、天正8年(1580)に本尊を不動明王にし、現在まで継承されています。江戸時代には54ヶ寺の末寺を擁し、15石の朱印状を拝領しました。 |
| 朝鮮様式を示す高麗王若光の墓や、国の重要文化財に指定された銅鐘があります。銅鐘は総高81.2cm、口径45cmです。信阿弥、平定澄が、鎌倉各地に名鐘を残した物部季重に造らせて、文応2年(1261)に勝楽寺(聖天院)に奉納したものです。上帯に雲、下帯に唐草文を繊細に鋳出し、全体の姿も優美です。 |
 |
長瀞渓谷
ながとろけいこく
埼玉県秩父郡長瀞町
Tel 0494-66-0950 長瀞ライン下り
 |
長瀞渓谷は「荒川」上流部にある渓谷です。日本でも有数の川下りのメッカです。国指定名勝天然記念物の岩畳や渓谷美を眺めながらのライン下りも人気です。春にはソメイヨシノが咲き誇ります。 |
| 長瀞駅から岩畳までの沿道は土産物屋や長瀞名物・鮎料理が食べられる店など食事処も軒を連ね、観光地風情を演出しています。 |
 |
 |
荒川沿いに約500m岩石群が続いています。岩の層がまるで畳を敷きつめたように見えることから岩畳と呼ばれています。 |
| 岩畳は三波川変成帯と呼ばれる変成岩帯が地表に露出しているところです。なめらかな壁面は、南北方向にのびる垂直の割れ目(節理や断層)にそって、岩がはがれ落ちて形成されたといわれています。 |
 |
 |
はるか昔に堆積した泥や砂が、川の浸食を受けて現在の特異な造形になっています。岩畳に腰掛けながら、水の流れと対岸の赤壁の紅葉を楽しむことができます。 |
| またこの岩畳のある長瀞は地質学的にも大変貴重な土地であることから、日本地質学発祥の地ともいわれています。 |
 |
 |
地下深くで高い圧力をかけられてできた結晶片岩が、長い年月をかけて隆起、それがさらに河岸の浸食によりつくられたものがこのダイナミックな景観です。 |
| 有名なライン下りは蛇行する荒川の豪快な流れを堪能できます。長瀞の自然が創りあげた芸術品ともいえる景観を川の中から眺められます。 |
 |
 |
風布川上流からこんこんと湧き出る名水「日本水」は日本名水百選に選ばれています。 |
| 県立長瀞玉淀自然公園の中にある長瀞は全長約6kmで、大正13年(1924)、国の名勝・天然記念物に指定されています。 |
 |
秩父神社
ちちぶじんじゃ
埼玉県秩父市番場町1−3
Tel 0494-22-0262
 |
秩父神社は三峯(みつみね)神社、宝登山(ほどさん)神社と並んで秩父三社の一つとされ、古くから秩父地方の総社として崇敬を集めてきました。秩父神社は、市街地のほぼ中央にある柞(ははそ)の森に鎮座しています。創建は崇神天皇の時代、知々夫彦命(ちちぶひこのみこと)が先祖である八意思金命(やごころおもいかねのみこと)を祀ったのが、始まりとされています。 |
| 天慶年間(938 - 947)、常陸大掾・鎮守府将軍平国香と平将門とが戦いました。上野国染谷川の合戦で、国香に加勢した村岡五郎平良文は、妙見菩薩の加護を得て将門を打ち負かすことができたそうです。 |
 |
 |
後に秩父に居を構えたとき、平良文は妙見菩薩を秩父神社の北東に勧進して祀りました。そして妙見信仰はこの地に根付きました。秩父神社は「妙見宮」、「妙見社」と称されるようになり関東武士団の源流・秩父平氏によっても信仰されました。 |
| 永禄12年(1569)武田信玄の秩父侵攻によって、妙見宮や周りの寺社は焼き払われてしまいました。天正元年(1573)に再建を図りましたが実現できませんでした。 |
 |
 |
天正19年(1591)、徳川家康は御朱印地10石、除地7石を安堵し、新たに50石を寄進しました。翌天正20年(1592)には、家康の命によって現在の「秩父神社社殿」が再興されました。 |
| 権現造りの本殿は名工・左甚五郎作の「子育ての虎」、「つなぎの龍」をはじめとする絢爛豪華な彫刻によって飾られました。日光東照宮のような派手さはありませんが極才色で彩られた彫刻は歴史的価値があります。 |
 |
 |
明治時代の神仏分離令により、社名は再び「秩父神社」に戻りました。昭和3年(1928)には、県社から国弊社に社格が上げられました。昭和28年(1953)秩父宮殿下の霊を奉斎し、祭神として合祀しました。 |
| 昭和41年(1966)の台風で社殿が損傷しました。そのため4年をかけて解体復元が行われ、昭和45年(1970)の秋に再建されました。社殿は昭和30年(1955)に埼玉県の有形文化財に指定されています。 |
 |
 |
中世から秩父神社には星の信仰である妙見の信仰が習合しました。今もなお年に一度の大祭である 「秩父夜祭 り」が妙見のまつりとして受け継がれ日本三大曳山祭りの一つとして数えられています。秩父祭の屋台行事と神楽は国の重要無形民俗文化財に、秩父神社神楽は選択無形民俗文化財に指定されています。 |
子宝、子育ての虎
| 徳川家康は、寅の年、寅の日、寅の刻に生まれたそうです。それに因んで拝殿の正面には4面の虎の彫刻が施されています。特に正面左より2つ目の子虎と戯れる親虎の彫刻は、名工左甚五郎が家康の威厳と祭神を守護する神の使として彫刻したそうです。 |
 |
| 子宝、子育ての虎 |
 |
当時の狩野派の絵画では、虎の群れの中に必ず一匹の豹を描くことが定法とされていたことから、母虎があえて豹として描かれているのが特徴的です。 |
| 子宝、子育ての虎 |
つなぎの龍
| その昔、秩父札所15番小林寺の近くに「天池(あまがいけ)」という池がありました。その池に住み着いていた龍が暴れた時には必ずこの彫刻の下に水溜りができたそうです。そこで、この彫り物の龍を鎖でつなぎ止めたところ、それ以後、龍は現われなくなったそうです。 |
 |
| つなぎの龍 |
 |
本殿東側に描かれた、鎖でつながれた青い竜の彫刻がこの「つなぎの龍」なのです。これも左甚五郎作とされています。古来より家や地域の四方を青龍・朱雀・白虎・玄武の四神で守護するという四神思想がありました。この青龍は、秩父神社の東北(表鬼門)を守護しているのです。 |
| つなぎの龍 |
北辰のふくろう
| 本殿北側中央に彫刻された梟(ふくろう)は「北辰の梟」といわれ、体は正面の本殿を向き、頭は正反対の真北を向いて昼夜を問わず祭神を守っています。祭神である妙見は、北極星を中心とした北辰北斗の星の信仰です。北辰の方角に妙見が出現するということです。 |
 |
| 北辰の梟 |
 |
洋の東西を問わず梟は知恵のシンボルとされています。八意思金命(やごころおもいかねのみこと)も知恵の神として崇敬されています。こうしたことから、思慮深い神の使として、社殿北面に施されたと思われます。 |
| 北辰の梟 |
お元気三猿
| 日光東照宮の「見ざる・聞かざる・言わざる」の三猿(さんざる)は、古来の庚申信仰に因んでいます。ここの三猿は日光のそれとは全く違った表情で「よく見・よく聞いて・よく話そう」といった仕草をしています。俗に「お元気三猿」として親しまれています。 |
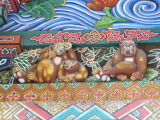 |
| お元気三猿 |
瓢箪から駒
 |
馬に関する諺の一つに「瓢箪から駒」があります。意外なところから意外な発見や出会いがあるという諺ですが、開運招福を意味しています。社殿西側の彫刻はこの諺に因んでいます。秩父の夜祭では、祭神は御輿だけでなく神馬に乗って御旅所に渡るため、毎年12月3日には本物の馬が2頭奉納されているそうです。 |
| 瓢箪から駒 |
天神地祇社
| 古くから秩父神社の境内社の一つとされてきた天神地祇社は全国の一ノ宮(75座)を祀っています。これほど多くの一ノ宮の神々を祀っているのは珍しいことです。 |
 |
| 天神地祇社 |
乳銀杏
 |
昭和8年(1933)秩父宮両殿下が参拝されたときに銀杏の苗木を植えられたそうです。女性のふくよかな乳房のように育ったことから「乳銀杏」と呼ばれているそうです。秩父宮雍仁親王も祭神に加えられています。 |
| 乳銀杏 |
宝登山神社
ほどさんじんじゃ
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1828
Tel 0494-66-0042
 |
宝登山神社は、三峰神社、秩父神社と並ぶ秩父三社のひとつで、古くから火防・災難除けの神様として信仰されています。三峯山同様、お犬さま信仰が残っています。神日本磐余彦尊(神武天皇)、大山祗神、火産霊神を祀っています。 |
| 火防、盗賊除け、諸難除けの守り神として広く信仰されていて、宝登山(標高497m)の山頂には「宝登山神社奥宮」のほかロープウェイ、宝登山動物園、宝登山梅百花園・宝登山ロウバイ園などがあります。 |
 |
 |
第12代景行天皇の41年(111)日本武尊(やまとたけるのみこと)が勅命により、東国平定のためこの地に来ました。遥拝しようと山頂に向っている途中、巨犬が出てきて道案内をしてくれたそうです。 |
| その途中、猛火に包まれどうすることもできない状態になってしまいました。その時、巨犬は猛然と火中に跳入り身体を火に擦り付けて消し止めたそうです。日本武尊は無事頂上へ登り遥拝できました。 |
 |
 |
そして巨犬は忽然と姿を消しました。日本武尊は巨犬は大山祇神の神犬であった事を知り、大山祇神の助けと確信しました。そして、この山に祠を建て大山祇命と火防の神である火産霊命を奉ったのだそうです。 |
| この巨犬が火を消したことより、この山を火止山(ほどさん)と呼ぶようになりました。火防、盗賊除け、諸難除けの守り神として広く信仰され続けています。 |
 |
 |
また他の説もあります。「ホト」とは一般的に女陰を意味する言葉だそうです。それに似た岩か岩屋があって名付けられたという説です。これは生殖・豊饒を尊ぶ古来の信仰から来ているようです。 |
| 現在の社殿は、江戸時代末から明治初頭に造り替えられました。本殿、幣殿、拝殿があり権現造り(ごんげんづくり)です。欄間には、「二十四孝」を始め多くの彫刻が施されています。 |
 |
 |
長瀞駅の目の前に聳える宝登山、宝登山神社の上から、奥宮の立つ山頂下までロープウェイが架かり、山頂には動物園もあり荒川をはじめ奥秩父の山々が見渡せます。 |
| 社殿は弘化4年(1847)本殿再建工事が始まり、明治7年(1874)完成の拝殿を以って成る権現造り(ごんげんづくり)で、社殿の随所には多くの彫刻が施されています。 |
 |
| 宝登山神社本殿 |
 |
「玉の泉」といわれるみそぎの泉があります。日本武命(やまとたけるのみこと)が宝登山に登る前に身を清めたといわれる神聖な泉です。日本武尊が東国平定の途すがら、山ろくの泉で「みそぎ」をされ、ホド山に登られたと伝えられます。 |
| 玉の泉 |
二瀬ダム
ふたせだむ
埼玉県秩父市大滝3875
Tel 0494-55-0001 二瀬ダム管理所
 |
二瀬ダムは荒川の最上流にあるダムです。堤高95mのアーチ式コンクリートダムで昭和36年(1961)に完成しました。調査開始から約9年、着工からわずか4年で建造したということです。 |
| 堤の長さ290mの二瀬ダムは荒川と大洞川と二つの川の合わさるところを堰き止めたダムです。そのため二瀬ダムと命名されたそうです。 |
 |
秩父湖
ちちぶこ
埼玉県秩父市大滝
Tel 0494-55-0001 二瀬ダム管理所
 |
秩父湖は荒川の急峻なV字谷をダムによってせき止めた細長い人工湖です。紅葉が美しい山あいの湖で、ダムの堰堤周辺から湖北側には遊歩道が整備されています。 |
| 湖には二つの吊り橋が架けられており、秩父連山の山並みと湖のコントラストは何ともいえない雰囲気をかもし出しています。稲川淳二の「恐怖の現場」でも取り扱われ、自殺の名所として知られるようにもなったそうです。 |
 |
 |
荒川の水源地にあたる秩父山地は、標高2000m級の山陵が連なるかなり険しい地形です。そこから松葉のように数多くの支川が流れ出て、秩父盆地を要に集まっています。 |
女男の滝
めおとこのたき
埼玉県秩父市大滝
 |
二瀬ダムから秩父の三峰神社に行く途中、女男の滝と見返りの滝があります。「女男の滝」は、二瀬ダムから2kmほど上ったところにあります。 |
| 荒川源流の大滝にある二筋の流れがあることからこの名があります。縁結びの滝とされています。落差は10mぐらいですが水量は少ない感じです。 |
 |
見返りの滝
みかえりのたき
埼玉県秩父市大滝
 |
二瀬ダムから秩父の三峰神社に行く途中、女男の滝と見返りの滝があります。見返りの滝は女男の滝より少し上にあります。 |
| 落差は15mぐらいです。その昔、三峯参拝の帰り、名残を惜しんで振り返ったと伝えられている滝です。この滝の真上が三峯山頂です。 |
 |
三峰神社
みつみねじんじゃ
埼玉県秩父市三峰298−1
Tel 0494-55-0241
 |
社伝によれば、日本武尊が東征のおり秩父に立ち寄って日本では最初の夫婦神である伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉册尊(いざなみのみこと)両神を祭ったのが始まりといわれています。 |
| このとき、日本武尊が争いあう二匹の狼を仲裁したことで、三峰山に住む狼が尊に従い眷属となったそうです。人々から大きな信仰を集めているのは、この御眷属(ごけんぞく)様と呼ばれる神使の「大口真神」です。これは秩父山中に生息していた狼を祀ったものなのです。 |
 |
 |
三峰神社の神門や鳥居の前にはたくさんの狼の像(狛狼)が置かれています。これが御眷属様です。「神犬」あるいは「オイヌサマ」とも呼ばれています
。御眷属様の護符を受けることで、盗賊や火災から御眷属様が守護してくれると信じられていたのです。 |
| 御眷属様は、本殿左手奥の摂社、御仮屋神社に祀られています。 人々は毎年神社から御眷属様を「借り」て祠(仮宮)に祭っていました。こうして拝借した御眷属様一疋の威力は50戸に及んだそうです。安政5年(1858)には1万疋以上の御眷属様が拝借されていたそうです。 |
 |
 |
創祀は景行天皇41年(111)日本武尊によって祀られ、後に神仏混淆の山となりました。江戸時代までは山伏たちの修験の山として栄え、別当観音院が支配していました。三峯山は、雲取(くもとり).白岩(しらいわ).妙法(みょうほう)の三つの峰が特に秀でていることから名付けられたそうです。 |
| 修験道は、役小角を開祖とし、山岳での修行により、霊力を身につける実践的な宗教だそうです。役小角は、三山のひとつ雲取山に飛来し修行したと伝えられています。その後景行天皇の巡幸に際して「三峰宮」の称号を賜ったといいます。 |
 |
 |
奈良時代には聖武天皇が「大明神」の称号を贈り、妻の光明皇后が使者を送って観音菩薩像を安置したと伝えてられています。この頃から神と仏が融合調和する神仏習合がおこりました。三峰神社も古くから神と仏が融合調和した聖域であったと考えられています。 |
| 鎌倉時代には畠山重忠ほか関東武士の崇敬を受けました。 荒廃した時期もあったようですが、16世紀初頭の戦国時代には中興の祖とされる月観道満が諸国を勧進し、社殿を再建しました。 |
 |
 |
さらに江戸期には、天台宗聖護院派の修験道場として栄えました。空海が安置した十一面観音に始まるとされる別当寺は観音院高雲寺と称し、同派の関東における拠点として10万石格ともいわれる繁栄を誇りました。明治維新の神仏分離によって三峯大権現は三峯神社となり、僧(修験者)たちも還俗したあと、神に仕えるようになりました。 |
 |
本殿(県指定有形文化財)は寛文元年(1661)中興第6世龍誉法印が、願主となって造営しました。一間社、隅木入春日造り、石積の壇上に立ち、正面と両面に縁をまわし、勾欄(こうらん)をつけ、屋根は銅板葺き、総体に木割も太く、堂々とした格調高い建造物です。全体に漆が塗られ、斗組・虹梁・柱頭などには極彩色が施されています。 |
| 三峰神社本殿 |
| 「寛文元年霜月廿日」の銘ある棟札が現存し、第6世竜誉法印が願主になって造営したことが記されています。なお、寛文元年建立の本殿は再建で、その前の旧本殿は、境内の東照宮の上舎として現存し、三峰神社に残る唯一の貴重な室町時代の建造物です。 |
 |
| 三峰神社本殿 |
 |
拝殿は祭典を行なったり参拝者が昇って拝礼する場所です。寛政12年(1800)再建され、極彩色の装飾が施されています。正面に見える千鳥破風や唐破風が華やかさを添えています。昭和37年(1962)にも改築されています。 |
| 三峰神社拝殿 |
| 拝殿の正面に掲げた大額は有栖川宮一品親王殿下の御染筆になります。 内部の格天井には奥秩父の花木百数十種が画かれ、左右脇障子に竹林七賢人の透彫があり重厚な雰囲気を感じさせます。 |
 |
| 三峰神社拝殿 |
 |
三峯神社の拝殿の手前に三ツ柱鳥居があります。三ツ柱鳥居は三ツ鳥居(みつとりい)とか三輪鳥居(みわとりい)ともいわれています。1つの明神鳥居の両脇に、小規模な2つの鳥居を組み合わせたもので、めずらしい鳥居の様式の1つです。奈良の大神神社とこの三峯神社のものが有名です。 |
| 三ツ柱鳥居 |
| この青銅鳥居は弘化2年(1845)の建立で江戸深川の堅川講中から奉納されています。荒川をいかだで引いてきたということです。奉納者の中に初代塩原太助の名も見えます。 |
 |
| 青銅鳥居 |
 |
神楽殿は神様の御心を慰めるために舞(神楽)の行われる殿社です。太々(だいだい)神楽、里神楽といわれる神話をもとにした神楽は神楽衣装をつけ面をかぶって笛太鼓に合わせて踊ります。 |
| 神楽殿 |
| 三峯の神楽は霧の流れる境内にひびく笛と太鼓との調和も良く巧妙な撥(ばち)さばきから宮本武蔵の二刀流を生み出させたともいわれています。 |
 |
| 神楽殿 |
 |
隋神門は大きな八脚門です。元禄4年(1691)に社殿前の青銅鳥居前に建立されました。現在の隋神門は、寛政4年(1792)に再建されたものです。昔は仁王門でした。仁王像は明治初年、鴻巣勝願寺に移されています。 |
| 隋神門 |
| 隋神門には「三峯山」と書かれた巨大な扁額があります。扁額の文字は伊勢長島藩主にして畫人であった増山雪齋(1754〜1819)の筆跡です。 |
 |
| 隋神門 |
 |
手水社の向かいに木造朱塗りの八棟木灯台があります。飾り灯台で安政4年(1857)に建てられています。高さは6mもあります。度肝を抜くような装飾が施されています。 |
| 八棟木灯台 |
日本武尊(やまとたけるのみこと)銅像は本体5.2mで、地上15mの高さにあります。
大和は 國のまほろは 畳なつく 青垣
山こもれる 大和しうるはし
命の 全けむ人は 畳こも 平群の山の
熊白梼か葉を 髻華に挿せ その子 |
 |
| 日本武尊の銅像 |
 |
三峯神社の奥宮は三峰山(1090m)の隣の山、妙法ケ岳(1329m)の山頂にあります。この妙法ケ岳は険しい岩場もあるため、そこまで行けない人達の為に、境内の少し高い所に「遥拝殿」という見晴台があります。 |
| 遥拝殿 |
| 正面に妙法ケ岳山頂の奥宮が望め、参拝出来るようになっていました。左側は秩父盆地が見えます。近くには森玄黄斉作のご神犬像がありました。奥宮までは徒歩で約1時間以上かかるそうです。 |
 |
| 遥拝殿 |
三峯山博物館
 |
三峯山博物館には、宝蔵に収められていた宝物類、主として修験の山として栄えた観音院時代の資料を展示しています。 |
| 三峯山博物館 |
| 数多くの記録文書や書画類、崇敬者より奉納された品々、また神仏混淆時代の仏像仏画経典などが収容され展示されています。 |
 |
| 三峯山博物館 |
慈恩寺観音
じおんじかんのん
埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺139
Tel 048-794-1354
| 華林山慈恩寺は天長元年(824)慈覚大師を開基とした天台宗のお寺です。坂東33ヶ所観音霊場の12番札所になっています。正面に本堂である間口13間の観音堂が壮大に建っています。 |
 |
 |
寺名は開山の慈覚大師が唐に渡って遊学した長安の大慈恩寺からとったものだそうです。大慈恩寺は天竺から仏典を持ち帰った西遊記の三蔵法師のモデルである玄奘三蔵が漢訳に従事した寺だそうです。 |
| 中世における慈恩寺領には、本坊42坊・新坊24坊の併せて66坊もの塔頭が存在しました。岩付太田氏から、北条氏へ支配が移り、天正17年(1589)に北条氏房の家臣、伊達房実が岩槻城主になり、南蛮鉄の灯籠を寄進しています。この灯籠はさいたま市の有形文化財の指定されています。 |
 |
 |
天正18年(1590)豊臣秀吉の命により、徳川家康は関東に入り関八州を支配しました。家康は寺領100石を寄贈しています。寛文10年(1670)東照神君の霊牌供養料28石を受け、文政年間(1818-1830)から日光輪王寺法親王歴代の参籠所となりました。 |
| 文政10年(1827)慈恩寺は焼失し、天保14年(1843)深乗上人の代に再建され、昭和の大改修がなされて今日に及んでいます。13間4面の大本堂は、格天井の花鳥絵、天井の鳳凰の図、欄間の天人の彫り物などこの大寺にふさわしく、みな立派なものです。 |
 |
 |
境内の十三重霊骨塔には、中国の古典「西遊記」でおなじみの三蔵法師玄奘の遺骨が分骨され、安置されています。昭和17年(1942)、南京駐留の日本軍がたまたま土木作業中に玄奘三蔵法師の遺骨を発掘し、南京政府に届け出ました。そこで、その分骨が日本仏教会に贈られ、現在、ここの石造十三重の塔に納められているのです。 |
牛島のフジ
うしじまのふじ
埼玉県春日部市牛島786
Tel 048-752-2012 藤花園
 |
牛島のフジは日本最古の古木で、フジの木としては唯一、昭和30年(1955)に国の特別天然記念物に指定されています。樹齢は1000年以上、根元の周囲は10m以上、藤棚は780平方mもの面積を持つ国内最大級の藤です。 |
| 主幹の中心部は枯れていて、根元から分岐した10本あまりの幹が絡み合って伸びています。花房は3m近くにもなります。 |
 |
 |
4月中旬から花を付け始め、5月上旬には満開となります。多くの文化人が訪れており、詩人の三好達治は「牛島古藤花」という詩を詠んでいます。 |
 旅と歴史のホームページへもどる 旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる 日本のページへもどる
|
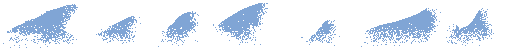
 旅と歴史のホームページへもどる
旅と歴史のホームページへもどる  日本のページへもどる
日本のページへもどる