�X�V���F�@�@
���Ȃ���

�Ԗڂ̖K��҂ł�
�iogino�쐬���ʃJ�E���g�j
��
���Ɨ��jΰ��߰��
OGI�����HP
�M�B��cΰ��߰��
�M�B����ΰ��߰��
�^�c�ꑰ��ΰ��߰��
Mr.ogino��ΰ��߰��
��c�̗��Ɨ��jHP
�M�B�̗�HP
���{�̗�
���E�̗�HP
��
|
���{�̗�
���{�̗��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�n���E����E����
|
�����݂̗�
�����݂̂���
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ��{��
Tel 0278-64-2210 ���̉w�����݂̗�
.JPG) |
�@�����݂̗��͎O���X���̐{��h�ŌÂ�����`������`���̋Z���U�Ȃ���y���߂�Ƃ���ł��B�{��h�ɂ͂ƂĂ����炩�Ȑ�������Ă��܂��B���Ԃ�����Ă��܂��B |
| �{��h |
| �@�����ē����̖L�y�ق𒆐S�ɂ��ĂQ�O�����̉Ƃ���X����Ă����`���̋Z�������Ă���āA�̌����ł���̂ł��B |
.JPG) |
| �{��h |
.JPG) |
�@�{��h�����ق͐́A�e�{�w�����������ł��B����A���A��q�A���Ԃ������̂܂c����{��h�Ɋւ���Õ����E����ȂǓW������Ă��܂��B |
| �{��h������ |
���可�����@
���イ�������傤��₭�������傢��
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ������{��
Tel 0278-62-2111 �݂Ȃ��ݒ��ό����H��
.JPG) |
�@���可�����@�͓V�ۂP�R�N�i1842�j�Ɍ��Ă��܂����B�͍��ƂS��̒�E�q�傪�可����������ꂽ���ɁA�̎�ɒO�����p�l���R�����v�ɖ����Č��Ă������Ƃ������Ƃł��B |
| �@�Ԍ��R�ԁA���s�T�ԁA�m�����̊��菑�@�ŁA����@�i���������j�q�����Q�ԁA���S�ځj������Ԍ��Q�ԁA���s�R�Ԃ̌��ւ��ꉮ�i������j�ƘA�����Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�ɒO�����x�����Ɏg�p�����悤�ł��B�m�����ɐԂ��g�^�����Ă��܂��Ă���̂ŕ���͑��Ȃ��Ă��܂��B�_�Ƃ̏��@�Ƃ��Ă͂߂��炵�����w��̏d�v�������ƂȂ��Ă��܂��B |
�הJ��
�����˂���
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ��{��X�W
Tel 0278-64-1131
.JPG) |
�@�ʌo�Ƃ��������ŗL���ȑהJ���͉��c�Q�N�i1309�j�^���i�����j�ɂ���ĊJ���܂����B�ŏ��͗ՍϏ@�Ƃ��ĊJ�n����܂������A�̂��ɑ����@�ɂȂ�܂����B�J��͍א�ɗ\�猹�j���Ƃ����������邻���ł��B |
| �@�����̓������̒��ňꎞ���ނ��܂������A�����̋ʐW�����������i�Ƃ�����Ԃ��j�ɂ���ēV���U�N�i1537�j��������܂����B�����@�ɉ��@���A���B���ւ���̕�������u���A�Ɠ����S�A�Г���A���萬�A�Ɍ䗘�v������ƐM���L�߂܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�r�ɉ˂��镗��̂���̋���n��ƒ����Βi�������܂��B�Βi�̏�ɂ͌��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���R�傪���X�ƌ��Ă��Ă��܂��B |
| �הJ���R�� |
| �@�~���P�Q�{�̂����P�P�{�͂P�{�̑�P���L������ꂽ�ƌ����`�����Ă��邻���ł��B��w�����ɂ͎߉ގO�����A�ޗt�E����̓���q�A�\�Z�����������u����Ă��܂��B |
.JPG) |
| �הJ���R�� |
 |
�@���i�P�O�N�i1633�j�Ɋw�����|�a���̑�Ɍ��ݒn�Ɉڂ��������A���݂̊�b���ł߂�ꂽ�����ł��B |
| �הJ���R�� |
| �@�R��͈��i�S�N�i1775�j�Ɍ������ꂽ���̂łQ�w�̘O��`���A���ꉮ����A�������A�R�ԂR�˂̘O��i�낤����j�ŁA�T�@�l���̎R��ł��B�V��ɂ͂U�ʊG�悪�`����A�ו��ɂ͐��I�Ȓ������{����Ă��܂��B |
 |
| �הJ���R�� |
 |
�@�@���w�̓V��͂U�Ԃɋ���Ă��܂��B������O�ɂ͗����`����Ă��܂��B�����̚��ɂ͖P�����`����Ă��܂��B���w�̓V��̍��E�̂Q�Ԃ��̂S�Ԃɂ͂��낢��ȓV���̍ʐF�悪�`����Ă��܂��B |
| �הJ���R�� |
| �@��w�̒��ɂ͞��i�����сj�Ȃǂ�ł��Ă��炸�Œ肳��Ă��Ȃ������ł��B�������ɂ͏�w�݂̂���k�ɗh�ꓮ���A������ނƌ��ɖ߂�悤�ɂȂ��Ă��邻���ł��B |
 |
| �הJ���R�� |
.JPG) |
�@�����͊��������������ł������a�S�Q�N�i1967�j�ɓ����ɂ��������ł��B |
| �הJ���R�� |
| �@�הJ���̖{���͊��i�V�N�i1795�j�Č����ꂽ���̂ł��B�הJ���{���̗��ԁA�{��h�͌Q�n���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B���Ԃ͖{�����ʂ̐{��d�̍��E�ɂQ�ʂ���܂��B |
.JPG) |
| �הJ���{�� |
.JPG) |
�@�������ĉE�����˂ɖP���i�ق������j�������Ă��܂��B�����ɂ͏��ɍE���������Ă��܂��B����������ŁA�ʐF����Ă��܂��B |
| �הJ���{�� |
| �@�{��d�ɂ͉��O�i�ۂ���j�ɓ����q�̒������Ȃ���Ă��čʐF����Ă��܂��B���R����̍��荂���{��d�ł��B |
.JPG) |
| �הJ���{�� |
.JPG) |
�@���O��ɗ��͐Ԃ��g�^���̉����ɂȂ��Ă��Đ܊p�̓��R����ɕ��͋C���䖳���̊������܂����B�@ |
�z�K��
���킫�傤
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ����c��
Tel 0278-72-2111
.JPG) |
�@�z�K���͗�����̐���ȗ��ꂪ����o�����k�J�ł��B���㉷��X�̒��S�Ɉʒu����̂����㋬�ŁA���̉����ɐz�K��������܂��B�����ɒf�R���₪�f���鐅����̌��ǂ���ł��B |
| �@���㉷��߂��A��R�D�T�����̌k�J�ł��B�����쉈���ɗV��������������A�t�͐V�A�Ă͗��A�H�͍g�t�A�~�͐�i�F�ƁA�l�G���ꂼ��ɍʂ��ς��A�U����y���߂܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�����P�U�N�i2004�j�ɁA���������{�̕��������Ȃ�݂����E��c�����\�����u���������{�̕��������Ȃ铹�T�O�O�I�v�Ɂu�k�J���E�z�K����K�˂�݂��v�Ƃ��Đz�K�����I��Ă��܂��B |
���㉷��
�݂Ȃ��݂���
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ������V�O
Tel 0278-72-2611
.JPG) |
�@���㉷��͑��Â�ɍ��ۂƕ��Ԍ����L���̉���n�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B������㗬�̌k�������̊R�ɏ������ƃz�e����h���������Ă��܂��B���̍��Ԃ�D���Đz�K���␅�㋬������A�g�t�V�[�Y���ɂ͑����̊ό��q�œ��킢�܂��B |
| �@����X���������Ƒ���g�e�n�Ԃ͐��㉷����\���镗�����ƂȂ��Ă��܂��B������ɂ͊���̋����˂����Ă��āA��ɂȂ�Ɠ������A���㋴�̓��C�g�A�b�v����܂��B |
.JPG) |
����������
���邪���傤����
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ�����������
Tel 0278-66-1246 ����������Z���^�[
| �@����������͎O���X���𗷍s���l�X���爤���ꑱ��������n�ł��B���a�R�R�N�i1958�j�����_�����������ĉ���X�͌̒�ɒ���ł��܂��܂����B |
.JPG) |
| �ԒJ�� |
.JPG) |
�@�����̗��ق��Ί݂Ɉړ]���č��̉���������̌�������������ł��B�ԒJ���猩�鉎��������͕������܂��B |
| �ԒJ�� |
| �@�������Ƃ������͉z��̏㐙���M���֓��N�U�̓r���ɐw�薽�������Ɠ`�����Ă��邻���ł��B |
.JPG) |
| �ԒJ�� |
.JPG) |
�@�ԒJ�ΔȂɂ́u�����̂��������v�ƌĂ���������܂��B�V���Q�P�N�i1552�j�㐙���M���֓��ɏo�����A�㐙�����䂩��̓��}�_�Ђ��Q�q���������ł��B�t���R��莝�Q�������̕ڂ������ɋt���ɂ����������ł��B�����Ă��̍�����𐁂��Ώo�w�̍K�悪�ǂ��Ɛ�����̂ł����B |
| �������� |
| �@�����}���������̍��͌��M�̊�]�ʂ肷�������Ɛ������Đ��N�ʼnԂ��炢���̂������ł��B�����P�W�D�Q���A�ڒʂ�U�D�Q���A�������P�P���̂��̍��̖͌Q�n���̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��Ȃ��B |
.JPG) |
| �������� |
�������֏�
���邪���傤��������
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ�����������P�P�S�S
Tel 0278-66-1156
.JPG) |
�@�������֏��͓���R�㏫�R�ƌ��̎���̊��i�W�N�i1631�j�S���ɐݒu���ꂽ�����ł��B�Q�n���̎j�ՂɎw�肳��Ă��܂��B |
| �@�O���X���͍��n�X���Ƃ��Ăꍲ�n�̋����]�˂ɉ^�ԂT�X���Ɍp���d�v�ȊX���ł����B |
 |
.JPG) |
�@�V�a���N�i1681�j��Ɏx�z���Ă����^�c�������ՂɂȂ薋�{�����̎x�z�ɂȂ�܂����B�㍂��A�Ж�A�ؑ��A�˕��̂S������X���P�Ŋ֎�̖��߂������ł��B |
| �@�����Q�N�i1869�j�����A�����V���{�̖��ɂ��֏��p�~��������ꂱ�̉������̊֏����p�~����܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@���뉀�ɂ͎���R�T�O�N�Ɛ��@����鍂��ꠁi������܂��j������Ă��܂��B�I�m�i�Ђ��ЂƁj�l�̂���Ɍ��܂������ł��B |
�J��x
���ɂ��킾��
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ������R���L�ѓ�
�V�����싛���S����
 |
�@�W���P�X�V�V���̒J��x�͌Q�n�E�V���̌����ɂ���O���R���̎R�ŁA���{�S���R�̂P�ł��B���̖͂����Y�R�A��m�q�R�A�Αq�x�Ȃǂƍ��킹�ĒJ��A��ƌĂ�Ă��܂��B |
| �@�J��x���[�v�E�F�C�œy�����w����W���P�R�Q�P���̓V�_���w�܂ł͖�P�O�����炸�ōs�����Ƃ��ł��܂��B�V�_�����ォ��͒J��A����M�z�̎R�X�̑�p�m���}���L����܂��B |
 |
 |
�@�J��x�̒����͓��ɕ�����Ă��܂��B�g�}�̎��i�W���P�X�U�R���j�A�I�L�̎��i�W���P�X�V�V���j�ƌĂ�Ă��܂��B |
| �@��m�q��Ȃǂ̒J��x�̊��́A���̌��������癛�x�E�䍂�x�ƂƂ��ɓ��{�R����̈�ɐ������A���b�N�N���C�~���O�̃��b�J�ƂȂ��Ă��܂��B |
 |

���ӓ��隬
�Ȃ���݂��傤��
�Q�n�������S�݂Ȃ��ݒ�����
Tel 0278-62-2275 �݂Ȃ��ݒ�����ψ���
.JPG) |
�@���ӓ��i�Ȃ���݁j�隬�́A���a�Q�S�N�i1949�j���w��j�ՂɂȂ��Ă��܂��B�V���U�N�i1578�j���c��͖k�����̎�ɗ����܂����B�������c���̉Ɛb�ł������^�c���K�͏��c��D��̂��߂̗v�ǂƂ��Ă��̖��ӓ����z���܂����B�{�ېՂɂ͐Δ肪�����Ă��܂��B |
| �@�@�V���V�N(1579)�A�k�𐨂͂Q�x���ӓ�����U�߂܂������s�ނ��A���̗��N�^�c���͂��������_�Ƃ��ď��c����U�ߍU�������̂ł��B�^�c�̂̊�C��Ə��c��̒��p�n�Ƃ��ďd�v�ȏ�ł������悤�ł��B�{�ہA��̊ہA�O�̊ہA���ȗցA�����E�A�ʎ�ȗ֓�������܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�V���P�O�N�i1582�j�A�L�b�G�g�ƑΗ���������ƍN�͎����̓P��k�������ɉł����A�k�����Ƙa�c�����т܂����B���̍ہA�^�c�̏�B���c�̂�k�����ɓn���A�k��̂̓s���A���v��������Ƃ������̂ł����B |
| �@���c�ŖS��A����ƍN�ɑg�݂��Ă����^�c���K�͂��̂��Ƃɓ{��A�ƍN�ɔ�����|���܂����B���c�̂�k�����ɓn�����㐙�i���𗊂�܂����B���{�����ƍN�́A�V���P�P�N�i1583�j��c���U�߂܂����B���ꂪ��c��E�_��̐킢�ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@���̌�A�L�b�G�g�̎x�z���ɓ������^�c���K�͏G�g�̒��قْ̍��������c���k�����ɖ����n���܂����B���q�E���v��̐킢�ʼnƍN�ɔs�k�����G�g�����Ėk�����͖��ӓ����܂߂ď��c�̂̂��ׂĂ���ɓ���悤�Ƃ��܂����B |
| �@���c��㒖���M���͐^�c���K�̋U�������薼�ӓ����̗�؎吅�d������c�Ɍ����킹�܂����B�����Ă܂�܂Ɩ��ӓ����D�悵���̂ł����B���K�͂��̂��Ƃ��G�g�ɑi���܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@��������G�g�͌��{���܂����B�����Ėk���̕s�M���Ȃ��菬�c�������̌R���N�������̂ł��B���ӓ���͖k�����ŖS�̂��������ƂȂ�����Ȃ̂ł��B |
�ޗt�R���؉@���ӎ�
�����傤����肤������݂낭��
�Q�n�����c�s�㔭�m���S�S�T
Tel 0278-23-9500
.JPG) |
�@���c�s�̖k�A�W����P�R�Q�Q���̎R���ɉޗt�R���؉@���ӎ��i�����傤�����イ������݂낭���j�͂���܂��B�ޗt�R�͕����R�n�ɘA�Ȃ�[�R�H�J�̏��ɂ���܂��B |
| �@�����V�c�̍c�q�����e���̔���ŁA�V��@��b�R����E���o��t���Ïˌ��N�i848�j�ɊJ�c�����Ƃ��������@�̖����ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@���������R�̖@�A�Ȗ،������̌Õ�(�ӂ�݂�)�_�ЂƂƂ��Ɋ֓��R��V��̈�Ƃ��ėL���ł��B |
| �@�N���Q�N�i1456�j�����@�ɉ��@����A���쏉�㏫�R�̋F�菊�Ƃ��Č���P�O�O�A�P�O���̊i���������ꂽ�R�����邨���ł��B����������Q���͂܂��ɐ[�R�H�J�Ƃ��������͋C���Y���܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�ޗt�R�Q��ł́A�ŏ��̔N�A����������V��ʂ���ċA��A���ɂ��Q�肷�鎞�Ɏ肽�ʂƁA��O�̓X�Ŕ������߂��V�����ʂ̂Q��Ԃ��Ƃ����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B |
| �@�������ɂ́A���{��̑�V��ʂ����u����Ă��܂��B���a�P�S�N�i1939�j�A���H��L�u�ɂ��폟���F�肵���ꂽ���̂������ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�����U�D�T���A�@�̍����Q�D�W���Ƃ�����V��ʂ́A�召���܂��܂ȓV��ʂƂƂ����J���Ă��܂��B�t�͐V�A�Ă͗쒹�u���@�m�v�̐����A�H�͑S�R�g�t�A�~�͔���l�͂��������܂��B |
| �@���a�S�U�N�i1970�j��V���^��ɂ���ʈ��S���F�肵�č��ꂽ�u��ʈ��S�g�����V��v�����u����Ă��܂��B |
.JPG) |
�@
.JPG) |
�@���a�T�W�N�i1983�j�ɏ��c�N��c������[����A���T���Ɉ��u���ꂽ�u���萬�A��V��v�ƁA�s���X�Ȃ��V��v���U�Ɉ��u���ꂽ�u�ό���V��v�́A���N�W���R�`�T���ɍs����u���c�܂�v�ɂ����ď����ɒS���o����l�C���Ă��邻���ł��B |
| �@�����̓V��̂��ʂ͊�|���Ɏ���ɂP�����Ă����A����傫��������̂Ȃ̂������ł��B |
.JPG) |
���c����
�ʂ܂���������
�Q�n�����c�s���q�����T�X�S
Tel 0278-23-2111 ���c�s�����s�s�v��ۓs�s�{�W
.JPG) |
�@���c�����͎s�X�n�̖k���ɂ�����c��̖{�ۂƓ�̊ېՂ����������ł��B���̖����Ƃ��Ă��L���ʼnԒd�ɂ͔������Ԃ��A�����Ă��܂��B |
| �@�@�V�R�̗v�Q�̒n�ł��������c��͎O�����}���ƒf�R�Ɉ͂܂�A�֓��Ɖz��A��Â����Ԍ�ʂ̗v�Ղ̏��c��n�ɎO�Y���n���c���ɂ���Ēz����܂����B���̌�A�㐙�A�k���A�D�c���Ɏx�z����A�V���P�W�N�i1590�j�L�b�G�g�ɂ���Đ^�c���K�Ɉ��g����܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�@������c���ɂ͐^�c�M�V���Ȃ�A�ߐ��I�ȏ�s�̐����ɂƂ肩����A��̊ہA�O�̊ہA�x�A�y�ۂȂǂ�z���A����ȗւɑ������āA�c���P�Q�N�i1607�j�ɂܑ͌w�̓V��t�����������܂����B |
| �@�@�V�a���N�i1681�j�T����^�c�M�����]�˗������̗p�ނ̔��o���x���Ǝ����̖��ڂʼn��ՂƂȂ�A�V��t�Ȃǔj�p����܂����B���̌�A�{�c�A���c�A�y�̋���ƂȂ�܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�{�ېՂɂ͏��O�����݂���A�Q��ˎ�^�c�M�g����������������i���傤���傤�j���މ������Ă��܂��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
�������ƏZ��
���イ���Ԃ��������イ����
�Q�n�����c�s���q�����T�X�S
Tel 0278-23-2111 ���c�s�����s�s�v��ۓs�s�{�W
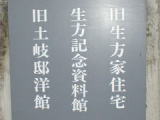 |
�@���c�����~�n���ɂ́A���a�S�T�N�i1970�j�ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�����ƏZ������ڒz����Ă��܂��B���c�˂̏鉺���Ɏc�鐔���Ȃ����ƌ��z�ł���A�����{���w�̌Â����ւ��Ă��܂��B |
| �@�����Ƃ́A��X�A���c�˂̖���p�B�߂������ʼn����́u���ǂӂ��v�Ƃ����������ł��B�Z��͂P�V���I���Ɍ��Ă�ꂽ��������ł��B |
 |
.JPG) |
�@�؍ȁA�Βu���A�ȓ���Ō��s���U�ԁA���ԂP�O�ԁA�쑤�ɓy�݁A�����ɉ�����݂��Ă��܂��B���a�S�W�N�i1973�j�A���ݒn�i���n�͏��c�s��V���j�ł��鋌���c��Ւn�Ɉڒz��������Ă��܂��B |
�^�c�͓���M�g�̕�
���Ȃ����킿�̂��݂̂Ԃ悵�̂͂�
�V�j���i�����j��
�Q�n�����c�s�ޖؒ��R�O�X
Tel 0278-23-1565
.JPG) |
�@�^�c�M�g�́A���c�ˏ���ˎ�^�c�M�V�̒��q�ŁA��͑�@�@�i�����a�j�ł��B���a�Q�N�i1616�j�M�V����c��Ɉڂ�����A���c�˂Q��ˎ�ƂȂ�܂����B��͑���Q�X�V�����̕�⸈Ŋ��i�P�Q�N�Ɍ��Ă��܂����B���c�s�̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B���W���ʂɘZ�A�K�����܂�Ă��܂��B |
| �@�^�c�M�g�͊��i�P�P�N�i1634�j�P�P���Q�W���ɍ]�ˉ��~�ŖS���Ȃ��������ł��B���N�S�Q�ł����B��[�͏��c�֑����ޗt�R�ʼnΑ����A�V�j���ɑ����܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�M�g�͌c���P�X�N�i1614�j���~�̐w�Ɨ��N�̉Ă̐w�ɂ͕��̐M�V�Ɠ�����ɉ�����������Ă܂����B���Ƃ��ĂP�W�N�ԑP�����s�Ȃ��A���Ə��c�̊Ԃ̗p�������������������ł��B |
| �@�V�j���ɂ����x��̕z�ςݐΊ_�ł��B�Ί_�̐ςݕ��́A�z�ς݂Ɨ��ς݂̂Q�ɑ傫���������܂��B�傫���̈Ⴄ���R�̕��A���H�����������܂��܂ȕ����ɑg�ݍ��킹�Đςݏグ�闐�ς݂ɑ��A���`�ɐ��`������r�I�������Ȑ�ڂ����ɒʂ�悤�ɐςݏグ����@�ł��B |
.JPG) |
�������̑�
���킵�݂��̂���
�Q�n�����c�s�㔭�m��
Tel 0278-23-1137�@���c�s�ό�����
.JPG) |
�@�������̑�͌����㔭�m�E�ޖؒ������ʌ������Ɍ������ƉE�̓������ɂ���܂��B�N���o�����������������̏����ȑ������ė���Ă����܂��B���̂悤�ɁA���������n�\�ɏo�ė��ꗎ�������u�����e�i�����イ���j�v�Ƃ��������ł��B |
| �������̑� |
| �@�u�������v�Ƃ������O�̗R���́A���ɐG�����Ƃ��Ɏv�킸�u���i����j���v�ƌ������Ƃ��납�疼�t����ꂽ�����ł��B�������̑�̗����͖�P�O���ł��B |
.JPG) |
| �������̑� |
�ʌ�����
����炱������
�Q�n�����c�s�ʌ�����
Tel 0278-23-9311 �����X�L�[�p�[�N
.JPG) |
�@�ʌ������i����炱������j�͕����R����[�A�W���P�Q�O�Om����P�T�O�O���̈�тɍL���鍂���ł��B�t�͐��m�ԁA�Ă̓��x���_�[�A�H�͍g�t�A�~�̓X�L�[�ƁA�l�G��ʂ��Ċy���߂܂��B |
| �@ �S�����{����T�����{�ɂ̓~�Y�o�V���E�̌Q�������邱�Ƃ��ł��܂��B�ʌ������Z���^�[�n�E�X����P���Ԃ��炢�Łu�������v�ƌĂ�鎼�����U�邱�Ƃ��ł��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�V����{���璆�{�ɂ̓j�b�R�E�L�X�Q�A�V�����{����W�����{�ɂ̓��i�M������x���_�[���炫�ւ�܂��B���x���_�[�͖k�C���̕x�ǖ삩��ڐA�������̂ł��B |
| �@����烉�x���_�[�p�[�N�ł́A�X�L�[��̃Q�����f�ɖ�T�����̃��x���_�[���炫�A���F���O�~�ł�������L���ɂȂ�܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�W�����{�܂ł̓}���[�S�[���h�Ȃǂ������ɂȂ�܂��B�V�[�Y�����ɂ͏��c�w���璼�s�o�X���P���S�{�^�s����܂��B |
| �@�ʌ��P���̑S���T�D�W�����̃T�C�N�����O�R�[�X������܂��B�ĎR���t�g���g���ĉԔ������w�ł��܂��B���{�ł��L���̃u�i�т�����A�~�̃X�L�[��A�L�����v��A�ς���̃z�r�[�T�C�N�����y���߂�T�C�N���p�[�N�Ȃǂ����ʂɑ����Ă��鍂���ł��B |
.jpg) |
�ʌ���
����炱
�Q�n�����c�s�㔭�m���ʌ�
Tel 0278-23-1137 ���c�s�ό�����
.JPG) |
�@�ʌ��͋ʌ������ɂ���l���ł��B���a�T�V�N�i1982�j�ɔ��m��i�ق�������j�㗬�ɑ���ꂽ�ʌ��_�������ɂ���Ăł��܂����B���͂��L�t���тň͂܂ꂽ���R�L���Ȍł��B |
| �@�ʌ��_���͒����T�V�O���A�����P�P�U������A�����y���Ր��nj^���b�N�t�B���_���ł��B���d��p�_���œ����d�͊�����Ђ����a�S�W�N�i1973�j��茚�݂ɒ��肵�A���a�T�U�N�i1981�j�Ɋ��������Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@��ʓI�ȃR���N���[�g���̃_���ƈ���Ă��āA��ςݏグ���đ����Ă��܂��B�ʌ��͎��R�ƒ��a���A�Ɉ͂܂ꂽ�������ł��B�H�ɂ͎��͂̍g�t���f���āA����w�f���炵�����i�������܂��B |
�����̑�
�ӂ����̂���
�Q�n�����c�s�������NJL
Tel 0278-56-2111 ���c�s�������U����
 |
�@�����̑�͓��m�̃i�C�A�K���Ƃ��Ă�A���a�P�P�N�i1936�j�A���̓V�R�L�O���Ɏw�肳��܂����B�����V���A�ЂR�O�����܂�ɋy�сA���������Ɨ����A��U�����e�z�Ɉ��|����܂��B |
| �@�ÊD��A�ԛ���̉͏���𗬂��Еi��̐������A�⎿�̓�炩��������Z�H���A�����̊���ڂ������܂����B����Ȋ₪�������ꂽ�悤�Ɍ�����Ƃ��납��A�u�����̑�v�̖������܂�܂����B |
 |
 |
�@�̂���A�����̑�̑��͗��{�ɒʂ��Ă���Ƃ������Ă��܂����B���̏j�V�ȂǐU�镑�����ɂ́A���{���炨�V�₨�o��݂��Ă��炤�K���������������ł��B���鎞�A�����ԈႦ�Ĉ�g�����Ԃ��Y�ꂽ�Ƃ���A����ȗ��݂��Ă��炦�Ȃ��Ȃ��������ł��B |
���b�N�n�[�g��
������́[�Ƃ��傤
�Q�n����ȌS���R���T�T�W�R�|�P
Tel 0279-63-2101
.JPG) |
�@���b�N�n�[�g��́A1829�N�i�����P�Q�N�j�ɃC�M���X�Ō��݂���A���a�U�Q�N�i1987�j���畽���T�N�i1993�j�ɂ����ē��{�ֈڒz���ꂽ�Ï�ł��B |
| �@���b�N�n�[�g�Ƃ̗R���́A�\���R�̎���ɑk��܂��B�X�R�b�g�����h�Ɨ��̉p�Y�E���o�[�g�E�u���[�X���Ɏd���Ă����R�m���E���ɐ���Đ펀���A���̋R�m�̐S���́A�̔��ɓ���āA�{���Ɏ����A���܂����B�����āA���̋R�m�̈ꑰ�́A���b�N�n�[�g�Ƃ����c����������ꂽ�����ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�q���̃E�B���A������b�N�n�[�g���݂̓X�R�b�g�����h�n���T�E�X�E���i�[�N�V���C�A�̃J�[���[�N�Ƀ��b�N�n�[�g���1829�N�ɒz���܂����B��R�Q�O�O�g���̍��₩��Ȃ�n��R�K�A�n���P�K�̌��������������ł��B |
| �@���a�U�Q�N�i1987�j�ɔo�D�̒Ð��F���A�k�C���̍L�����Ɍv�悵�Ă������W���[�����h�u���̉����T���^�������h�v�̒��j�{�݂Ƃ��ׂ��A����Ń��b�N�n�[�g����w�����܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@���N�A�S���o�`���t�哝�̂̏����āA�V�x���A�S�����o�R���āA�k�C���ɂ��̐ɕ������ĉ^��܂����B�̃u���b�N���S�O�O�O�A�U�O�O�O�g�������������ł��B�Ƃ��낪���W���[�����h�v��͓ڍ����āA���c�s�̐މ�����������A�e�[�}�p�[�N�u�嗝�Α��v�Ɍ��݂����̂ł����B |
| �@�������[���b�p�̒����݂��Č������嗝�Α��́A����������C�u���A�h���}�̃��P�n�ȂǂƂ��ė��p����Ă��܂��B����ɂ́A�ΊW�̂ق��ɁA�}�������E�������[��_�C�A�i���܂̈�i�A�Ð삳���W�����T���^�N���[�X�̐l�`�A�e�f�B�x�A�Ȃǂ��W������Ă��܂��B |
.JPG) |
���y��ƏZ��
���イ�Ƃ݂��킯���イ����
�Q�n����ȌS���V�厚�哹�P�Q�V�S
Tel 0279-75-2111�@���V����ψ���
.JPG) |
�@���y��ƏZ��͍]�ˎ��ォ��Q�T��p���ꂽ�V�c���̖���̉Ƃł��B�����Q�N�i1790�j�Ɍ��Ă�ꂽ�ؑ��Q�K���āA�����������A���ꉮ����̑�^�_�Ƃł��B |
| �@�y��Ƃ́A�����S�V�����̏o�g�ł������A�V���̍����̒n�ɁA�V�c���J�܂����B���X�ɓc���𑝂₵�A�č�A�{�\�A�^���A���݂��܂ŕ��L���s���m�ł���n�ʂ�z���グ�܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@���y��ƏZ��͑�^�{�\�_�Ƃ̑�\�I�Ȍ����ŁA���a�S�T�N�i1970�j�ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�P�K�͢�y�ԣ �������� ��ł������傤����Ɏd���Ă��܂��B |
| �@����傤����͏��@����Ńc���V��ɂȂ��Ă��܂��B�L���y�Ԃɂ͂S�̔n��������܂��B�y��Ƃ͉^���Ƃ��s���Ă������ߕK�v�������悤�ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�Q�K�͗{�\�p�̕����ɂȂ��Ă��܂��B�\�́A�����͌����̌����Ƃ��č��l�Ŏ������Ă��܂����B�������V�哹�i�����ǂ��j�́A�W�����W�O�O���ƍ����A����n�̂��ߎ\�����炷��̂ɑ�ϓK���Ă��܂����B |
| �@�Ԍ��͂Q�R�D�X�V���A���s�͂P�Q�D�X�T��������܂��B�����̌`��╽�ʍ\������k�ђn���̗{�\�_�Ƃ̓T�^�Ƃ���܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�y��Ƃ͓V���N�Ԃɂ��̒n�ɓy���������r�O�Y�E�q��̌���ŁA���̌�̊J���ɂ��勝�N�Ԃɂ͑��̂R���̂Q�̐��c���y��Ƃ̏��L�ƂȂ��Ă��������ł��B |
| �@��������(���Ԃ�)����Ŋ��̌`�����Ă��܂��B�Q�Ό��̎��ɁA�喼�̏h�����ɂ��Ȃ��Ă��������ł��B |
.JPG) |
�l�����M��
���܂̂�������
�Q�n����ȌS���V�厚�l���R�T�Q�O
Tel 0279-75-2111�@���V����ψ���
.JPG) |
�@�l������̏�����O�A�����R�T�R�������̎l����ɂɉ˂���u�H�����v���牺���̖�P�R�O���̊Ԃɑ召�W���M���������܂��B |
| �@�M���Ƃ́A��̉Q������̗���ɂ��A�⍻�������Ƃ�������A���̊�ՂƐڐG���ĐN�H����Ăł����ۂ����ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�l����̋������̗͂����̓]���A��Ձi�ÊD��j�̐ڐG���ɉ��݂������N�Ƃ��������N���ɂ킽���ĐZ�H�������̂ł��B |
| �@�܂��Ɏ��R�����o�����|�p�ł��B�l����Ɏ搅�_�����ł���ȑO�́A�M���͎q�ǂ��̐��V�я�ɂȂ��Ă��������ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�傫�����̂ł͒��a��R���E�[���S�����z�����M��������܂��B�����͏��a�S�U�N�i1971�j�P�Q���Q�Q�����̓V�R�L�O���Ɏw�肳��܂����B |
�l������
���܂���
�Q�n����ȌS���V��
Tel 0279-64-2321 �l������
.JPG) |
�@�Q�n����ȌS���V�Ɏl���i���܁j������܂��B�ɍ��ۉ���A���É���ƂƂ��ɌQ�n���̂R�����ɂ������Ă��܂��B�l����̌k�������ɂ���������i�F�Ɨɂ܂ꂽ�Ƃ���ł��B |
| �@�u�l���v�̖��O�́A�l���̕a�Ɍ����Ƃ����Ƃ��납�炻�̖����t���������ł��B���Α叫�R�̍��c�����C�����������̂����˂Ƃ������Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@���勬�̓r���Ɉʒu���鏬��̑�ł��B�l����Ɠ������삪��������ꏊ�ł�����܂��B�ꌩ���n����������Ă��čg�t���̌i�F�͐�i�ł��B |
| ����̑� |
�ϑP��
��������
�Q�n����ȌS���V�l���b�S�Q�R�U
Tel 0279-64-2101
.JPG) |
�@�Ԃ����̌��������ɐϑP�ٖ{�ق������Ă��܂��B���{�ŌẨ���h���z���Ŏl������̋�������u�͌��̓��v�̂������Ɉʒu���Ă��܂��B |
| �@�{�ق͌Q�n���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B���\����̑n�ƂłR�O�O�N�̗��j�������Ă��邻���ł��B���̉��ɎR���A�������i�����傤�Ă��j�̂R�̎���̌����������Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@����͐Ԃ����̉��𗬂��V����̐��A�����X�O�O���b�g���̖L�x�ȗN�o�ʂ�����A�����C�͌���|���������ł��B |
| �@�ϑP�ق͐V����Ǝl����̍����_�ɂ����āA�h�̐��ʂ͐V�����n�鋴�ɂȂ��Ă��܂��B�������̉f��̃��P�ɂ��g��ꂽ�Ƃ���ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�ϑP�قɂ́u���\�̓��v�Ƃ��闁��������܂��B���a�T�N�i1930�ɑ���ꂽ�����ł��B�l������̃|�X�^�[�̂��Ȃ��������ł��B |
��������t��
�ЂȂ��݂₭���ǂ�
�Q�n����ȌS���V�厚�l���S�R�V�P
Tel 0279-64-2321 �l������
.JPG) |
�@�������ɂ����t���͍��̏d�v�������ł��B�c���R�N�i1598�j�Ɍ������ꂽ�A��������̌��z�l�����c�������ł��B |
| �@���������Ԃ������̖�t���́A�S���ł��������a�m�ƑT�@�l���̐ܒ����z�ł��B��d�̊�����ʼn������������Ƃ��Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@���ʁA���ʂƂ��ɎO�Ԃł��B�O����Ԃ͊O�w�A�����Ԃ͓��w�Ƃ��āA���̋��Ɋi�q�˂��͂߂���ł��܂��B |
| �@����Ԃ̋��V����x��������ˍ\�̏o�g�░�̌`�A�ؕ@�̊G���l�A�Q�����̌`�Ȃǂ���������̓�����\���Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@��t���̑O�ɂ��邨�ē��͒��w��̏d�v�������Ōc���P�X�N�i1614�j�Ɍ��Ă�ꂽ�����ł��B�����q���a�C���������߂ɒ�߂�ꂽ�������������Ă����Ă��F��Ȃǂ��������ł��B |
��
�₭������
�Q�n����ȌS���V�厚�l��
Tel 0279-64-2927 ���
.JPG) |
�@���R���ɂ��鏔�V�P�_����F�͖@�̎��ŕa���������Ă����Lj�Ƃ��Đ��߂��Ă��܂��B |
| �@���͐̂��璆�������̎��Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B�����Ɉ����ꂽ�N���͖��Ƃ��Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�̂��炱�̖������ނ��Ƃɂ���Ē����ɂȂ�Ȃ��ƐM�����Ă��������ł��B |
| �@�l���̉���͈ݒ��a�Ɍ��\������A���a���Ђ��肤�l�����������K��Ă��邻���ł��B |
.JPG) |
�ɍ��ۉ���
�����ق���
�Q�n���a��s�ɍ��ے��ɍ���
Tel 0279-72-4526 �Βi�̓�
 |
�@�q��̓��Ƃ��ėL���Ȉɍ��ۉ���͐Y���R�̉ΎR�����ŗN�o���������ł��B������P�X�O�O�N���O�̘b�ł��B���t�W�ɂ��r�܂ꂽ���j�̂��鉷��ł��B |
| �@�ɍ��ۉ���̃V���{���̐Βi�X�͒��̐킢�Ŕs�ꂽ���c�������^�c���ɖ����ēV���S�N�i1576�j�ɍ�点�����̂ł��B |
 |
 |
�@�ɍ��ې_�Ђ����ԉ��̊֏��܂Ŗ�R�U�O�i���̊K�i�������A���፷�͖�W�O��������܂��B�́A����h�͌���̋߂��ɂ������悤�ł����A���̍���ł̑����̕����҂̎��Â̂��ߎR�̏�ɗN�������Ă��鉷��������悭�h�ɕ����邽�߂ɁA�Βi�̉���X���o���オ�����Ƃ������Ƃł��B |
| �@�Βi�̓����ɂ��鋤�����ꂪ���O�̂Ƃ���u�Βi�̓��v�ł��B�O�ς͔��ǂ̘a���Ȍ����ł����A�����͕����P�T�N�i2003�j�S���̃��j���[�A���ɂ�苤������Ƃ�����茻��I�ȓ��A�艷��{�݂ɂȂ�܂����B |
 |
�ɍ��ۊ֏���
�����ق������傠��
�Q�n���a��s�ɍ��ے��ɍ��ۍb�R�S
Tel 0279-72-3155 �a��s�ɍ��ۑ����x���o�ό��݉�
 |
�@���i�W�N�i1632�j�A�O���X���̗����҂̗v���Ƃ��Ė��{�̖��ɂ��݂���ꂽ�֏��i�����ԏ��j�����Ă��܂��B�����̊֏��́A�Ԍ��T�ԁA���s�R�Ԃ̖�P�T�̊��������̌����ŁA���͂ɖ؍���A�����ɖ�����݂����Ă��܂����B |
| �@�ɍ��ۉ���́A�q��̓��Ƃ��Ēm���A�]�˂���̕w�l�q�����������̂ŁA����S�C�ɏo����̑F�c��������������܂����B�s�R�҂�߂炦��A���J���܂ŗ^����d�g�݂ɂȂ��Ă��������ł��B |
 |
 |
�@���ł͊֏��̖����ɂ��ďڂ����������Ă��܂��B�X�l�`���ǂ��ł��Ă��܂��B���݂̎����قł́A�����̒ʍs��`��Õ����A����Ȃǂ������܂��B |
�ɍ��ې_��
�����ق���
�Q�n���a��s�ɍ��ے��Q
Tel 0279-72-2351
 |
�@�ɍ��ې_�Ђ͈ɍ��ۉ���̒��ŗL���ȐΒi�X�����߂��ꏊ�ɂ���܂��B�x���̋M�O�_�ЁA�ԏ�̐ԏ�_�ЂƂƂ��ɁA��썑�O�V�{�Ƃ��ČÂ�����M���W�߂��R������_�Ђł��B |
| �@�n���N�͏�������܂����R���ɂ��ƓV���Q�N�i825�j�Ɋ������ꂽ�̂��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B�����͐Y���R���ӂ̎R�X�̐_�ł���u�����ق̐_�v���J���Ă��������ł��B�����n�����݂̎O�{�_�Ђ��ɍ��ې_�Ћ����ɂ������Ɛ��肳��Ă��܂��B |
 |
 |
�@���̒n���̗L�͎҂ł������L�n�����삵�Љ^���������������ł����A�L�n���̐��͐��ނƂ��ɂ��т�A���ݒn�ɑJ��������X�̒���ƂȂ����悤�ł��B |
| �@�ɍ��ې_�Ђ̌�Ր_�͑�ȋM���ʼn���A��Â̐_�l�ł����A�ŋ߂ł́A�����сA�q�����A���Y�̐_�l�Ƃ��Ă��L���ł��B���N�X���̗��Ղɂ͑����̐l�X�œ��킢�܂��B |
 |
���n���C���������㗝���g�ʓ@
���イ�͂킢�����������イ�ɂ������肱�����ׂ��Ă�
�Q�n���a��s�ɍ��ے��ɍ��ۂQ�X�|�T
Tel 0279-72-2237 ���x�b�ԋL�O���w��
 |
�@���������Ɍ��Ă�ꂽ���a���̖ؑ����z�ł��B���ăn���C���Ɨ������������̓��{�����g���o�[�g�EW�E�̕ʓ@�ł��B�n���C�����͖����Q�U�N�i1893)�܂ő��݂��Ă��܂����B���{�ƃn���C�ږ���������������A���E�B�����̓n���C�ږ��̕��Ƃ�ꂽ�l���ł��B |
| �@���{�Ɏc��n���C�����B��̌����ł��B�@���ɂ͓����̃n���C�����Ɠ��{�̌𗬊W�̎������͓���̊�Ȃǂ��W������A�����̎ʐ^�Ȃǂ������Ă��܂��B |
 |
 |
�@���a�U�O�N�i1985�j�Ƀn���C�ږ��P�O�O���N���L�O���Ĉڒz�ۑ�����a��s�w��j�ՂɎw�肳��܂����B |
�ܓ��R���i����ω��j
���Ƃ�����݂�����ł�i�݂����킩��̂�j
�Q�n���a��s�ɍ��ے�����Q�P�S
Tel 0279-72-3619
 |
�@�ܓ��R����ϐ����͍㓌�R�R�ω��̑�P�U�ԗ��ŁA��ʂɂ͐���ω��̖��Őe���܂�Ă��܂��B����ω��͈ɍ��ۉ���쓌��S�����ɂ���܂��B���ÓV�c�A�����V�c�̒���ɂ�荂��
�̍��m�b���m��̊J��ɂ��āA���i�����������̑n���ł��B |
| �@ �����V�c�̎���i690-697�j�ɂ͍��i�ł��长�K�M���Ɛ���k���������Ȏ�����Η����A�䓰�R�O�]���A�V�ɂR�O�O�]���A�����P�W�O�]�̂��Ď������Ɠ`�����Ă��܂��B |
 |
 |
�@���̌�A���~�ɂ���čċ����ꎛ�^���������܂����i���W�N�i1511�j�A��i�Q�N�i1524�j�̉Ђő����̓��F���Ď����܂����B�]�ˎ���ɓ���Ɩ��{����삳����������A�ɍ��ۉ���̓����q��D������̏���҂�����ɂȂ�Ăї������܂����B |
| �@�����ω��v�����łȂ��u���ǂ�v���L���ł��B����ω��R�剺�ɂ����Ɨ��������ǂ�X�́A�b���m��̎w���̂��ƁA�Q�q�҂ɂ��ǂ� ��U�镑�������Ƃ���L���ɂȂ�܂����B���{�O�傤�ǂ�ɐ������Ă��܂��B |
 |
 |
�@�����ɂ���Z�p���͑S���ł���������]�����d���ł��B�n�����Ƃ��Ăꌳ�\����Ɍ�������܂����B�s�̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �@���ɂ͂U�̂̒n���������u����Ă��āA�^�S�����߂ĘZ�p�������ɂR��珂��Ċ肢���Ƃ�����ƁA�肢�����Ȃ��Ɠ`�����Ă��܂��B |
 |
�|�v����ɍ��ۋL�O��
�����Ђ���߂������ق��˂�
�Q�n���a��s�ɍ��ے��ɍ��ۂT�S�S
Tel 0279-72-4788
 |
�@�|�v����ɍ��ۋL�O�ق́A����̈ɍ��ۂ��������S�ɂ��������a�T�U�N�i1981�j�T���Ɍ��݂���܂����B �吳�W�N�i1919�j�u���ґ��v�����{���ʼn̂��A����̖����m��n�������A�ɍ��ۂ̏�������̈�ʂ̎莆����ɍ��ہE�Y��������Ȃ������邱�ƂɂȂ�܂����B |
| �@����͐Y���̂قƂ�ɃA�g���G�����āA�������Y�Ɣ��p�w�Z�ɂ��悤�ƍl���܂����B���������̎v�����ɂ��Ă��̐�������܂����B�L�O�قɂ͒|�v����̑�\��u���D���v���͂��߁A���X�̔��l��A�f�U�C����A
���ʉ�A�f�`�ȂǁA���L����i��W�����Ă��܂��B |
 |
�ԏ鎩�R��
������������
�Q�n���a��s�ԏ钬��ԏ�R���[����W�X�Q
Tel 0279-56-5211
 |
�@�ԏ�R���[�Ɏ��R�̊y���u�ԏ鎩�R���v������܂��B�R�O�N�߂��A�l�̎�Ŏ��R��n�����Ă����ԏ鎩�R���ł������A�����Q�P�N�i2009�j�R���P�T���ɐԎ������𗝗R�ɕ����܂����B����Ј����W�����ԁA�����ŊǗ����A�ĂуI�[�v�����܂����B |
| �@�����̓Z�]���K�[�f���A�l�G�̐X�A���R���ԉ��̂R�u���b�N�ɂ킩��Ă���A�ԏ�̐A���A�����ɂł������Ƃ��ł��܂��B�Z�]���K�[�f���͓��{��̂��Ⴍ�Ȃ������܂ށA�݂��ƂȃC���O���b�V���K�[�f���ɂȂ��Ă��܂��B |
 |
 |
�@���̎��R���̕~�n�͂P�Q�O�w�N�^�[���A��R�U���A�Q�n�ł����Ȃ�Y���Ƃقړ����傫���Ȃ�ł��I�@�R���K�[�f���Ȃ�ł��B |
| �@���������Ă���X�^�b�t�͋C�y�ɉԂ̖��O�Ȃǂ������Ă���܂��B�������Ă�����̕��������ĕ����͓���܂���B�₢���킹�����Ă���s���Ă݂������悢�Ǝv���܂��B |
 |
�S���o����
���ɂ�����������
�Q�n����ȌS�ڗ��������P�O�T�R
Tel 0279-86-4141
 |
�@�S���o�����͐�ԎR�k�[�ɍ��X�ƍL����s�C���Ȍi�ς̊�ό��n�ł��B�C�^���A�̃x�X�r�I�ΎR�A�����ƕ���Ő��E�R���ɐ������Ă��܂��B |
| �@�����ł͗n��Q�̒�������Č��w���邱�Ƃ��ł��܂��B�ԋ߂Ɍ��鋐��ȗn��͔��͖��_�ł��B�S���o�������猩�����ԎR�͟��ϕ�F�̂悤�Ɍ����܂��B |
 |
 |
�@�V���R�N�i1783�j�A��ԎR�̑唚���̍ۂɗ��o�����n�◬�ɂ���āA�P�O�O�O�����鎀�҂��o�܂����B�S���o���́A���̗n�◬�̖��c��Ȃ̂ł��B |
| �@�Ό��ŋS�������������o�����A�Ƃ��������̐l�X�̕��̈�ۂ��A���̖��O�̗R���ƂȂ��Ă��܂��B���̌����������ɓ`�����C�ƁA�L���ȑ厩�R���D��Ȃ��A��ԍ�������̌i�ςł��B |
 |

 |
�@�n�◬�͕��Vkm�A�����W�����ɂ킽�鍕��̍r��ɂȂ��Ă��܂��B�S���Q�D�V�����̗V��������������Ă��āA���R�ɎU�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B |
| �@�S���o���̗n��́A�ӕ����Ό����͂ɑ͐ς��A�}�X�̂��߂ɗo�����ċÌł��Ȃ���Ō�ɗ��o��������ȗn��Ƃ݂��Ă��܂��B |
 |
 |
�@�����̍���ɂ͓V���R�N�i1783�j�̐�ԎR�̑啬�ŋ]���҂ɂȂ���������{�����ԎR�ω����������Ă��܂��B��������S���o�����ԎR�͂������A��ԍ������甒���R�Ɏ����p�m���}���y���߂܂��B |
| �@�ω����͏�슰�i���̕ʉ@�ŁA����ω��Ƃ��Ă��l�C������܂��B�y�傩��\�Q����ʂ��Ċω����֍s���r���ɂ͐��ՎɁA���ω��A���O������܂��B��ԎR�ω����́A���b�R�ωi���`���̔镧�ł��鐹�ϐ�����F���J���Ă��܂��B |
 |
 |
�@�ω���������V�����́A����͖�R�O������S�O�����炢�ł��B��ԍ����ɐA�������P�O�O��̍��R�A���������܂��B�V�V�O���̍��R�A���ώ@�R�[�X��A�P�D�Q�����̉��̉@�Q���R�[�X�A�T�P�O���̕\�Q���R�[�X�A�S�P�O���̗��Q���R�[�X������܂��B |
| �@�k�����ɂ͗n��Ƃ͈�����A��ԍ����̎��R�т���Q�c�c�W��V���N�i�Q�Ȃǂ̉Ԗ����邱�Ƃ��ł���Ԗ؉��Ȃǂ�����܂��B�Ԗ؉��͍L���P�U�W�O�O�O�������A�O���P�R�O�O������܂��B |
 |
 |
�@�����ɂ̓q�J���S�P�����n������܂��B���ہi�Ђ��育���j���d�ނŎ��Y�ي��ŗt�͓��ɕ���ł�����̑̂������˂��ċ��F�ɋP���Č����܂��B�@ |

| �@��ԎR�͊��ΎR�Ō��݂������𑱂��Ă��܂��B�����P�U�N�i2004�j�X���P���ɂQ�P�N�Ԃ�ɔ������܂����B�����U�����A�R���̖k���U�����܂ōő�R�����̉ΎR�I���~�����܂����B���������댯�ɔ����邽�߁B�U���H�̂��������ɔ����݂����Ă��܂��B |
 |
����n����
�����炢�킶��������
�Q�n����ȌS���쌴���k�y��� �P�X�W�W
 |
�@���Ă̐�ԎR�[�͖��l�ł���A���̍������������闷�l�̕�������̂��߂ɒn���������A�M�Z�̍��̍����i�Q�n���E���쌧���t�߁j�ɍ���܂����B�@ |
| �@�������A�V���R�N�̐�ԎR�̑啬�ɂ��A�n������������A�s�����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B��ɒn���쌴�Ŕ�������A����̒n�Ɉڂ������n�����Ɩ�������܂����B�����S�N�i1751�j�A���̒n�������߂����Č���������h���Ɗ����̉������̊Ԃői�����������������ł��B |
 |
 |
�@�������͂��łɐ�ԎR�S�_���ɋ���F�ƒn����F��{���Ƃ��Ē��N���J���Ă���̂ɉ��̒f����Ȃ��ɐ�ԎR���{�Ƃ����͕̂s�͂����Ƃ��đ��̏ꏊ�Ɉڂ��悤�ɐ\������܂����B�n�����̊J�ዟ�{������ю��̘a���͈ꐡ����Ƃ����������Ƃ܂���Ȃ��Ǝ咣�B |
| �@��h�̖���ׂ͒��Ƃ��Ă��̂Ă�Ƃ�����ɂ��ꂽ���Ƃ����A���܂肩�˂����������͕��P�Q�N(1762)��s���ɑi���o�܂����B�ٌ��͒n�����Еt���ƂȂ葼�̏ꏊ�Ɉڂ��ꂽ�����ł��B���a�U�Q�N�i1987�j�ɒ��쌴���w��d�v�������ɂȂ��Ă��܂��B |
 |
�Z�������̓�����ω�
�낭�肪�͂�݂̂�����ׂ���̂�
�Q�n����ȌS���쌴���k�y��� �P�X�W�W
 |
�@��ԎR�k�[�͘Z�������Ƃ��Ă��܂����B�V���R�N�i1783�j�̐�ԎR�̑啬�̉e���ŁA�����͌�ʂ̓�ł����B�V���S�N�i1784�j�n���̐l�X�ɂ��A�B�|�A����A��h�̕���_�ɂȂ��Ă��������i�킩����j�����Ɋω�������������܂����B�i�����T�N�Ɋ������������ł��j���̊ω����͓�����ω��̊�_�ɂȂ��Ă������ߊ�_�ω��ƌĂꂽ�����ł��B |
| �@�����T�N�i1808�j�A�����i�킩����j�����̏��l�Y�Ƃ����l�̊����ɂ��Z�������̓�����ׂƂ��Ċω���������A��_�ω��𒆐S�ɌB�|�A����A��h�̎O�����ɂ��ꂼ��R�R�̂��ݒu����܂����B |
 |
 |
�@�P�O�O�̍��ꂽ�����R�O���̂��m�F����A����n�����ɏW�߂�꒬�̎w�蕶�����ɂȂ��Ă��܂��B�����R�N�i1991�j�ɁA�n���̐l�X�ɂ��P�O�O�̂ɕ������ꐮ�R�ƕ���ł��܂��B |
�����ω���
���܂͂炩��̂�ǂ�
�Q�n����ȌS�ڗ��������S�X�Q
Tel 0279-97-3852

 |
�@�V���R�N�i1783�j�̐�ԎR�啬�͖k�[�֍����̓y�Η��𗬂��A���������͂��ߑ����̏W����j���v�����܂����B�������͎����P�O�O�����̉ӓD���ɏP���܂����B���̑��ɂ͂S�V�V�l�̑��l���Z��ł��܂����B |
| �@���̎��A���̊ω����ɓ��ꂽ�X�R�l��������ՓI�ɏ�����܂����B�ȗ��A�ω����͖���ω��Ƃ��ĐM��Ă��܂��B |
 |
 |
�@�ω����̑O�̐Βi�͌��݂P�T�i�ł����{���͂T�O�i����܂����B���̐Βi���Ō�܂ŋ삯�オ�������l�������ӗ����瓦��邱�Ƃ��ł��܂����B�킸�����i��肫�ꂸ�ɖ��𗎂Ƃ����l����������Ă��܂��B |
| �����ω��� |
| �@�c�������l�͂��ꂼ�ꉏ��g�݁A�V�����Ƒ��ƂȂ��đ����Č����Ă������Ƃ����߂����]���̂���ꏊ�ł��B |
 |
| �����ω��� |
 |
�@�ω����̗���̒ڗ����y�����قɂ́A�o�y���������Ȃǂ��W������Ă��܂��B��ԎR���̉ӗ��Ɋւ��鑍���I�Ȕ��@�����̋L�^�Ȃǂ��W������Ă��܂��B |
| �ڗ����y������ |
| �@���@�����͏��a�T�S�N�i1979�j����n�܂�܂����B�����̎ʐ^���ڂ����Ă��܂����B���݂̒n�㕔���͂P�T�i�ł����A���̏������ŏ����Q���̈�̂��������ꂽ�����ł��B�ω����֓����悤�Ƃ��āA���Ɛ��i�̏��ŊԂɍ���Ȃ������Ǝv���܂��B |
 |
�����R
����˂���
�Q�n����ȌS���Ò����Ô���
Tel 0279-88-0800 ���É���ό�����
 |
�@�����R�͌Q�n�A���염���ɂ܂�����W���Q�P�U�O���̊��ΎR�ł��B �R���ɓ����A���A���� �Ƃ���������A�u�ꑐ�Í������H�ő�̊ό��|�C���g�ɂȂ��Ă��܂��B |
| �@�����R�̓���������ɂ́A�咓�ԏ���P�O���قǕ����܂��B���\�}�ł��������ڂقǑ�ςł͂Ȃ������ł��B |
 |

| �@�����R�̎R���ɂ͐_��I�ȃG�������h�O���[���̐��������������_���̃J���f���u�����v������܂��B |
 |

 |
�@���Ô����R�͍������͂���ŁA�����R�Ɩ{�����R�ɕ�����Ă��܂��B�t�̓S���h������V���N�i�Q�̌Q�������邱�Ƃ��o���܂��B |
| �@���Â���u�ꍂ���܂Ŏu�ꑐ�Ã��[�g���J���Ă��܂��B���͖���������܂����B |
 |
 |
�@�����R�͈يE���v�킹��r���Ƃ������͋C�̒��ɔ������Ό������Ƃ���ł��B����A�{�����R���ӂ͐������ꂽ�n�C�L���O�R�[�X�������āA�����h�E�E�R�}�N�T�E�V���N�i�Q�Ȃǂ̍��R�A�����炢�Ă��܂��B |
������
��������
�Q�n����ȌS���Ò�
Tel 0279-88-0800 ���É���ό�����
.JPG) |
�@���É���͍]�ˎ��ォ��m��ꂽ����ŕʖ��u��̂��œ��v�Ƃ����܂����B�]�ˎ���̉���ԕt�ł͓���ւ̍ō��ʂɈʒu�t�������{���\���鉷��ł��B |
| ���� |
| �@�ї��R�͓��{�O����̈�ɋ����������ł��B���Ẩ���͋����_����ŁA�E�ۗ͂������A�������邱�ƂŐg�̂̊O���A��ɔ畆�����Ȃǂ̏Ǐ�����P�����Ă����͂����邻���ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@����X�̒��S�n�ɂ��鋐��Ȍ������i������j�ł��B��ɔ������������������Ɨ�������A�����̂ɂ������Y���Ă��܂��B |
| �@����ƍN�ɖ�����ɉł����ꐳ���ƂȂ����L�b�G�g�̖��̒����P���S���Ȃ�R�N�O�ɗ×{�ɗ��������ł��B���̍��͐^�c�����������߂Ă��������ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@����^�c�K���ɉł�������J�g�p�����\�R�N�i1594�j�ɓ������Ă��܂��B���C�a�̎��Âɑ��Â̋��_�̓��������������ł��B |
| �@�����̑O�ɔM�̓�������܂��B�u���Â悢�Ɓ`���A�����ǁ`�͂����Łv�ŗL���ȑ��Ð߂��̂��Ȃ��璷���œ����݂��Ă��܂��B |
.JPG) |
| �M�̓� |
.JPG) |
�@�]�ˎ��ォ��`��鑐�Â̓����݂͖�U�O�x�̌���𐅂��������ɓK���܂ŗ�܂��̂ł��B���ÓƓ��̓����@�ɓ����݂ŗ�܂������ɓ����̍��߂ň�ĂɂR���Ԃ����������鎞�ԓ��Ƃ�������������莡�Âɂ��g���Ă��邻���ł��B |
| �M�̓� |
���ÕЉ��ߑ��Y���p��
�������������邽�낤�т������
�Q�n����ȌS���Ò����ÂS�V�X
Tel 0279-88-1011
| �@�����P�O�N�i1998�j�P�Q���A�Љ��ߑ��Y����̒a�����ɃI�[�v���������p�قł��B���Ãz�e���ɗאڂ��Ă��܂��B����ɗ����l�����߂Ɖ��ʂŋC�y�ɓ������p�ق����肽���Ɗ肢���������������ł��B |
.JPG) |
| �Љ��ߑ��Y���p�� |
.JPG) |
�@�������N�i1989�j�Ƀh���}�u�u���̐t�L ���炠�S�b�z���v�ŎႫ���̓����u�������������Ƃ����������ɂȂ��āA���n���`�����蓩�|�������肷��悤�ɂȂ��������ł��B�n�ʉ�⏑�Ȃǖ�S�O�O�_�̎����i�̒������P�Q�O�_�̍�i��W�����Ă��܂��B |
| �Љ��ߑ��Y���p�� |
���̉͌�
�����̂����
�Q�n����ȌS���Ò��厚���ÂT�Q�P�|�R
Tel 0279-88-0800 ���É���ό�����
| �@���̉͌��͑��Â̒����𗬂�铒��̏㗬�A����X�̐����ɐ��̉͌�����������܂��B�����ƂȂ�ԑ��É���̖����̈�ł��B |
.JPG) |
| ���̉͌� |
.JPG) |
�@�u�̉͌��v�u�S�̐v�Ƃ��Ă�A�����炽�Ȃ��ꏊ�ł��B���̉͌������̈�ԉ��Ɂu���̉͌��I�V���C�v������܂��B |
| ���̉͌� |
| �@�����C�̑傫���j�����킹�Ă͂T�O�O�u�i��P�T�O�j����A�r�̒��ɂ���悤�ł��B���̘I�V���C�͑������{�ōő勉�̑傫�����Ǝv���܂��B |
.JPG) |
| ���̉͌� |
�X�L�[������
�Q�n����ȌS���Ò����ÂQ�|�P
Tel 0279-88-0800 ���É���ό�����
.JPG) |
�@���É^�����������̓��̉w�̕~�n���ɃX�L�[�����ق͂���܂��B |
| �X�L�[������ |
| �@�̎g���Ă�������|�łł����X�L�[�̃X�g�b�N��A�n�����Ïo�g�̃X�L�[�m���f�B�b�N���������_���X�g�������i�I�肪�g�p�����E�G�A��X�L�[�Ȃǂ��W������Ă��邻���ł��B |
.JPG) |
| �X�L�[������ |
�x���c���m�L�O��
�Q�n����ȌS���Ò����ÂQ�|�P
Tel 0279-88-0800 ���É���ό�����
.JPG) |
�@�x���c���m�L�O�ق͑��É���̖��𐢊E�ɍL�߂��h�C�c�l��t�G�����B���E�t�H���E�x���c���m�̎����قł��B |
| �x���c�L�O�� |
| �@���Â̖������^���A�N�A�n�E�X�Ö@��ł��o�����x���c���m�̈�i�⎑���Ȃǂ��W������Ă��܂��B |
.JPG) |
| �x���c�L�O�� |
.JPG) |
�@�X�L�[�����فA�x���c���m�L�O�ق����鑐�É^�������������̉w�ł��B���É���̑����C���t�H���[�V�����Z���^�[�Ƃ��Ċ��p����Ă��܂��B |
| ���̉w |
��Ȍk�J
�����܂�������
�Q�n����ȌS����Ȓ��厚���J
Tel 0279-68-2111
.JPG) |
�@��ȌS���쌴���ƌ�Ȓ��ɂ܂������Ȑ���Ő��F�̌k�J����ȋ��ł��B���ɒ��쌴���쌴���̔��c��勴����A��Ȓ����J�̊�K�܂ł̊Ԗ�R�D�T�L�����w���܂��B |
| �@���c��勴���玭�܂ł̖�P�D�W�����ɂ͗V��������������Ă��܂��B |
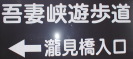 |
.JPG) |
�@��B�̑啪���k���̖�n�k�͌������k�J�ŗL���ł��B�吳���N�i1912�j�A�����Ȓn���w�ҁA�u��d�V����Ȍk�J��K��u�֓���n�k�v�ƌĂ�ł��܂��B |
| �@���̌k�J�͌�Ȑ�̋}�����A�����̊�̎R����[����Z�H���č��ꂽ�����ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�吳��N�A�̐l�̎�R�q������Ȍk�J��K��u�ǂ��炩�Ƃ����i��B�̖�n�k���j�`�̏������[���ĐÂ��Ȍ�Ȃ̌k�ɁA��葽���S�̎䂩���̂������v�i�u�݂Ȃ��I�s�v�j�ƋL���Ă��܂��B |
| �@���a�P�O�N�i1935�j�ɍ��̖����Ɏw�肳��Ă��܂��B�Ȃ��A���̈�т͔��c��_���̌��ݗ\��n�ɂȂ��Ă��܂��B���̃_������������Ɩ����w����̖�S���̂P�������Ă��܂��܂��B |
.JPG) |
��C���
����т��傤����
�Q�n����ȌS����Ȓ�����
Tel 0279-68-2111
.JPG) |
�@��C��́A���q���㏉���Ɍ�ȑ��Y�����ɂ��z�邳�ꂽ�Ƃ����܂��B��s�̋K�͂͂P�D�S���������Ə�B�ő�ōb��̊�a��A�x�͂̋v�\��ƕ��ѕ��c�̓��̂R����Ə̂���܂����B |
| �@���̌�A�֓������̎�ɂȂ�A�i�\�U�N(1563)���c�M���͏d�b�E�^�c�K���Ɋ�C��U���𖽂��܂����B���A�֓���͕��킵�܂������A���c���̎蒆�ɗ����܂����B�����čK���͌�ȌS�̎��𖽂����܂����B |
.jpg) |
 |
�@�V���Q�N(1574)�A�K���̎���A���q�̐M�j�����ɂȂ�܂������A���N�A���̐킢�ŐM�j�A���P�Z�킪�펀�B�^�c�Ƃ̂R�j�A���K���������܂����B��C��͕��c���ŖS�̍ۂɂ͏��K�����c�������}���鏀�������Ă�����ł�����܂��B |
| �@�^�c���K�͓���ƍN�̉Ɛb�ƂȂ�܂������A��c�̗̒n�ł�����c�̂�k�����ɓn���悤�ɂƂ�������������f�������߁A�V���P�R�N�i1585�j�ƍN�͏�c����U�����܂����B���Ǔ���R�͐疼�ȏ�̐펀�҂��o���Ĉ����グ�܂����B�L�b���ɂ������K�ɏG�g�͖k�����Ƃ̒��ق����܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@���ӓ��͐^�c�ɁA���c�̂̂R���̂P�͐^�c�ɁA�c��R���̂Q�͖k�������ɂƂ������e�ł����B�������A���c�S�̂ɍŌ�܂ł������k�������́A�G�g�̒��ق����ď��c��㒖���M���ɖ��ӓ�����U�������܂����B����ɓ{�����G�g�́A ���c������U�߁A�k�����͖ŖS���邱�ƂɂȂ����̂ł��B |
| �@�V���P�W�N(1590)�A�k�����̖ŖS�ɂ��A�M�K�͏�����c���ƂȂ�A��C��͏��c�̎x��ƂȂ�܂����B�������A���̐w�̍ۂɓ��쎁���͂����Đ^�c�M�V�̎�Ŕj�p����܂����B |
.JPG) |
��C�R
.JPG) |
�@��C�R�͌�ȂW�i���\����i���n�ł��B�W���W�O�Q���ʼn��₩��Ȃ�藧������R�ł��B��ʂ͂Q�O�O�����̒f�R��ǂɂȂ��Ă��Ē�����̂悤�Ȏ�ł��B |
| ��C�R |
��C�鉷�났�̊�
| �@��C�鉷�났�̊ق͊�C�ӂꂠ���̋��̒��S�I�Ȏ{�݂ł��B��������C��Ɏ����Ă��錒�N�Z���^�[�ł��B�{���̊�C��͐^�c���̋���Ƃ��ėL���ł����B |
 |
| ��C�鉷�� |
�s���̑�
�ӂǂ��̂���
�Q�n����ȌS����Ȓ������V��
Tel 0279-68-2111
.JPG) |
�@�̂͏��R�Ƃ���ۂƌĂ�Ă����W���T�R�O���̊ω��R�i��䮎R�j�̂ӂ��Ƃɂ͑�䮎R�s�����̓�������A���̂��ɕs���̑ꂪ����܂��B |
| �@�����S�N�i1747�j�ɂP�O�O�̊ω��Α����J���Ă���ω��R�Ƃ�����悤�ɂȂ��������ł��B���R�Ɛ��R������A���R�ɐ����R�R�ԂƔ��R�R�ԁA���R�ɒ����R�S�Ԃ����u����Ă��邻���ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�s���̑�͎O�d�̑�Ƃ��Ă�쌱����ꂾ�����ł��B�����R�O���̂R�i�̑�ł��B�V��g�t�ȂǁA�l�G�܁X�ɔ�������Ȃ̕��i�̍\���v�f�ƂȂ��Ă��܂��B |
| �@��̉��ɂ͉��̉@�̌A������܂��B�����ɂ͊�C�R�ɒʂ��铹������Ζ傪����܂��B |
.JPG) |
| �s���� |
�߂��ˋ��i�O�X��R�A�[�`�j
�߂��˂��i�����������R���[���j�j
�Q�n�������s����c����{
 |
�@�߂��ˋ��͐M�z���A�v�g���S������Ɏg��ꂽ��R�����ł��B�����͑�Q���������U�����܂ł̂T��c���Ă��āA�u�O�X���S���{�݁v�Ƃ��č��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �@�S���͉O�X�̋}�s���z���邽�߃h�C�c�̃n���c�R�S���̃A�v�g�����̗p����܂����B�����̐v�҂̓C�M���X�l�̃p�D�l���Z�t��ł��B�����Q�T�N�i1892�j�P�Q���ɏv�H����Q�U�N�ɂ����Č��݂���܂����B��������̃A�[�`���Œ����͂W�V�D�V���A�����͂R�P������܂��B |
 |
 |
�@�����z�͂P�O�O�O���̂U�U�D�V�Ƃ��������S�ō��̂����z�ł��B���a�R�W�N�X���ɑ��x���ǂ̂��ߔp�~�ɂȂ�܂����B�D�ꂽ�Z�p�ƌ|�p�I�Ȕ������͍��Ȃ����̈Зe���c���Ă��܂��B�@ |
| �@�������{�͍ŏd�v�̗A�o�i�����������Y�Ƃ̐U���ƁA�����{�̕�����A�����邽�߂��̓S�������������܂����B |
 |
 |
�@�T�O�O�l�ȏ�̋]���҂��o���Ȃ���A�킸���Q�N�Ԃ̍H���ł��̑�H���͏o���オ�����̂ł��B |
| �@��������P�Q�̃g���l���̓�����͂��ׂĈ�����f�U�C���ɂȂ��Ă��܂��B��{�I�ɂ̓����K�ς݂ł�������I�݂ɑg�ݍ��킹�A���قȊO�ςɂȂ��Ă��܂��B |
 |
�O�X��
��������
�Q�n�������s����c����{
 |
�@�O�X�͐M�z���̘e�𗬂�钆����ƉO�X��̍����_�������~�߂đ������L���ȗ̒��ɂ���l�H�ł��B�C���i�A�}�X����������Ă��邽�ߒނ��Ƃ��Ă��l�C������܂��B |
| �@�l�������L�т̑�ɕ����A���ɏH�̌Ζʂɂ���g�t�͑f���炵���Ƃ������Ƃł��B�ŋ߁A����w�̉O�X�S�������ނ炩��߂��ˋ����ʂɂÂ��V�������������Ă��܂��B |
 |
��{�h
�������Ƃ��キ
�Q�n�������s����c����{
 |
�@��{�h���o�����͓̂���ƌ��̎���ł��B�Q�Ό��ɔ����O�X���̓o����ɏh�ꂪ�K�v�������̂ł��B���i�Q�N�i1625�j�ɕt�߂̏Z�����ڏZ�����A�����P�S�D�W�T���A�����V�P�R���̓��H���������ɂ͗p���H��ݒu���܂����B |
| �@�����ɖ{�w�A�e�{�w�A�n�h�A���ĂR�Q���A�����A���C���A���Y���e�U���A�ĉ��A�b�艮�Ȃǂ��ׂĂ̏��X�����т܂����B���݂ł������̌������������c���Ă��܂��B |
 |
�O�X�֏���
�������������傠��
�Q�n�������s����c�����쉳�T�V�R
Tel 027-393-1111
�@�O�X�֏��͑��V�c�̏��ׂQ�N�i899�j�ɌQ���������܂邽�߂ɉO�X��ɐ݂����܂����B���̏ꏊ�Ɉڂ����̂͌��a�N�ԁi1615�`1623�j�Ƃ����Ă��܂��B
�@���a�Q�N�i1616�j�������u�Ɉ䒼���v�������ɂ�����ƂȂ�A�Ȍ������傪��X����ɂ�����܂����B |
 |
 |
�@�u����S�C�ɏo���v�Ƃ������ˑ̐��𒆐S�Ƃ������얋�{�̊m���A����̂��߂Ɏg���܂����B�����Q�N�i1869�j�̔p�~�܂Œ��R���̗v���ƂȂ�܂����B |
�O�X���S�������ނ�
�������Ƃ����Ăǂ��Ԃނ�
�Q�n�������s����c������S�O�V�|�P�U
Tel 027-380-4163
| �@�����X�N�i1997�j�̒���V�����J�ʂɔ����A�M�z���́u�O�X�z���v�i����|�y���ԁj���p���ɂȂ�܂����B���̉O�X���̓S���P�O�O�N�̗��j���c�����߂Ɂu�O�X���S�������ނ�v�������P�P�N�i1999�j�S���ɉ���@��̐Ւn�Ɋ������܂����B |
 |
 |
�@�����ɂ͉��ƃr�f�I�ɂ��^�]�̌�����j�����̓W���A�L�����O�ɂ͑����̕ۑ��ԗ���A�~�j�r�k�⋷�O�r�k��Ԃ̉^�]���s���Ă��܂��B |
| �@�M�z�{���̔p���Ղ𗘗p���āAEF�U�R�`�d�C�@�֎Ԃ̑̌��^�]���s�Ȃ��Ă��܂��B�܂������P�V�N�i2005�j����A�g���b�R��Ԃ̉^�s���J�n���Ă��܂��B |
 |
�H�Ԕ~��
�����܂����
�Q�n�������s����H��
Tel 027-382-1111
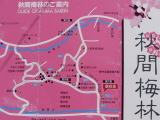 |
�@�H�Ԕ~�т͏H�Ԑ�̏㗬�̎R�����ɍL�����T�O�w�N�^�[���̔~�тł��B���R�Ȃ����Ƃ��Ȃ��悤�ɑ���ꂽ�����ł��B |
| �@�R�T�O�O�O�{�̍g���~���Q�����{����R�����{�ɂ����ĎR�Ԃɍ炫�ւ�܂��B���N�Q����O�y�j������R�����{�̊ԁA�~�Ղ�͍Â���܂��B |
 |
 |
�@�R���J������s���N�̉ԂŖ��ߐs������A�ق̂��ȊÂ����肪�Y���܂��B |
| �@�~�эՂ�ł́A�~�̉Ԃ̉��Řa���ۂ��炳�ꂽ��AⵋȂ̉��t���������肵�܂��B |
 |
 |
�@�Î����T�[�r�X����A���f���B�e��Ȃǂ��s�Ȃ�ꂽ�肵�Ĕ~�̍�����y���ސl�łɂ��킢�܂��B |
| �@�߂��ɂ͈镔��������܂��B�������\���錩���̈�ɂȂ��Ă��܂��B |
 |
�V��������
�ɂ����܂��傤���イ����
�Q�n�������s�����P�|�V�|�R�O
Tel 027-381-2477
.JPG) |
�@�V�����͖����W�N�i1875�j���u�Б�w�̑O�g�ƂȂ铯�u�Љp�w�Z��ݗ������l�ł��B�V�ۂP�S�N�i1843�j�����ˎm�̎q�Ƃ��č]�ˁE�_�c�̔q�Ə㉮�~�Ő��܂�܂����B�Q�P�̎��A���ق���A�����J�֖��q���L���X�g���k�ƂȂ�܂����B |
| �@�A���㕃��̏Z�ވ����g���܂����B�����V�N�i1874�j�P�P���Q�X���A���̉ƂłP�O�N�Ԃ�ɕ���o���ƍĉ�܂����B���N�P�Q���Q�S���܂ő؍݂��w�Z�ȂǂŃL���X�g���̋�����`���������ł��B |
 |
 |
�@�@���a�R�W�N�i1963�j�Ɉ����s�͂��̐V�����̋�����ڒz���A���̈�i��W���ދy�юʐ^�������W���ēW������{�݂�A���N�ɊJ�ق��܂����B |
| �@ �V�����́A�����W�N�i1875�j�U���ɋ��s�ɂ��鋌�F���˓@�Ղ��w�����A�P�P���ɓ��u�Љp�w�Z��n�݂��Ă��܂��B�����Q�R�N�i1890�j�P���Q�R���ɐ_�ސ쌧�̑��Ő��U���I���������ł��B |
 |
�������ˌS��s���
���イ����Ȃ��͂�Ԃ��傤�₭����
�Q�n�������s�����R�[�U�[�X
Tel 027-381-3855
.JPG) |
�@�������ˌS��s���ɂ́A�Â��͔ˎ�q�����̑��߂̎R�c�O�Y���Z��ł����Ɠ`�����Ă��܂��B���̌�A�����E�q��������������������ł��B���҂Ƃ������˂̌S��s���߂܂����B |
.JPG)
| �@���̌����͕����T�N�i1993�j����U�N�ɂ����āA�Ð}�ʂƌ����Ɏc�鍭�Ղ����ɓ����̎p�ɕ����������̂������ł��B�����ɏZ�ނ��Ƃ͗̓��̔_���̓��������S���Ă����ƍl�����܂��B |
.JPG) |
�������˕��ƒ���
���イ����Ȃ��͂�Ԃ��Ȃ���
�Q�n�������s�����R�|�U�|�P
Tel 027-382-7515
 |
�@�����Ĉ�������ɂ͉Ɛb�̉��~���������т��̈ꕔ�͒��������������ł��B�������˕��ƒ����͂��̂����̂S�������ň����鐼��̂������ɂ��������̂ł��B |
| �@���ׂɂ͂T�������������������ł��B�R���������c�����Ă������������z�����̂S�������ɕ����������ł��B |
 |
 |
�@�����˂̉E�M�E���쒼���c���Ă������}�ʂ����Ƃɂ��ĕ������N�i1989�j����R�N�����ē����̎p�ɕ��������������ł��B |

���O�X�S����
���イ����������₭����
�Q�n�������s�����R�[�Q�P�[�T�P
Tel 027-382-3764
 |
�@�����P�P�N�i1878�j�ɌS�撬���Ґ��@�����z����ĉO�X�S�������J�����܂����B�����Q�P�N�i1888�j�U���ɉO�X�S�����̐V���ɂ����݂̏ꏊ�Ɍ��Ă������ł��B |
| �@�@�Ƃ��낪�����S�R�N�i1910�j�Ɍ����s���̏o�őS�Ă��Ă��܂��A���N�̖����S�S�N�i1911�j�ɏv�H���ꂽ���̂���������O�X�S�����ł��B�ؑ��������ʼn��ɒ����`�ł��B |
 |
 |
�@�吳�P�T�N�i1926�j�S�������p�~����A���I�Ȏ������Ƃ��ė��p���ꂽ�肵�܂������A�����W�N�i1996�j�Ɏs�w��d�v�������ƂȂ����ہA�C������Č��J�����悤�ɂȂ�܂����B |
���{�L���X�g���c��������
�ɂق肷�Ƃ��傤��������Ȃ����傤����
�Q�n�������s�����R�|�P�X�|�P�O
Tel 027-381-0680
| �@���{�L���X�g���c��������͖����P�P�N�i1878�j�n�����ꂽ��J�Α���̔���������ł��B���u�Б�w�n�n�҂̐V������蓒�Y�ȂǂR�O�l����������Ƃ���ł�����܂��B |
 |

 |
�@���̋���̗�q���́A�V�������V�R�O���N���L�O���Č��Ă��u�V�����L�O��v�Ƃ������Ă��܂��B�吳�W�N�i1919�j�Ɍ������ꂽ�����̊O�ς͑�J�Α���œ����ɂ̓X�e���h�O���X���͂ߍ��܂�Ă��܂��B |
| �@�Q�n���ŏ��̃L���X�g����ł���ƂƂ��ɁA���{�l�̎�őn�����ꂽ���{�ŏ��߂Ă̋�������ł��B |
 |

�C�_��
��������
�Q�n�������s�����T�U�P
Tel 027-385-3899
| �@�C�_���͏����L�̎��Ƃ��ėL���ł��B�C�_���̏Z�E���������c�J�̍������̏����ω������������̂ł��B |
 |
 |
�@�́A�F�����̈�ɒ��F��������Ɏ��ɏo������J�ɂ����Ă��܂��������ł��B���̎��Ɉ�C�̔L�����ꂽ�����ł��B |
| �@���̔L�͕Ў���グ�Ċ����̕��܂ňē����Ă��ꂽ�̂ʼnJ�����̂��������ł��B���ꂪ�����ω��E�������̗R���ł��B |
 |

 |
�@�������̏����L�ɂ��ȂA��̒����Ɠ��̏����L���̔�����Ă��܂��B�����ɐ��A�Ɠ����S�A��ʈ��S�Ɍ䗘�v�̂��鎛�Ƃ��ĐM����Ă��܂��B |
| �@�����ɂ��铌���200�N�O�ɖ��卡��Ƃɂ���Č��Ă�ꂽ����ڒz�������̂������ł��B |
 |
 |
�@�����ɂ͓w�͎q���ɉh�̞Ёi����j�̖ȂǁA�Ö���A�l�G�܁X�A�Ԃ��炫����邻���ł��B |
���юR�B����
���傤���܂�
�Q�n������s�@�����Q�X�U
Tel 027-322-8800
 |
�@�́A��^���ʼnO�X��ɗ���ė�������ꗹ�s�҂��B����t�̑����Ă����Ɉ��u�����̂����юR�B�����̋N����ł��B |
| �@���\�P�O�N�i1696�j�A�O��������������ˌ������ɂ��肢���āA�����̓n���m�u�S�z�T�t�v�i�����j���}���T�̓���Ƃ��āA���̎����J���������ł��B |
 |
 |
�@���ʕ��Ђ������Ƃ����k�l����_�i�������k�C����아���i�ق������ꂢ�ӂ���j�ƒB����t���J���Ă��܂��B |
| �@�B�����́A����q�̉��N�B���̐��܂ꂽ���Ƃ��Ēm���Ă��āA���X�́u����܁v���Ղ��Ă���u�B�����v������܂��B |
 |
 |
�@�Q�n���o�g�̗�㑍���̂���܂Ȃǂ������Ă���܂����B |
| �@���̎��ӂ́u����܂̗��v�Ƃ����A���{��̂���܂̎Y�n�������ł��B |
 |
 |
�@���N�P���U�A�V���ɊJ����邾��s�͗L���ł��B�����ɂ�������̉��N�B���̘I�X���������сA�Ɠ����S�A�����ɐ��Ȃlj��N�����߂ĒB�������߂ɂ���l�œ��킢�܂��B |
| �@���肾��܂͏��юR�B�����X�㓌���a���̓`���Ő����ɋꂵ�ޔ_���̕��ƂƂ��Ă���܍����R���F�ܘY���n�߂����Ƃ���n�܂��������ł��B |
 |
 |
�@�����́A�}���͒߁A�@������q�Q�͋T������킵�A�ƂĂ����N�̂悢��̕�������܂ł��B |
| �@���юR���ӂł͐����P��̂���s�ɂނ��A�V�O���قǂ̉ƂŔN�ԂP�T�O���̂���܂����Y����A�S���̂W�����߂Ă��܂��B |
 |
���蔒�ߑ�ω�
���������тႭ����������̂�
�Q�n������s�Ό����Q�V�P�O�|�P
Tel 027-322-2269
.JPG) |
�@����s�̐����ɍL����ω��R�u�˂̒���ɂ͔��ߑ�ω������т������Ă��܂��B�����P�Q�N�i2000�j�ɂ͑��Ƃ��Ă͏��߂č��̓o�^�L�`�������ɑI�肳�ꂽ�����ł��B |
| �@����s�X�n�������낷�ω��l�́A���a�P�P�N�i1936)�Ɏ��Ɖƈ��ێO�Y�ɂ���Č������ꂽ�����ł��B���ł͍���̃V���{���Ƃ��Ďs���Ɉ�����Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�����͂S�P�D�W���Œn��X�K���Ă̑傫�Ȃ��̂ł��B�����ɖ������_�a�ȕ\������Ă��܂��B |
| �@�ٓ��͂X�w�ɕ�����Ă��āA�Q�O�̂̕��������u���Ă��邻���ł��B���������̕ӂ܂ŊK�i�ŏオ�邱�Ƃ��ł��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�ω����̎���ɂ͖�R�O�O�O�{�̍��̖��A�����Ă��ďt�ɂ͉Ԍ��q�œ��킢�܂��B |
������
����݂��ł�
�Q�n������s�Ό����Q�S�O�P
Tel 027-323-3214
 |
�@�ω��R�u�˂̓�[�Ɉʒu���鐴�����́A�����Βi�ƃA�W�T�C�̔��������Ƃ��ėL���ł��B�n���͑哯�R�N�i808�j���c�����C�����Γ����̍ہA���̒n��K�ꋞ�s�̐��������犩�����Đ폟�F��ƕ��^���v��������̂��n�܂�Ɠ`�����Ă��܂��B |
| �@���̎傩��삳�ꌳ�\�T�N�i1692�j�ɂ͍���ˎ�����d��������M�ɖ����āu������ω����o�m�}�v�Ɓu�\�y�g��w�m�}�v�̂Q�ʂ̑�G�n���ω����ɕ�[����Ă��܂��B |
 |
 |
�@���s�̐��������v�킹��N�₩�Ȏ�F�̘O�傩��͎s�X����]�ł��܂��B�����ɂ͈�ĖF�P�̌��z�P�U�ʂ���L�������Ă��܂��B |
�Q�n���썑�_��
����܂���������
�Q�n������s�敍���Q�O�O�O
Tel 027-322-6309
 |
�@�Q�n���썑�_�Ђ͖����ېV�����Q�����E���܂ł̌Q�n���o�g�W�̏}���̉p��S���V��]�����J���Ă��܂��B���̐_�Ђ�����s�ɑn�����ꂽ�̂́A���a�P�U�N�i1941�j�ł����B |
| �@�����_�Ђ̕��Ђ�����s�Ɍ�������邱�Ƃ����肵�������ɁA�S���I�ɖ����_�Ђ̕��Ђ��P�{���P�Ќ������悤�Ƃ����v�悪�������ꂽ���߁A�O���s�������������җ�ȗU�v�^�����J�n���܂����B |
 |
 |
�@���̌�A������b���w�肷��썑�_�Ђɂ͎Ж��ɕ{������t���A�P�{���P�Ђ������Ƃ��܂����B |
������
�����������傤����
�Q�n������s�������P
Tel 027-321-1257 ����ό�����
.JPG) |
�@ �����̒n�ɂ́A�������㖖���ɍ����a�c�`�M���z�邵���a�c��ƌĂ��邪����܂����B��������ɂȂ�Ƙa�c���͊֓��Ǘ̂̏㐙���ɋA�����Ă��܂������A�i�\�S�N�i1561�j���a�c�Ɣɂ͕��c�M���ɏ]���܂����B���̌�A���q�̘a�c�M�ɂ́A�k�����ɑ����A�V���P�W�N�i1590�j�ɖk�������łԂƗ̒n�͖v������܂����B |
| �@����ƍN���֓��̗̎�ɂȂ�ƍ���s���ӂ͓���l�V���̈�Y�E��ɒ������P�Q���œ���������˂𗧔˂��܂��B�������֏������Ƃ��܂������c���R�N�i1598�j�ɍ����Ɉڂ��Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@ ���̒n�͒��R���ƎO���X���̕���_�ɓ������ʂ̗v�Ղł��B�����͓�k�ɗ����͐�����R�v�Q�ɁA���a�c�����n�̈ꕔ�Ɏ�荞�T�^�I�ȕ���ł��B |
| �@�{�ۂ𒆐S�ɐ��̊ہE�|�s�Ɨ֊s���ō\���A��̊ہE�O�̊ۂ͒�s���꒣�Ŗ{�ۂ��͂ތ`�������A�X�ɁA���\���ƌĂ��x�Ɠy�ۂŏ鉺�����͂ލL��ȏ��ł����B���֏邩�瑽���̍\�z�����ڂ��A�S�Ă̏�s�����������̂́A�����S�N�i1664�j���Ƃ����Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�@��ɒ����͂Q�N�]��ݏ邵�܂������A�c���U�N�i1601�j�A�ߍ]���a�R��i�F���s�j�֓]�o���܂����B���̌�A����ƁA�˓c�����ƁA���䏼���ƁA�����ƂƏ�傪����ւ���Ă��܂��B |
| �@ ���a�T�N�i1619�j�ɓ��邵�������d�M�͏�̉��C�ɒ��肵�܂����B�Ȍ�A�R��V�V�N�Ԃ������đ���C����ߑ��s����������܂����B ���i�P�O�N�i1633�j�A�R�㏫�R����ƌ��̖��ɂ��A���̏�ɗH����Ă�����̓��쒉���������Ŏ��Q���܂����B |
.JPG) |
.JPG) |
�@ ���̌�A����g�ۂƂƂ��ɂT��j�g�����̕Иr�ł���������(����E��͓�)�P��A�U��Ɛ�E�V��ƌp�̑��p�l�̊ԕ��F�[�Ƒ����A�ēx�A�����P�傪�W��g�@�ɗp�����A�V���Ƃ��ĕԂ�炫�ݏ邵�܂����B���̂܂���(����E��͓�)�Ƃ͂P�O��A��P�T�O�N�����Ė����ېV���}���Ă��܂��B�����S�N�i1871�j�p�˒u���ɂ�荂���͔p��ƂȂ�A�������͈ڒz�A�j�p����Ă����܂����B |
���Ӕ�L�O��
�����Ђ��˂�
�Q�n������s�g�䒬�r�P�O�W�T
Tel 027-387-4928
.JPG) |
�@���Ӕ�́A�ޗǎ��㏉���̘a���S�N�i711�j�ɋg�䒬�Ɍ��Ă�ꂽ�Δ�ł��B�{�錧�� ������i�������傤�Ёj �E �Ȗ،��� �ߐ{������i�Ȃ����ɂ݂̂���Ёj
�ƂƂ��ɓ��{�R�Ô�̈�ɐ������Ă��܂��B |
| �@�����̂R�̌S����R�O�O�˂����A�V�������ӌS��݂������Ƃ��L����Ă��܂��B���a�Q�X�N�i1954�j���w����ʎj�ՂɎw�肳��܂����B |
 |
.JPG) |
�@�a���S�N�i711�j�R���X���ɓ����̌Q�n���ł͂P�S�Ԗڂ̌S�̑��ӌS���a���������Ƃ��L���L�O��Ȃ̂ł��B |
| �@�R�m���A������ƂƂ��ɏ��R��Ə̂���Ă��܂��B���̂R��͓���S���̔�r�I�߂��͈͂ɑ��݂��A���莞�����߂������ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@��͒n���ł͓V���A���ӐƌĂ�鋍������i�����Ԃ�������j �Ƃ����d���̍�����o���Ă����Ă��܂��B |
| �@���Ӕ�̍����͂P���Q�Vcm����A���͂U�Ocm�A���邻���ł��B�蕶�́A�a���Ɗ����������荇�������̂ŁA�U�s�W�O�����������Ă��邻���ł��B |
.JPG) |
.jpg) |
�@�l�p���̔�g�̏�ɁA����� �u�}�v �������
���܂��B�}�͍����Q�T�����A�����W�W�����̕��`����ł��B���̂͊ۂ݂�тт������̂ŘZ���̉e�����Ă���Ƃ��A�����k鰂̏����ɒʂ���Ƃ������Ă��܂��B |
| �@���̗D�ꂽ���͍̂��������̏��ƒB�Ɉ��D����A���Ӕ�L�O�قł́A���̂����ꂽ���̂Ɋւ��钆�����̑�{�����W������Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@����r��̎��͌Â����璍�ڂ���Ă��܂��B�n���ł́A�̂��碗r���v��̕�Ƃ���A��r���ܣ�ƌĂ�Ő��q����Ă��܂��B |
�Y���_��
�͂�Ȃ���
�Q�n������s�Y�����W�S�X
Tel 027-374-9050
 |
�@�Y���_�Ђ͐Y���R�����ɂ���A�P�S�O�O�N�̗��j������n�ł��B ���̐_�Ђ͗p���V�c���N�܂�X�Q�V�N�̑n���Ɠ`�����Ă��܂��B�Ɛ��̐_���J��R�x�M�̖{�R�Ȃ̂ł��B |
| �@�Õ�����ɎR�[�������Z�n�߂��ɂ܂��Ă����Y���_�Ђ��A�V��A�^���̖����k�ɂ��A����ł��������Y���_�Ђ̊��֕��ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B |
 |
 |
�@�Y���_�Ђ͉����T�N�i927�j�ɕҎ[���ꂽ���쎮�_�����ɋL�ڂ��ꂽ��썑�P�Q�Ђ̓��Z�m�{�Ƃ��đ��������A�㐙���M�A���c���k�����A�^�c���Ƃ��������̎��x�z�҂ɐ��h����܂����B |
| �@�Y���_�Ђ͐퍑�������ɂȂ�ƍ���E���u���ꂸ���ނ��܂����A�]�ˎ���ɓ���V�C�m�����ċ����A�c���P�X�N�i1614�j�ɂ́u��썑�V��@�Y���R�ޓa���@�x�V���v�����z���ꊰ�i���̔z���ƂȂ�܂��B���{������삳��ĂюЉ^���������܂����B |
 |
 |
�@�]�ˎ���ɓ���ƐY���_�Ђ͏C���m�����łȂ��u�Y���u�v�ƌĂ�閯�ԐM�����ӂ̔_�����ɐZ���������Ƃ�����A�����̎Q�q�҂��K��R���̎ЉƂ͂R�O�O�O�V���ɉh���ɂ߂��Ƃ����Ă��܂��B |
| �@���m����ł��������_��i�����������j�͍O���S�N�i1847�j�㓏����Ă��܂��B�����͍�ʌ��{���̊֍��C���A�_�������܂ł͓�͎m���������ĉ^�c�̍�Ɠ`�����Ă��܂����B���_��͍��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ���_�� |
 |
�@�c���S�N�i1868�j�R���A�_�������߂��o����A�����I�Ȃ��͔̂r�˂���܂����B���̂Ƃ��A�Y���_�Ђ��畧���F�͈�|���ꂽ�����ł��B���̎O�d���͖����Q�N�i1869�j�ɍČ����ꂽ�����ł��B���������̂P�Um�̓��ł��B���݂͐_��a�ƌĂ꒿�����_���J���Ă���O�d���Ȃ̂ł��B |
| �O�d�� |
| �@���N��ƌĂ�鐅���͂�邱�Ƃ��Ȃ���ł��B�Y���_�Ђ͉J��̐_�Ƃ��ėL���ł��B�J��ɂ͂����̐������������Ă����̂ł��B |
 |
| ���N�� |
 |
�@���������Ƃ������̌Ö������R����o��ƁA��₪��Ȃ鋫���Ɏ���܂��B�Q���̐Βi�͑ۂނ��A�Ƃ���ǂ���ɂ��т�������_��I�ł��B |
| �@�r�q�i�݂����j�̑�ł��B�r�q�͐_�ɋ�����_����������Ȃǂ̊�̂��Ƃł��B��̗����Ă��闼�e�̊��r�q��ƌĂсA�������痎���Ă����Ƃ����Ӗ��ł��B |
 |
| �r�q�̑� |
 |
�@���_�͉̂~���^�̊�ɐl�̓����̂����悤�ȑ傫�Ȋ�₾�����ł��B |
| �@�S�O�O�N�O�A���c�M�������֏�U���̍ہA��𗧂Đ폟�F��������Ɠ`�����鐙�̋��ł��B�O�{�A���A������T�Tm�A�ڒʂ����X�D�Vm�A����N��U�O�O�N�O��Ƃ����Ă��܂��B���a�W�N�i1933�j�ɍ��̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ��� |
 |
�@�o����ł��B�����Q�N�i1855�j�Ɍ��Ă��Ă��܂��B��������̌����őf���炵�������ł��B���̒����␅�n�悪�`����Ă��邱�Ƃ���o����ƌĂ�Ă��邻���ł��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �o���� |
| �@�o����̍��ɂ��鋐��͖g��i�ق�����j�ƌĂ�Ă��邻���ł��B�ʖ����[�\�N��Ƃ������Ă��邻���ł��B |
 |
 |
�@�_�K�a�i�݂䂫�ł�j�͈����U�N�i1859�j�Ɍ��Ă��Ă��܂��B�T���W���ɖ{�Ђ�肱�̐_�K�a�ɐ_�`���n�䂵�A�P�T���ɊҌ䂳���܂ł̊��ԊJ����A�Q�q���邱�Ƃ��ł��邻���ł��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �_�K�a |
| �@�Y���_�Ђ̖{�ЁE���a�E�q�a�͕����R�N�i1806�j�ɍČ����ꂽ�����ł��B�{�Ђ͌�p��̑O�ʂɐڂ��Č��Ă��≜�Ɍ�_�̂��J���Ă��܂��B�������̌����͎�ƍ�����Ƃ��ėv���ɋ����⑽�ʂȍʐF���{����Ă��܂��B��������̖{�ЁE���a�E�q�a�͍��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| �Y���_�Ж{�� |
 |
�@���c�Ћy�ъz�a�͖{�ЁE���a�E�q�a�̌������č��Ɍ����Ă��܂��B���c�Ђ͌��̖{�n���ŁA�c���N�ԁi1600�N���j�̌��z�ł��B�ڑ�����z�a�͕����P�P�N�i1814�j�̌��z�ł��B |
| ���c�Ћy�ъz�a |
| �@��b�͖{�ЁE���a�E�q�a�Ɠ��������ɂ����A���ꉮ����Ō��q�◓�Ԃ̒������݂��܂����A�S�̓I�ɑ����͍T���߂ɂȂ��Ă��܂��B���c�Ћy�ъz�a�͍��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| ���c�Ћy�ъz�a |
 |
�@�Y���_�А_�y�a�e�̓S���U�ɂ́A���g���ɂP�X�W���̖������c���Ă��܂��B�����R�N�i1323�j�ɑ���ꂽ�Q�n�����ŌÂ̌ÓS���U�ł��B�Q�n���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �S���U |
| �@�_�y�͐_�ɕ�[���邽�߂ɕ�����̂ŁA�_�y�a�͖{�a�ɐ^�������ʒu�Ɍ��Ă��Ă��܂��B���a���N�i1764�j�̍Č��ł��B���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
 |
| �_�y�a |
�Y����
�͂�Ȃ�
�Q�n������s�Y����
Tel 027-374-9408 �Y�����X�g�n�E�X
 |
�@�Y���͔������Y���̎R���݂Ɉ͂܂ꂽ�W���P�P�O�O���̕ʓV�n�A�Y���ΎR�̃J���f���ɐ������܂��Ăł����ł��B |
| �@������P�����A��k�P�D�R�����̌��ʌ^�ŁA���͖͂�T�����ł��B�̂�т�ƕ����g�e�n�Ԃ��l�C������܂��B�Y���x�m���Ζʂɉf�����p�͐�i�̂ЂƂ��Ƃł��B |
 |
 |
�@�l�G��ʂ��Ă�������̊ό��q�œ��키�Y���̈�т͌����Y�������Ƃ��Đ�������Ă��܂��B�Y���͌Â��͈ɍ��ۏ��ƌĂ�Ă��������ł��B |
| �@�ΔȂ͍���O�}�q���̂����ΔȂ̏h�̃��f���ɂȂ������Ƃ�ł��B�ɍ��ۉ�����߂��̂Ŕ����n�Ƃ��Đl�C������܂��B |
 |
�����c�x��������
���イ�����Ƃ݂������������傤
�Q�n���x���s�x���P�|�P
Tel 0274-64-0005
 |
�@�����U�N�i1859�j�̊J�`�ɂ��A���{�̐����́A�i���s�����Ă������Ċe���ɗA�o���ꊈ����悵�܂����B���l�ɂ́A�e���̖f�Տ��Ђ�������ׂ܂����B |
| �@�Ƃ��낪�i���̂悭�Ȃ��e���Ȑ������o���s�]���܂����B�����V���{�͉��Ă̐����ɗ��Ȃ����i�Y���邽�ߑn�ݐӔC�҂ɔ����Ւ���C�����A�m���̐����̋@�B�̓������ċߑ�I�Ȑ��Y�������m�����悤�Ƃ��܂����B |
 |
 |
�@�t�����X�l�|�[���E�u�����i�Ɏw������A�Ɠ��������Y������ł��������̕x���Ɋ��c�̐����H�ꂪ���݂���܂����B�����T�N�i1872�j�V���H�ꊮ�����P�O�����瑀�Ƃ��J�n���ꂽ�����ł��B |
| �@�u�����i�Ȃǂ̊O���l���ԃ��C��������ł���̂��Ⴂ���̌�������ł���ȂǂƉ\����A�H�����v���悤�ɏW�܂�Ȃ����������ł��B |
 |
 |
�@���{���߂ɂ���Ďm���Ȃǂ̎q�����W�߂��O���ɏ���������ł��B�����Ă����ŏC�s�����q���������̒n���ɖ߂������ɂ͋@�B���������Y�̎w���҂Ƃ��Ċ��������ł��B |
������
��イ������
�Q�n���x���s�x���P�O�X�R
Tel 0274-62-0528
.JPG) |
�@�������̕�n�ɂ́A���J���ɕ��U����ĂS�W�l�̋����c�x��������H���̕悪����܂��B�����U�N�i1873�j�U���ɂ͑S������W�߂�ꂽ�H���͂͂T�T�O�l�������������ł��B |
| �@�x��������͊��c�̖͔͐����H��Ƃ��āA�����T�N�i�P1872�j�P�O���ɑ��Ƃ��J�n���܂����B�����ċ@�B�ɂ�鐻���̋Z�p�K���̂��ߑ����̏������W�߂�ꂽ�̂ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�����Q�U�N�i1893�j�܂łɕs�K�ɂ��ĕa�C�ȂǂŖS���Ȃ����ҏ����͂U�S�l�قǂ��āA�唼�͉����ً��̒n����x���ɂ����l�����ł����B���̗������ƊC�����ɖ������ꂽ�����ł��B |
| �@�������ŗL���ȕ��͔� (�����Ёj�ƞ����ł��B�ΓD�Њ�Ƃ������ޗ��Ƃ����A�����P�S�O�����A���S�T�D�T�����̒����`�̔�͌Q�n���̗L�`�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�ّ��E����^���Ƃ��̋��������ܗ֓��`�ɑg�ݍ��킹�Ă���̂������ł��B�ّ��E����̕�g�^����������q�i�A�A�r�A���A�E�[���A�P���j���ܗ֓��`�ɑg�ݍ��킹�Ė���ō���ł���̂ł��B |
| �@�厡�O�N�i1364�j�\�C�K�����v�u�t�C�v�u�����v�̖�������܂��B�������Ƃ���₷�茸�������Ȃnj�������܂���B�Y��ɒ���ꂽ��ł��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@��y�@�̗������͌c���P�V�N�i1612�j�{��h�i���x���s�{��j�ɂ���܂����B�V�c�J���̂��߂��̒n�Ɉڂ��������ł��B���̎��̒����J�R�͎�_���y�ŁA��Q���͂̂��ɑ��c�̑���@�̊J�R�ƂȂ����ۗ��i�ǂ��イ�j��l�����������ł��B |
| �@�������̞����i�ڂ傤�j�͑�����P�P�Q�����A���a��U�T�����Ŏ�������̒����Ɛ��肳��Ă��܂��B���a�Q�U�N�i1951�j���w��d�v�������ɂȂ��Ă��܂��B |
.JPG) |
�{�����
�݂₴����������
�Q�n���x���s�{��R�Q�X
.JPG) |
�@�u���̂̂ߓ��v�ƌĂ��Z�p���������낹��{������ł��B�����Q�O�N�i1879�j�{��̕x���ł�������؏�쎁�����������̂ł��B�c�c�W�ƃ��~�W�𒆐S�A�����Ă��܂��B |
| �@���a�R�O�N�i1955�j�ɕx���s�Ɉڊǂ���A�{������ƂȂ�܂����B�����ɂ͏d�v�������̋��Ζ؉Ƃ��ڒz����Ă��܂��B���⒃��Ȃǂ��Â���Ă��邻���ł��B |
.JPG) |
���Ζ؉ƏZ��
���イ���Ă������イ����
�Q�n���x���s�{��R�Q�X
Tel 0274-62-1511
.JPG) |
�@���̉Ƃ͂��Ƃ͎s���_�_���Ɍ��Ă��Ă������̂ł��B�Ԃ������̖��ƂƂ��Ă͑S���I�ɂ��ł��Â����z�����Ő퍑����̑�i�V�N�i1527�j�̌��z�������ł��B |
| �@���ނɎc���ꂽ�㐢�̖n���ɑ�i�V�N�̌��z�ƋL����Ă��������ł��B���̏��L�҂ł������Ζ؉Ƃ̐�c���A�퍑����ɐ_�_���ɂ�������R��̏��ł������Ƃ����Õ������`�����Ă��܂��B�@ |
.JPG) |
.JPG) |
�@�؍ȑ���̔��Βu�����̖��ƂŌ��s�P�T�D�P�T�Q���A���ԂV�D�T�V�U�����邻���ł��B���ނ̑g�ݕ��͗Y��ŗ͋��������̓������悭�c���Ă��܂��B |
| �@���a�S�T�N�i1970�j�U���A���̏d�v�������Ɏw�肳��܂����B���a�T�Q�N�ɋ{������Ɉڐ݁A�ۑ��C���̂�����ʂɌ��J����Ă��܂��B |
.JPG) |
�ёO�_��
�ʂ���������
�Q�n���x���s��m�{�P�T�R�T
Tel 0274-62-2009
| �@�ёO�_�Ђ͐�N�]���o���ÖɈ͂܂ꂽ�����ȐÂ����̒��ɂ���܂��B�������璷���K�i���������Ƃ���Ɍ������Ă��܂��B |
 |
 |
�@�ёO�_�Ђ̓��������āi���炩�˂����Ƃ��낤�j�͍����R�X�T�����̈�̓������Ăł��B�c�����N(1865)�ɐ��삳��c���Q�N�ɂ����Ɍ��Ă��܂����B�n���̗{�\�_�Ƃ��͂��ߏ�B�A�]�ˁA���l�̐����A�����l�Ȃǂ���S�V�X�O�����̌��[�����W�܂��������ł��B�x���s�w��d�v�������ł��B |
| ���������� |
| �@�ёO�_�Ђ͂T�R�P�N�ɕ��_�ł���o�Î�_ (�ӂʂ��̂���) �Ɣ_�k�̐_�A�䔄��_ (�Ђ߂�������) ���J�����̂��n�܂�ŁA�P�T�O�O�N�߂��̗��j������܂��B |
 |
 |
�@���݂̎Гa�͂R�㏫�R����ƌ��̖��ɂ���Č��Ă�ꂽ�����ł��B�]�ˎ��㏉���̎��h��ŋɍʐF�̎Гa�͍��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �@���V�c�̎���ɕҎ[�̎n�܂������쎮�̐_�����ɂ͖��_��ЂƂ��ė��Ă��ČÂɂ����̎��ォ��̖��Ђł��B��썑��V�{�Ƃ��Ē�����Ƃ킸���h�����߂Ă��܂����B�@ |
 |
 |
�@�{�a�E�q�a�E�O��͊��i�P�Q�N(1635�j�R�㏫�R�ƌ����Č����A���̌㌳�\�P�P�N(1698)�ɂT�㏫�R�j�g�̎���̑傪����ȏC���������Ƃ������Ƃł��B |
| �@�V���V�c�̎���ɏ��̕i�ق��ׂ��j�������������ł��B�Ƃ͓V�c�̖��ɂ��_�Ђɕ�����邱�ƂŁA���������ޗǂ̓s�ɂ܂ŊёO�_�Ђ̑��݂��m���Ă����������@�ł��܂��B |
 |
 |
�@�Г`�ɂ͍�{�i�����݂̂�j�i�����s�j�ɕ������镔�����A���_�ł���o�Î�_���J��A���̍�{�̓���A�H���u�����J�i���������������߂����Ɂj�ɎЂ��߂��̂����ՓV�c�̌��N�i531�j�Ƃ���A���ꂪ�n���Ƃ���Ă��܂��B |
| �@�����ɂ͓������i�Ƃ��������j�Ƃ���吙������܂��B����P�Q�O�O�N�Ƃ����Ă��܂��B�V�c�Q�N�i939�j���썑����R�i������s�j�̏�員���G��(�U�����G���j�������哢���̍ہA�����ɎQ�q���Ď����Ɠ����N�̂R�U�{��[�������̈�{���Ƃ����Ă��܂��B |
 |
| ������ |
�����s�˓@��
�Ȃ̂������͂�Ă�����
�Q�n���x���s�����s�P�S�Q�T
Tel 0274-63-0053 �x�����Z
 |
�@�����s�˓@�Ղ͌Q�n�����x�����Z�̒��ɂ���܂��B�����s�˂͏�B�O�c�������߂Ă��܂����B�~�n���ɂ́A�V�ۂP�R�N�i1843�j�Ɍ��Ă�ꂽ�˓@�̈ꕔ���c��u��a�v�ƌĂ�Ă��܂��B |
| �@�x�����Z�̃V���{���ƂȂ��Ă����́u����v�ƌĂ�u��a�v�̒���ł��B���݂����k�̒ʗp��Ƃ��Ďg�p����Ă��܂��B |
 |
 |
�@�u����v�Ƃ����Ăі��͉���@��ƍ]�ˉ��~�̐Ԗ�i����j�ɑ��Ďg���������ł��B |
| �@�����s�ˎ�͉���̑O�c�Ƃ̕��Ƃ������Ă��܂����B��B�ɂ͖��{�̑�����n�⏬�˂���������A�����ːD�c�� (���a������͏������j�Ȃǂ�����܂����B |
 |
 |
�@�����s�˂̔ˑc�́A����˂̔ˑc�E�O�c���ƂT�V�̎��̏��q�A�ܒj�̑O�c���F�ł��B���̐w�ŗ��F�͓���G���ɑ����ďo�w�����̌��ɂ��A���a�Q�N�i1616�j�A��B�Êy�łP����^�����A�����s�ɐw�����\���܂����B |
| �@���˂ŁA�V�ۂ̑�Q�[�Ȃǂ̓V�Ђ��������A�{�Ƃł������O�c�˂̍����I�������āA�悤�₭�������Ă����悤�ȏ����Ȕ˂������悤�ł��B |
 |
 |
�@�Ȍ�A�����s�˂͈�Ǝx�z�ŁA��B�O�c�ƂP�Q��̐w���Ƃ��Ė����ېV�܂ő������܂����B |
���`�R
�݂傤������
�Q�n���x���s���`��
 |
�@���`�R�͐ԏ�R�E�Y���R�ƂƂ��ɏ�юO�R�Ƃ��Q�n�����ے�����R�̈�ł��B�啪���̖떃�k�A���쌧�̊����k�ƂƂ��ɓ��{�O���̈�ɂ��������Ă��܂��B |
| �@���̖��`�R�́A���_�R�i���n�x�P�P�O�S���j�A�����R�i�P�P�O�S���j�A���{�R�i�W�T�U���j�̂R��Ȃ�\���`�ƁA�G�X�q��i�P�P�P�V���j�A�J�}�R�i�P�P�U�Q���j�Ȃǂ���Ȃ闠���`�Ƃɕ�����Ă��܂��B |
 |
 |
�@�Ζ�Q�̂���\���`�͌������`�����ɂȂ��Ă��܂��B���`�R�͖��`�r�D���v������������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| �@���`�R�͉ΎR���o���ō\�������Â��ΎR�̂Ƃ����A���N�ɂ킽�镗���A�Z�H�ɂ���Ċ�̌����������c��A����������悤�Ȋ��y��̎R�e�ɂȂ����悤�ł��B |
 |
 |
�@���̂悤�ȓ����͑�P�����S�̐Ζ�A�J�j�̉����A��C���낤������Ȃǂ�����Ζ�Q�ɂ悭�\��Ă��܂��B |
| �@���_�R�̍����ɂ���O�p�`�̉s���₪�P�P�O�S���̑��n�x�ł��B�E���̎R���ɖ��`�_�Ђ̉��̉@������܂��B���̉��ɑ�̎�������܂��B���[�̓o�������ł��B |
 |
 |
�@�W�T�U���̋��{�R�́A�܂��ɓ��{�ŃV�M���A���b�N�ł��B���̉E�ɂP�P�O�S�������R����������ɉE�����_�R�ł��B |
���`�_��
�݂傤������
�Q�n���x���s���`�����`�U
Tel 0274-73-2119

 |
�@���`�_�Ђ́A���Ɖ��Ŗ��������`�R�̎�����_�R�̓��R�[�ɂ���܂��B�����ɂ����閭�`�_�Ђ̐Δ�̂܂��ɂ́A����Q�O�O�N�]��ɂȂ�V�_�������t�ɂ͍炫����邻���ł��B |
| �@���`�_�Ђ̑n���͐鉻�V�c�Q�N(537)�ƎЋL�ɋL����Ă��邻���ł��B���ݖ��`�_�Ђɂ͍��w��d�v�������̊G�����Ȃǂ�������������Ă��܂��B |
 |
 |
�@�����ɂ͍��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��鑍�傪�����Ă��܂��B�]�ˎ���ɂ͔��_�R�Γ����̐m���傾���������ł��B�_�������ɂ�葍��ɉ��߂�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B |
| ���� |
| �@�R�ԂQ�ԒP�؍ȑ���̗��h�ȑ傫�Ȗ�ł��B���i�Q�N(1773)�Ɍ��Ă��Ă��܂��B�����͍ŋ߂܂Şw�畘�ł������A���a�U�O�N���畽�����N�i1989�j�̏C���ɂ��n�����̓����ɉ��߂��܂����B |
 |
| ���� |
 |
�@�V���̐����鋫���Ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă�����̑咹���Ɠ��Ă�����܂��B���j�ƐM����肩���Ă���悤�ł��B |
| ���� |
| �@�咹���̐_�z���ɂ́A���������\�N�\�g���A�O�V������i�e���Ǐ����V�Ə�����Ă���Ƃ������Ƃł��B |
 |
| �咹�� |
 |
�@�咹���̋߂��ɍ��̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��閭�`�_�Ђ̑吙�̎q��������܂��B���a�W�N�i1933�j�ɓV�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ�吙�͘V�̂��ߐ��サ���a�S�U�N�i1971�j�P���̑䕗�ɂ��|�������ł��B |
| ���`�_�Ђ̑吙 |
| �@��錧�̍����֓��і؈���ɂ��̐��̌��S�ȕ䂪���ŕۑ�����Ă��܂����B������Q�n���ыƎ����ꂪ���炢�吙�̎q�������A�͂������̂������ł��B |
 |
| ���`�_�Ђ̑吙 |
�g�ȑ]��
�͂�������
 |
�@���̏d�v�������ł��鋌�{�Ђ̔g�ȑ]�Ёi�F���a�j�ł��B�{�a�A���̊ԁA�q�a�̍\���ł��B�R�O�O�N�ȏ���O�̌����ł��B |
| �g�ȑ]�ЋF���a |
| �@�ŋ߂܂Ŗ{�a�͔g�ȑ]�ЂɁA�q�a�͐_�y�a�ɂȂ��Ă��܂����B��N�V�ނ�⑫���č��̊Ԃ����ڒz��C�����A���Ԃɕ����������ł��B |
 |
| �g�ȑ]�� |
 |
�@���`�_�Ђ͌Ñ�͔g�ȑ]�i�͂����j�_�ЂƌĂ�Ă����悤�ł��B�u�O����^�v�̒�ό��N(859)�̏��Ɂu�����c���Z�ʏ�g�ȑ]�_�]�܈ʉ��v�Ƃ���̂��ł��Â��L�^�������ł��B |
| �g�ȑ]�� |
| �@���Ƃ͔g�ȑ]�̑�_�Ƃ����A��ɖ��`�Ɖ��߂��Ɠ`�����Ă��܂��B�]�ˎ���ɂ����Ă͗�㓿�쏫�R����������q����ȂǁA�Â�����i���̍����_�ЂƂ��ĕ��m�▯�O����M����Ă��������ł��B |
 |
| �g�ȑ]�� |
���@��
 |
�@�����Βi�̏�ɂ͓��傪�҂��\���Ă��܂��B���̌��������̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
| ���� |
| �@���s�P�ԁE���ԂP�ԁE�ȕ��͓��j���̕����̖�ŁA�ѓ��̖ؕ@�͋e�Ԃ��Ē��A�˂̔ʂ͔������̖P���̒����Ȃǂ��{����Ă��܂��B |
 |
| ���� |
 |
�@���Ǔc���Ƌ{�̓���ƂƂ��ɁA�����ł͍ł��D�ꂽ����Ƃ̕]���ł��B |
| ���� |
| �@�����̎Гa�͍]�ˎ���̕���Q�N(1752)�ɑ���z����A���a�U�O�N���畽�����N�i1989�j�ɂS���~�̔�p�������ď��a�̑�C�����s��ꂽ�����ł��B |
 |
| ���� |
�{�a�A���a�A�q�a
 |
�@�{�a�A���a�A�q�a�͑�\�I�Ȍ������ō��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�{�a�͓��ꉮ����ŁA���s�R�ԁA���ԂQ�ԁA�P�d�̂��ł₩�ȎГa�ł��B |
| �{�a�A���a�A�q�a |
| �@���ɖ{�a�̔Ǖ��A���ԁA富ғ��A���V��A�����A�q�a�ł͌��q���Ƃ̂Ȃ��̊C�V�����Ɏ�̂����������Ă��܂��B |
 |
| �{�a�A���a�A�q�a |
 |
�@���Ԃ�富ғ��A�e��q�Ȃǂɂ͏��ɖP���A����賂̓����A�e�ԗt���Ē��ȂǓ������Ƌ{�`���������t�̋Z�p���킩��܂��B |
| �{�a�A���a�A�q�a |
| �@�����͐�i�V��i���肠�������Ă傤�j�ɂȂ��Ă��āA�e�Ԗ��ɋe�Ԃ̋ɍʐF���{����Ă��܂��B |
 |
| �{�a�A���a�A�q�a |
 |
�@�{�a�A�q�a�Ƌ��ɍ����h�������ꉮ����ł��B�q�a�͐��ʂɐ璹�j���������A���̑O�ɓ��j���̌��q������o���Ă��܂��B |
| �{�a�A���a�A�q�a |
| �@�q�a�̗��ɂ͏�藴�Ɖ��藴�����Ȃ��Ă��܂��B�߂̒����A��ƂƂ�сA�e��q�̒|�тɎ����l���q�̒��̍�������̒����������ł��B |
 |
| �{�a�A���a�A�q�a |
 |
�@�����͔ё��ۈ��v�h�A���{�d�������Z�[�ƋL����Ă��邻���ł��B�]�˂��璤���t�A�h���t�A�D�i������j�H�A�|�����E�l�ȂǗ��������ł��B |
| �{�a�A���a�A�q�a |
| �@�{�a���ɂ���V��Ђł��B���Q�肷��ƐS�萬�A���邻���ł��B |
 |
| �V��� |
���{�l��a
 |
�@���`�_�Ђ͍]�ˎ���A��쓌�b�R���i���̍���։����{���X�䌓�т̐_�ЂƂȂ�A��㏫�R�⏔�喼���Ă����h���Ă��܂����B |
| ���`�_�Ќ�a |
| �@���`���̎w��d�v�������̖��`�_�Ќ�a�ł��B���ɋ{�l��a�Ƃ����A�Éi�T�N�i1852�j�ɍČ�����Ă��܂��B |
 |
| ���`�_�Ќ�a |
 |
�@���i�P�R�N(1636)�ȗ��A�։����{�̉B�����ƂȂ�A��o�R�̐܂ɂ́A���̌�a�ɔ����������ł��B |
| ���`�_�Ќ�a |
| �@���{�l��a�̓����ɂ͌Q�n���w��V�R�L�O���̖��`�_�Ђ̃E���W���K�V������܂����B |
 |
| �E���W���K�V |
�ӂ邳�Ɣ��p��
�ӂ邳�Ƃт������
�Q�n���x���s���`�����`�P�|�T
Tel 0274-73-2585
| �@���`�R��w�i�Ƃ������炵���i�ςɕ����ꂽ���p�فu�ӂ邳�Ɣ��p�فv������܂��B���̉w�݂悬�ׂ̗�ɂ�����p�قŕ����U�N�i1994�j�ɃI�[�v�����܂����B���a�T�W�N�i1983�j���瑱���Ă���u���`�R��`���G��W�v�̏G����ꓰ�ɓW�����Ă��܂��B |
 |
 |
�@�P�K�ɏ�ݓW�����E���W�����A�Q�K�ɓW���M�������[�A�R�K�ɓW�]�ʐ���������A�G���ʂ��Ė��`�R�̎l�G�ɐG��邱�Ƃ��o���܂��B�V���������̋��_�Ƃ��Ė��`�̕��i�ƌ|�p�������邷�ׂĂ̐l�X�̂��߂ɉ������Ă��܂��B |
���V�Ԑ_��
�Ȃ��̂�������
�Q�n���Êy�S���m�c���㏬��P�Q�S�U
Tel 0274-82-5671
| �@���V�Ԑ_�Ђ͖��`�R�̒����Ɉʒu���A���i���N�i1182�j�Ԗ��V�c�̎���ɑn�����ꂽ�ÎЂœ��{�������J���Ă��܂��B�单���V���ł�����܂��B |
 |
| ���V�Ԑ_�В��� |
 |
�@��T�Q�㍵��V�c�̒����ɂ��A�O�m�X�N�i819�j��[�������~�k���ƍO�@��t���o�Ԃ��A�卑��_�o�_��Ђ̕��ЂƂ��đn�݂��ꂽ�����ł��B |
| ���V�ԑ卑�_�В��� |
| �@�K�i��O�ɒ��V�ԑ卑�_�Ђ�����܂��B�֓��̏o�_�Ƃ��Đ��ɒm���Ă��܂��B���������l�͕��ʂ͖ؒƂ������Ă��܂��������̂͌��������Ă��܂��B������∫����P���Ƃ����Ă��邻���ł��B |
 |
| ���V�ԑ卑�_�� |
 |
�@���V�Ԑ_�Ђ͌Â����疭�`�R�M�̎ЂƂ��ĎQ�q����Ă��܂��B�Гa�̌���ɂ͍���Ƃ�����₪���˂��h���l�ɂ��т��Ă��܂��B |
| ���V�Ԑ_�ЎГa |
| �@���V�Ԑ_�Ђ͂��̍������_�̂Ƃ��Ă���̂Ŕq�a�E���a�݂̂Ŗ{�a���Ȃ��������l���ƂȂ��Ă��܂��B ��a����̑�Q�X��Ԗ��V�c�i�݈�539-571�N�j�̌��ɖ��`�����Гa���������������ł��B���������A��W�Q��㒹�H�V�c�̎��i�Q�N�i1183�j�����S�������_�����[���Ă��܂��B |
 |
 |
�@�]�ˎ���A��P�O�W��㐅���V�c�̌��a�Q�N�i1616�j���������i���m�j���o���������̊J�R��Ƃ��Đ_�������Ă��A���喼�����h����悤�ɂȂ�܂����B |
| �@�������������閭�`�̋����R�i�P�P�O�S���j�ɂ͐퍑���ォ��]�ˎ��㏉���ɂ����Ď��݂����Ƃ����u�����v���m�̓V��`�����c���Ă��܂��B |
 |
 |
�@���������͐퍑���㏬�c���̖k�����Ɏd���Ă������m�̉Ƃɐ��܂ꂽ�����ł��B���m�̕��e�͎E����Ă��܂��������ł��B |
| �@�����̖��n�Ȍ��̘r�ł͋w�����ȂǓ��ꖳ���ł��邱�Ƃ����A���p�̏C�s�̂��ߐ��N�ԁA�����R�ɘU��܂����B�����Č������C�s��ς݁A���ɂ͌��̋Ɉӂ����߂������ł��B |
 |
 |
�@���e�̋w��T���o���ꌂ�̂��Ƃɑ�����a�茩���ɏh����ʂ��������m�͕���ɓ���܂����B�����Ė����u�����v�Ɖ��߂܂����B�����ċ����R�ɖ߂�ƌ��ւ̏C�s�ɖv�����A�a�C�������Ƃ�����ՂȂǂ������Ƃ����Ă��܂��B |
| �@����A���m�͖��`�R�ɐ�������V��̓��̂ƂȂ�A�吨�̓V��𗦂��č��ł��R�x�����̏C�s�҂�R���̐_�Ђ̐��h�҂�������Ă���Ƃ����Ă���̂ł��B |
 |
�r�D��
����ӂ˂�
�Q�n���Êy�S���m�c�����q
Tel 0274-82-2111�@���m�c�����ꏤ�H�ό���

 |
�@�퍑����̓`�����c��A�R�ɕ����ꂽ�_���ł��B�e�������͉Ƒ��A��ɐl�C������܂��B�R�Ԃ̐Â��ȌΔȂ��U��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B |
| �@�ΔȂɂ́A�e�������Ǝq�������ɐl�C�̃��[���[���ׂ�䂪����_������������܂��B |
 |
 |
�@�r�D�ɂ͎��V�R�[�X���ł��Ă��܂��B��������Ί݂��オ��E�݂̐e�������֍s���A�������݂�����_�����������A���ݐe���������܂���Ă����̂ł��B |
| �@�߂��ɂ͈����O�̑�Ȃǎ��R�i���n�������Ď��R�i�ł��܂��B�@ |
 |
�_�Öq��
�����Âڂ����傤
�Q�n���Êy�S���m�c�����q�Q�T�O
Tel 0274-84-2363
.JPG) |
�@�����Q�O�N�i1887�j�n�݂̓��{���̗m���q��ł��B ���쌧�k���v�S�u�ꑺ�o�g�̐_�ÖM���Y���ɂ���ĊJ�݂��ꂽ�����ł��B |
| �@���쌧���̕W���P�O�O�O���̕����R���Ζʂɑ��ʐςR�T�O�w�N�^�[���̖q�ꂪ�L�����Ă��܂��B�V������L��Ȃǂ���������Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�A���v�X�̍����q����v�킹��Ƃ艮���̖q�ɂ���ۓI�ł��B�����ƐG�ꂠ����ӂꂠ���L��Ȃǂ��l�C�ł��B |
| �@���{�ł͒������i��̃W���[�W�[�������F���ѕ��݂����đ����͂�ł��܂��B�R�r��|�j�[�Ȃǂ����q����Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG) |
�@�z���X�^�C������莉�b�ܗL�ʂ������W���[�W�[�����ƁA���̋����������\�t�g�N���[����o�^�[�͍s�ł���قǂ̐l�C�ł��B |
���R����
�������܂�������
�Q�n�������s�S�Q�R�T
Tel 0274-52-2214�@���R�����Ǘ���
 |
�@���R�����͌Q�n���암�̓����s�S�i���ɂ��j�n��ɂ���R�Ԃ̌����ŁA�~�����L���ł��B�����ɂ͂V�O�O�O�{�̓~�����炢�Ă��܂��B�g�t�ƁA�����Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B |
| �@��זg�i�݂��ځj�̎R�X��w�i�ɁA�P�T�O�O�g�����̎O�g��p���đ傫�Ȓr�Ɛ�����g�ݍ��킹���{�i�I�Ȓr����V���뉀������܂��B |
 |
 |
�@���R�����̂���͋S�͍�ʌ��Ƃ̌����߂��ɂ���A���a�Q�X�N�i1954�j�̒��������ɂ��O�g�쑺����S�Β��ɂȂ�A�����P�W�N�i2006�j�̕����̑升���œ����s�ɂȂ�܂����B |
| �@�@�����S�P�N�i1908�j�����̎O�g�쑺�����A���I�푈�̐폟���L�O���đ��̏Z���̋��͂ō����P�O�O�O�{�A�͂����̂��n�܂�ł��B���܂��܂��̒��ɓ~���̕c���S�O�O�{���荬�����Ă��āA�P�P����{����P�Q�����{�܂ł̍g�t�̎����ƉԌ��̋G�߁A�N�ԂQ�x�ɂ킽���č炫�ւ����̂ł��B |
 |
 |
�@�����́A�~���͂قƂ�ǒm���Ă��܂���ł����B�~�ɍ����炢���Ƒ�ςȕ]���ɂȂ��������ł��B�~�����P�J���ɂ܂Ƃ܂��č炭���R�́A���a�P�Q�N�i1937�j�ɍ��̖����E�V�R�L�O���̎w����܂����B |
| �@�~���Ɗ����͖��O�����Ă��܂����A�����͒W�g�F��d�̉Ԃ��P������Q���ɂP���炫�A�~���̂悤�ɕς�����炫�����͂��܂���B |
 |
 |
�@�~���̂Ȃ��ɂQ�x�炫�̏\�����Ƃ����̂�����܂����A����̓R�q�K���i���ފ݁j�n�̍��łP�O���ɊJ�Ԃ��܂��B�ԕق���P�V���ƕs�K���Ŕ��d�炫�̂��̂������A�F�͓~�����Z���s���N�ł��B |
| �@�����k���ɐ������ƁA�ڂ݂͊J�����ɓ~���z���A�t�ɂȂ��Ēg�����Ȃ��Ă���Ԃ��܂��炫�܂��B�P�{�̖łQ�x�Ԃ��炭���ƂɂȂ�܂��B�~���̂Q�x�炫�ł��B |
 |
 |
�@�����Ɍ������č炭�̂ŁA�炫�n�߂Ă���P�������炢�炫�����܂��B��ւ܂���ւƓ~�̌����č炭�̂ŁA�U��Ƃ����Ԑ���ɂȂ��ĎU�邱�Ƃ͂���܂���B���C�������Ȃ�ƁA�ɓ\����悤�ɉԂт炪���ڂ�ł����܂��B |
| �@�~���͏H�ɂȂ��ėt�������āA��x�����ɂ���Ȃ��ƉԂ��悭�炫�܂���B�H���珉�~�̋C��̕ω��ɂ��A�����ɂ��炫�͂��߂܂��B�ł�����A�P�P�����{����P�Q�����{�������ł��B |
 |

 |
�@�~���Ŗ��������R�̎R�[�ł́A�݂�������y���߂܂��B �Q�n���ŗB��A���{�Ŗk���̊ό��݂��������ł��B |
�����V�ƏZ��
���イ���낳�킯���イ����
�Q�n������S��쑺�茴�Q�O�O�|�X
Tel 0274-59-2657 ��쑺����ψ���
.JPG) |
�@��쑺�茴�̍����Q�X�X�������ɋ����V�ƏZ�����܂��B��쑺�����얋�{�̓V�̉��������R���́i������j�̂P�W���I�����̑可���̌��z�ł��B |
| �@����Ƃ͂܂���ю�Ƃ��āA�����p�̑�����炷��䑃��R�̊Ǘ��ɂ��������Ă��������ł��B |
.JPG) |
.JPG)
.JPG) |
�@��K�͂Ȑ؍ȑ���̌��z�ł��B�Ԍ��Q�Q���A���ʂP�U���̑��Q�K���A�傫�Ȍ��ւ��Q�����Ȃ��Ă��܂��B�����͔����Ő��u����Ă��܂��B |
| �@���~�⌺�ւȂǂ̈ӏ��͑f���炵���喼��Ƃ��Ă̊i�����ւ��Ă��܂��B�㊯���}���邽�߂́u�����炷�v������A���̍s���ɗ��p���ꂽ�����A�䏊���R�J��������܂��B |
.JPG) |
.JPG)
.JPG) |
�@�q���~��4��������A�͘F���̂��钃�̊Ԃ͂R�P�������̍L��������܂��B��̊K�͐̂͗{�\�Ɏg���Ă������ł��B���݂͏�쑺�̖����������W������Ă��܂��B
�@ |
| �@�R�����鋌�Ƃ̐�����`����可���̏Z��ł��B���a�S�T�N�i1970�j���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B |
.JPG) |
.JPG)
.JPG) |
�@.JPG) |
 ���Ɨ��j�̃z�[���y�[�W�����ǂ� ���Ɨ��j�̃z�[���y�[�W�����ǂ�  �@���{�̃y�[�W�ւ��ǂ�@�@�@�@ �@���{�̃y�[�W�ւ��ǂ�@�@�@�@
|
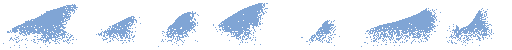



 ���Ɨ��j�̃z�[���y�[�W�����ǂ�
���Ɨ��j�̃z�[���y�[�W�����ǂ�  �@���{�̃y�[�W�ւ��ǂ�@�@�@�@
�@���{�̃y�[�W�ւ��ǂ�@�@�@�@



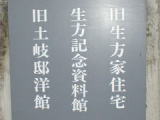

.jpg)






.jpg)


.jpg)



























